愛のゆくえ 「雪国」その5
「白い朝の鏡」
つづけて『改造』に書かれた続編では、はじめに、読者を面食らわせないないためだろうか、芸者代わりに呼んだ女とのいきさつが少し書いてある。
それから、つづきがあって、間もなく来た芸者を一目見ると、「島村の山から里へ出た時の女ほしさは、味気なく消えてしまった」ので、郵便局の時間がなくなるという口実をもうけて芸者を返す。そして、若葉の匂いの強い裏山へ登ってゆく。ほどよく疲れて、駈け下りてくると、
「どうなすつたの?」と、女が杉林の陰に立つてゐた。
「うれしさうに笑つてらつしやるわよ。」
「止めたよ。」と、彼はまたわけのない笑ひがこみ上げて来て、 「もう止めだ。」
「さう?」と、女は表情のなくなつた顔であちらを向くと、杉 林のなかへゆつくり入つた。彼は黙つてついて行つた。
神社であつた。苔のついた駒(ママ)犬の傍の平な岩に、女は腰を下 して、
「ここが一等涼しいの。真夏でも冷い風がありますわ。」
ここでふたりは会話をかわしながら、夕暮れまでの時間を過ごす。島村のとらえた女の特徴も書きこまれている。
「少し中高の円顔は平凡な輪郭ながら、白陶器に薄紅を刷いたやうな皮膚で、首のつけ根も肉づいてゐないから、美人といふよりもなによりも、清潔だつた。」
自分の男を呼ぶ声
それから問題の場面が登場する。
その夜の10時ごろ、女が廊下から島村の名を大声で呼んで、ばたりと倒れるように彼の部屋へ入ってくる。宴会の途中だった。
「悪いから行つて来るわね。後でまた来るわね」と、よろけながら出て行く。
一時間ほどしてまた廊下にみだれた足音で、
「島村さあん、島村さあん。」と、助けを求めるやうに叫んだ。それはもうまぎれもなく、酔つたあげくの本心で、女が自分の男を呼ぶ声であった。それは島村の胸のなかへ飛びこんで、むしろ思ひがけないほどだつたが、宿屋中に聞えてゐるにちがひなかつたから、当惑して立ち上がると、女は障子紙に指をつつこんで桟(さん)をつかみ、そのまま……〈伏せ字8字〉倒れかかつた。
「女が自分の男を呼ぶ声」とは、女が自分の好きな男を呼ぶ声、の意味だろう。
ちなみに、現行の定本では、この箇所はみごとに彫琢されて、こんなに簡潔な文章に変わっている。
一時間ほどすると、また長い廊下にみだれた足音で、あちこちに突きあたつたり倒れたりして来るらしく、
「島村さあん、島村さあん。」と、甲高く叫んだ。
「ああ、見えない。島村さあん。」
それはもうまぎれもなく女の裸の心が自分の男を呼ぶ声であつた。島村は思ひがけなかつた。
女は酔って、本心から、「自分の男」を呼んだのである。
だが、女はいつのまに、島村を「自分の男」と思うようになったのか。
さきほどの夕暮れの杉林の中での会話からだろうか。前夜、芸者の代わりに呼ばれて、島村と話が合ったからであろうか。それとも、今日の午後、芸者を呼んでくれと、失礼なことを云われたことが、かえって女の心を刺激したのか。
いずれにしても、前夜、ふたりの話の合ったことが基本であろう。だからこそ好意を抱いて、女は翌日の午後、島村の部屋を遊びに訪れたのである。それなのに芸者を世話してくれといわれて、女の心は傷ついた。しかしこの危機は、女の素直な心によって回避された。
しかし、それでもなお、女がここまで深く島村を思ってしまった心の因はわからない。
女の心はわからないままに、物語は進行する。
島村の部屋で、女は酔ったままにさまざまな姿をみせるが、結局、島村に抱かれることになる。しかしその時になっても、「お友達でゐようつて、あなたがおつしやつたぢやないの」と、幾度繰り返したかしれなかった。
島村はその言葉の真剣な響きに打たれ、また、固く渋面をつくつて自分を抑へてゐる意志の強さには味気なくなるほどで、女との約束を守ろうかとさえ思うのである。
この場面の初出は伏せ字だらけで、意味が通らないので、定本によって補正すると、
「私はなんにも惜しいものはないのよ、決して惜しいんぢやないのよ。だけど、さういふ女ぢやない。私はさういふ女ぢやないの。きつと長続きしないつて、あんた自分で言つたぢやないの。」(中略)などと口走りながら、よろこびにさからふために袖をかんでゐた。
女はこんなに簡単に男に身を任せることで、男が誤解することを恐れているのだ。好きな男にあげる。だから惜しいんじゃない。だけど、あなたは誤解する。あたしが、こんなふうに誰にだって簡単に身を任せてしまう女だと誤解する。それは違う!
女は、よろこびがこみ上げてくるなかで、それに逆らいながら、必死で言いつのっているのだ。
……しばらく気が抜けたみたいに静かだったが、女はふと突き刺すように、
「あなた笑つてるわね。私を笑つてるわね。」と言って、泣くのである。旅の男に簡単に身を任せた、男からすれば、据え膳喰わぬは……と、そんな女を安っぽい、尻の軽い女として馬鹿にするだろう。女は、そう思われることを避けようと、必死で男を刺すのである。
この場面は、女が行きずりの島村に本気で惚れて身を任せ、その自分の気持ちを軽いものと誤解されることを恐れていると、読者に繰り返し訴える。女の真剣な好意がつよく印象づけられるシーンである。
それとともに、そのように言わねばならぬほど、男に容易に身を任せてしまった女の哀れが読者に迫ってくる。
「白い朝の鏡」は、それから女が夜が明けるのを恐れて、宿の人が起きる前に帰ってゆくところで閉じられる。
「夕景色の鏡」との対照は、この作品では書かれずじまいだったのである。
「物語」
「夕景色の鏡」「白い朝の鏡」と1935年(昭和10年)の新年号に発表されたまま、作品は1年ちかく放置される。
次に第3作「物語」、第4作「徒労」が発表されるのは、同年11月号、12月号のことである。
先にも指摘したように、その秋の康成の3度目の越後湯沢への旅が、「余情」を後に残す契機となったのである。
「物語」も、読者にこれまでの経緯を説明するところから始まっている。女が夜明けに宿を抜け出して帰っていったあと、「その日島村は東京へ帰つてしまつた。女の名も聞き忘れたほどの別れやうであつた。」
それから、新しい「物語」が始まる。
女はしきりに指を折って勘定している。島村が問うと、「5月の23日ね」といい、今夜がちょうど「199日目だわ」と応えるのである。
ここは、これまでいくつもの論考で指摘されてきたように、平安の昔に、深草(ふかくさ)の少将が小野小町を99夜たずねた、その故事「深草少将の百夜(ももよ)通い」に関連づけているのであろう。女は、自分たちの関係に何か意味を見出そうとしているのである。
それから、この「物語」の中心となる、女の生きる姿が示される
「だけど、五月の二十三日つて、よく覚えてるね。」
「日記を見れば、直ぐ分るわ。」
「日記、日記をつけるのか。」
「ええ、古い日記を見るのは楽しみですわ。なんでも隠さずその通りに書いてあるから、ひとりで読んでゐても恥しいわ。」
「いつから?」
「東京でお酌に出る少し前から。(以下略)」
これだけでも島村を驚かすには十分だったが、島村をもっと驚かせたのは、女が、読んだ小説を1つ1つ雑記帳に書きつけている、ということだった。
日記の話よりも、尚島村が意外の感に打たれたのは、彼女は十六の頃から、読んだ小説を一一書き留めておき、そのための雑記帳がもう十冊にもなつたといふことであつた。
「感想を書いとくんだね?」
「感想なんか書けませんわ。題と作者と、それから出て来る人物の名前と、その人達の関係と、それくらゐのものですわ。」
「そんなものを書き止めといたつて、しやうがないぢやないか。」
「しやうがありませんわ。」
「徒労だね。」
「さうですわ。」と、女はこともなげに明るく答へて、しかしぢつと島村を見つめてゐた。
全くの徒労であると、島村はなぜかもう一度声を強めようとした途端に、しいんと雪の鳴るやうな静けさが身にしみて/それは女に惹きつけられたのであつた。
島村は、女の意外な一面を知って驚く。山深い田舎のひとりの無名の女が、読んだ小説の題名をノートにつけたとて、いったいそれが何の役にたつというのだろう。
彼女にとつては、それが徒労であらうはずがないとは彼も知 りながら、頭から徒労だと叩きつけると、なにか反つて彼女の 存在が純粋に感じられるのであつた。
このとき初めて、島村は女に惚れたのである。あるいは、女の一生懸命に生きている姿を知って、そこにひとりの女の生きる息づかいを感じて、女に対する心からの愛情が湧いてきたのである。
……その夜、つまり再会の最初の夜も、女は島村の部屋に泊まって朝を迎える。
部屋が明るんでくると、女の赤い頬があざやかに見えてくる。寒いせいだろうと島村が訊くと、白粉(おしろい)を落としたからだ、と女は答える。
「寒いんぢやないわ。白粉を落したからよ。私は寝床へ入ると直ぐ、足の先までぽつほ(ママ)して来るの。」と、島村の枕もとの鏡台に向つて、
「たうとう明るくなつてしまつたわ。帰りますわ。」
島村はその方を見て、ひよつと首を縮めた。鏡の奥が真白に光つてゐるのは雪である。その雪のなかに、女の真赤な頬が浮んでゐる。なんともいへぬ清潔な美しさであつた。
この場面でようやく、康成の初めの構想――「夕景色の鏡」と、人差指が覚えていた女の「白い朝の鏡」との照応が完成するのである。
1つの短篇で終わるはずだった作品が、3作めの「物語」の最後になって、やっと当初の目的を完成したのである。康成は、ここでこの連作を終わってもよかった。
それがさらに次の「徒労」へとつづいてゆくのは、この「物語」の中で、日記をつけているばかりか、読んだ小説を雑記帳に書きとめているという、ひとりの女の、徒労の生を懸命に生きている姿を知って、男の内部に、遊びごとではない、女への真剣な思いが芽生えたからである。
これが「余情が後に残って」の意味であろう。ここから、作品は真剣な愛を抱いた男と女の物語へと変貌してゆくのである。
「白い朝の鏡」
つづけて『改造』に書かれた続編では、はじめに、読者を面食らわせないないためだろうか、芸者代わりに呼んだ女とのいきさつが少し書いてある。
それから、つづきがあって、間もなく来た芸者を一目見ると、「島村の山から里へ出た時の女ほしさは、味気なく消えてしまった」ので、郵便局の時間がなくなるという口実をもうけて芸者を返す。そして、若葉の匂いの強い裏山へ登ってゆく。ほどよく疲れて、駈け下りてくると、
「どうなすつたの?」と、女が杉林の陰に立つてゐた。
「うれしさうに笑つてらつしやるわよ。」
「止めたよ。」と、彼はまたわけのない笑ひがこみ上げて来て、 「もう止めだ。」
「さう?」と、女は表情のなくなつた顔であちらを向くと、杉 林のなかへゆつくり入つた。彼は黙つてついて行つた。
神社であつた。苔のついた駒(ママ)犬の傍の平な岩に、女は腰を下 して、
「ここが一等涼しいの。真夏でも冷い風がありますわ。」
ここでふたりは会話をかわしながら、夕暮れまでの時間を過ごす。島村のとらえた女の特徴も書きこまれている。
「少し中高の円顔は平凡な輪郭ながら、白陶器に薄紅を刷いたやうな皮膚で、首のつけ根も肉づいてゐないから、美人といふよりもなによりも、清潔だつた。」
自分の男を呼ぶ声
それから問題の場面が登場する。
その夜の10時ごろ、女が廊下から島村の名を大声で呼んで、ばたりと倒れるように彼の部屋へ入ってくる。宴会の途中だった。
「悪いから行つて来るわね。後でまた来るわね」と、よろけながら出て行く。
一時間ほどしてまた廊下にみだれた足音で、
「島村さあん、島村さあん。」と、助けを求めるやうに叫んだ。それはもうまぎれもなく、酔つたあげくの本心で、女が自分の男を呼ぶ声であった。それは島村の胸のなかへ飛びこんで、むしろ思ひがけないほどだつたが、宿屋中に聞えてゐるにちがひなかつたから、当惑して立ち上がると、女は障子紙に指をつつこんで桟(さん)をつかみ、そのまま……〈伏せ字8字〉倒れかかつた。
「女が自分の男を呼ぶ声」とは、女が自分の好きな男を呼ぶ声、の意味だろう。
ちなみに、現行の定本では、この箇所はみごとに彫琢されて、こんなに簡潔な文章に変わっている。
一時間ほどすると、また長い廊下にみだれた足音で、あちこちに突きあたつたり倒れたりして来るらしく、
「島村さあん、島村さあん。」と、甲高く叫んだ。
「ああ、見えない。島村さあん。」
それはもうまぎれもなく女の裸の心が自分の男を呼ぶ声であつた。島村は思ひがけなかつた。
女は酔って、本心から、「自分の男」を呼んだのである。
だが、女はいつのまに、島村を「自分の男」と思うようになったのか。
さきほどの夕暮れの杉林の中での会話からだろうか。前夜、芸者の代わりに呼ばれて、島村と話が合ったからであろうか。それとも、今日の午後、芸者を呼んでくれと、失礼なことを云われたことが、かえって女の心を刺激したのか。
いずれにしても、前夜、ふたりの話の合ったことが基本であろう。だからこそ好意を抱いて、女は翌日の午後、島村の部屋を遊びに訪れたのである。それなのに芸者を世話してくれといわれて、女の心は傷ついた。しかしこの危機は、女の素直な心によって回避された。
しかし、それでもなお、女がここまで深く島村を思ってしまった心の因はわからない。
女の心はわからないままに、物語は進行する。
島村の部屋で、女は酔ったままにさまざまな姿をみせるが、結局、島村に抱かれることになる。しかしその時になっても、「お友達でゐようつて、あなたがおつしやつたぢやないの」と、幾度繰り返したかしれなかった。
島村はその言葉の真剣な響きに打たれ、また、固く渋面をつくつて自分を抑へてゐる意志の強さには味気なくなるほどで、女との約束を守ろうかとさえ思うのである。
この場面の初出は伏せ字だらけで、意味が通らないので、定本によって補正すると、
「私はなんにも惜しいものはないのよ、決して惜しいんぢやないのよ。だけど、さういふ女ぢやない。私はさういふ女ぢやないの。きつと長続きしないつて、あんた自分で言つたぢやないの。」(中略)などと口走りながら、よろこびにさからふために袖をかんでゐた。
女はこんなに簡単に男に身を任せることで、男が誤解することを恐れているのだ。好きな男にあげる。だから惜しいんじゃない。だけど、あなたは誤解する。あたしが、こんなふうに誰にだって簡単に身を任せてしまう女だと誤解する。それは違う!
女は、よろこびがこみ上げてくるなかで、それに逆らいながら、必死で言いつのっているのだ。
……しばらく気が抜けたみたいに静かだったが、女はふと突き刺すように、
「あなた笑つてるわね。私を笑つてるわね。」と言って、泣くのである。旅の男に簡単に身を任せた、男からすれば、据え膳喰わぬは……と、そんな女を安っぽい、尻の軽い女として馬鹿にするだろう。女は、そう思われることを避けようと、必死で男を刺すのである。
この場面は、女が行きずりの島村に本気で惚れて身を任せ、その自分の気持ちを軽いものと誤解されることを恐れていると、読者に繰り返し訴える。女の真剣な好意がつよく印象づけられるシーンである。
それとともに、そのように言わねばならぬほど、男に容易に身を任せてしまった女の哀れが読者に迫ってくる。
「白い朝の鏡」は、それから女が夜が明けるのを恐れて、宿の人が起きる前に帰ってゆくところで閉じられる。
「夕景色の鏡」との対照は、この作品では書かれずじまいだったのである。
「物語」
「夕景色の鏡」「白い朝の鏡」と1935年(昭和10年)の新年号に発表されたまま、作品は1年ちかく放置される。
次に第3作「物語」、第4作「徒労」が発表されるのは、同年11月号、12月号のことである。
先にも指摘したように、その秋の康成の3度目の越後湯沢への旅が、「余情」を後に残す契機となったのである。
「物語」も、読者にこれまでの経緯を説明するところから始まっている。女が夜明けに宿を抜け出して帰っていったあと、「その日島村は東京へ帰つてしまつた。女の名も聞き忘れたほどの別れやうであつた。」
それから、新しい「物語」が始まる。
女はしきりに指を折って勘定している。島村が問うと、「5月の23日ね」といい、今夜がちょうど「199日目だわ」と応えるのである。
ここは、これまでいくつもの論考で指摘されてきたように、平安の昔に、深草(ふかくさ)の少将が小野小町を99夜たずねた、その故事「深草少将の百夜(ももよ)通い」に関連づけているのであろう。女は、自分たちの関係に何か意味を見出そうとしているのである。
それから、この「物語」の中心となる、女の生きる姿が示される
「だけど、五月の二十三日つて、よく覚えてるね。」
「日記を見れば、直ぐ分るわ。」
「日記、日記をつけるのか。」
「ええ、古い日記を見るのは楽しみですわ。なんでも隠さずその通りに書いてあるから、ひとりで読んでゐても恥しいわ。」
「いつから?」
「東京でお酌に出る少し前から。(以下略)」
これだけでも島村を驚かすには十分だったが、島村をもっと驚かせたのは、女が、読んだ小説を1つ1つ雑記帳に書きつけている、ということだった。
日記の話よりも、尚島村が意外の感に打たれたのは、彼女は十六の頃から、読んだ小説を一一書き留めておき、そのための雑記帳がもう十冊にもなつたといふことであつた。
「感想を書いとくんだね?」
「感想なんか書けませんわ。題と作者と、それから出て来る人物の名前と、その人達の関係と、それくらゐのものですわ。」
「そんなものを書き止めといたつて、しやうがないぢやないか。」
「しやうがありませんわ。」
「徒労だね。」
「さうですわ。」と、女はこともなげに明るく答へて、しかしぢつと島村を見つめてゐた。
全くの徒労であると、島村はなぜかもう一度声を強めようとした途端に、しいんと雪の鳴るやうな静けさが身にしみて/それは女に惹きつけられたのであつた。
島村は、女の意外な一面を知って驚く。山深い田舎のひとりの無名の女が、読んだ小説の題名をノートにつけたとて、いったいそれが何の役にたつというのだろう。
彼女にとつては、それが徒労であらうはずがないとは彼も知 りながら、頭から徒労だと叩きつけると、なにか反つて彼女の 存在が純粋に感じられるのであつた。
このとき初めて、島村は女に惚れたのである。あるいは、女の一生懸命に生きている姿を知って、そこにひとりの女の生きる息づかいを感じて、女に対する心からの愛情が湧いてきたのである。
……その夜、つまり再会の最初の夜も、女は島村の部屋に泊まって朝を迎える。
部屋が明るんでくると、女の赤い頬があざやかに見えてくる。寒いせいだろうと島村が訊くと、白粉(おしろい)を落としたからだ、と女は答える。
「寒いんぢやないわ。白粉を落したからよ。私は寝床へ入ると直ぐ、足の先までぽつほ(ママ)して来るの。」と、島村の枕もとの鏡台に向つて、
「たうとう明るくなつてしまつたわ。帰りますわ。」
島村はその方を見て、ひよつと首を縮めた。鏡の奥が真白に光つてゐるのは雪である。その雪のなかに、女の真赤な頬が浮んでゐる。なんともいへぬ清潔な美しさであつた。
この場面でようやく、康成の初めの構想――「夕景色の鏡」と、人差指が覚えていた女の「白い朝の鏡」との照応が完成するのである。
1つの短篇で終わるはずだった作品が、3作めの「物語」の最後になって、やっと当初の目的を完成したのである。康成は、ここでこの連作を終わってもよかった。
それがさらに次の「徒労」へとつづいてゆくのは、この「物語」の中で、日記をつけているばかりか、読んだ小説を雑記帳に書きとめているという、ひとりの女の、徒労の生を懸命に生きている姿を知って、男の内部に、遊びごとではない、女への真剣な思いが芽生えたからである。
これが「余情が後に残って」の意味であろう。ここから、作品は真剣な愛を抱いた男と女の物語へと変貌してゆくのである。












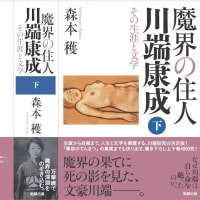
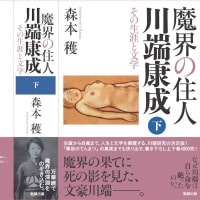

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます