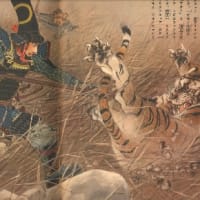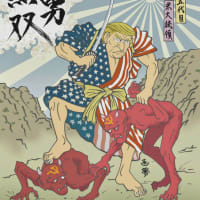神社での祈祷や地鎮祭などで祝詞をお聞きになったことのある方は多いであろう。普段馴染みのない方にとってはまさに「唐人の寝言」のようであり、何を言っているのか良く分からないうえに、あの独特の節まわしは奇妙なものと思われるかもしれない。しかし、前回、前々回の記事に掲載した祝詞や下記の参考HPをごらんになって頂ければ良くお分かりになると思う。
祝詞は基本的にやまとことばで書かれるものである。漢字も音読みではなくわが国古来の訓読みにされていることにお気づきになるだろう。原語の音に漢字を当てただけの仏教のお経に比べれば、はるかに祝詞のほうが分かりやすいものなのである。
やまとことばで書かれたもので、私たちに馴染みの深いものは和歌である。和歌を単に声を出して読んでも、伝わってくるものは少ない。しかし和歌を朗詠(節をつけて詠うこと)すると(歌会初めや百人一首を思い出していただきたい)、不思議なことに、作者の心理や情景が生き生きとして心に伝わってくる。これはいったい何故なのだろうか。
海外スピリチュアリズムの翻訳家で知られる近藤千雄氏は著書『日本人の心のふるさと《かんながら》と近代の霊魂学《スピリチュアリズム》』の中で、単語の末尾が母音で終わることの多い日本語の特徴を解説し、やまとことばの持つ不思議な力を次のように述べている。
(引用開始)
例えば「ありがとうございます」を幼児言葉の抜け切れない子供に言わせると、「あ・り・が・と・う・ご・ざ・い・ま・す」と、一語一語はっきりと発音する。言い換えれば、一語一語に母音が付いている。これが成長とともに母音が薄れて発音されるようになる。特に最後の「ます」はほとんど子音だけのように響く。専門語でいうと無声音に移行する。ところが感謝の気持ちをこめて述べる時は、最後まで母音をはっきりと発音するものである。ここに何か言霊の秘密のようなものがある。
(引用終了)
近藤氏の言うように、最後まで母音をはっきりと発音し、強調することが言霊の秘密であるとすれば、祝詞に見られる、緩やかに一語一語を明瞭に詠みあげ、語尾を延ばす詠法は、当然ながら母音を強調する有効な方法となる。
つまり祝詞独特の詠法は、「心と思いの霊力」を言の葉に込めることに他ならないのである。
●参考HP 上野八幡神社 祝詞集
http://www.h3.dion.ne.jp/~tsutaya/newpage13.htm
最近の「神社と古神道の教え」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
- 台湾(2)
- 今日のちょっと見、拾い読み(23)
- 安全保障(21)
- 米中戦争(1)
- ロシア(ソ連)の大犯罪!シベリア抑留(1)
- ディープステート(4)
- もうひとつの無法国家 北朝鮮(2)
- 韓国崩壊(0)
- 中国滅亡(13)
- 教科書検定不正問題(4)
- 大東亜戦争(2)
- アイヌ利権(1)
- アメリカ大統領選(0)
- アメリカ大統領選挙(4)
- 情報ソース(0)
- デジタル言論統制(0)
- トランプ大統領(0)
- ビックテック(0)
- チャイナ利権(0)
- お清め(0)
- スメラミコト(2)
- 日本の心(7)
- 美しの国ニッポン(32)
- 日本人に謝りたい(9)
- 日本の今を考える(71)
- 日本人必見!軍事講座(4)
- 情弱とお花畑が思考停止する「軍事と国防」(6)
- 「左翼に騙されるな」アンチ左巻き講座(2)
- WGIP覚醒講座(2)
- 知っ得、納得「政治・経済」(6)
- 反日種族主義 ビデオ講座(4)
- 売国奴・売国企業図鑑(15)
- 在日問題(16)
- 中共のウィグル人弾圧と人権侵害(4)
- 中共の蛮行・愚行(32)
- 中共の臓器移植・臓器狩り・大量虐殺 (3)
- 武漢ウィルス ・武漢肺炎(16)
- 中共の超限戦(3)
- 沖縄が危ない! 中国、北朝鮮、韓国(1)
- 体験的昭和戦後史(4)
- 国連・国際機関の深い闇 (3)
- ユダヤの陰謀(45)
- 今そこにある日本の危機(5)
- 神社と古神道の教え(25)
- スピリチュアル(59)
- 死後の世界(19)
- 世界宗教の真実(18)
- 昭和ノスタルジー(7)
- 意識のパワーレベル(9)
- 易と手相(14)
- 爬虫類人とプラズマ兵器(36)
- ケムトレイル(18)
- もったいない(3)
- 食の安全と健康(3)
- 医療の虚実(8)
- その他(24)
バックナンバー
人気記事