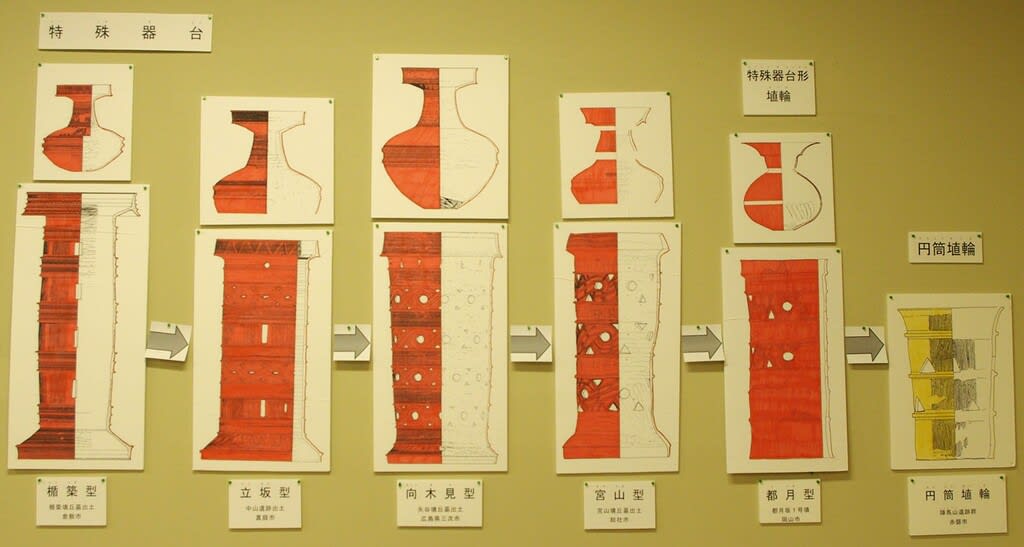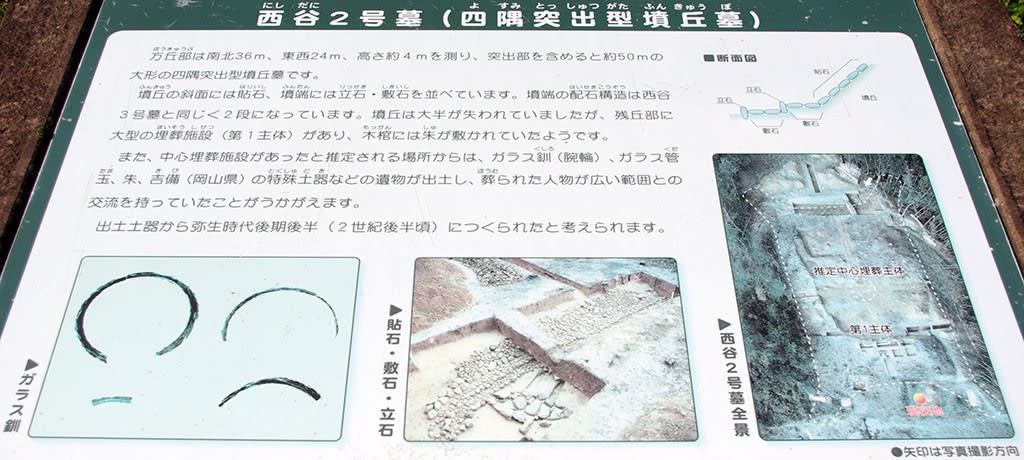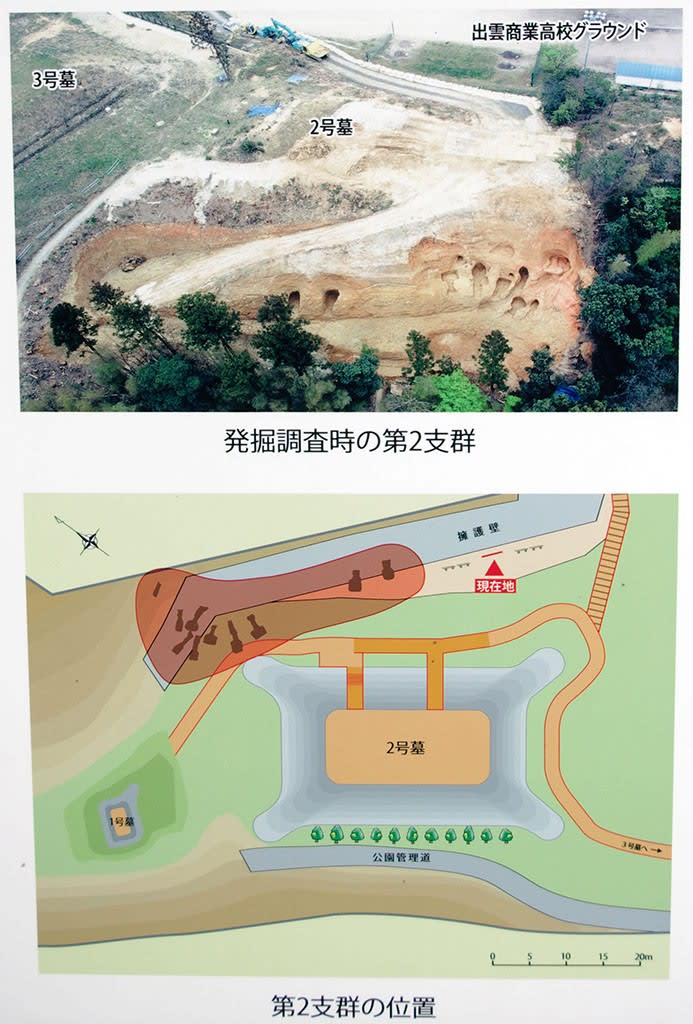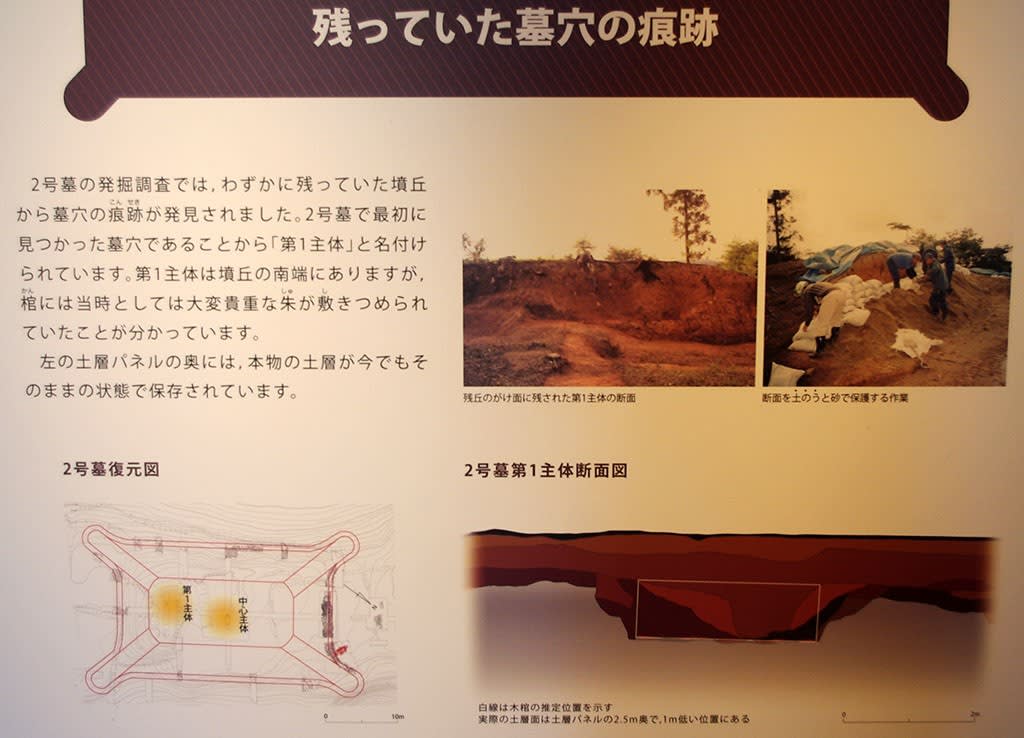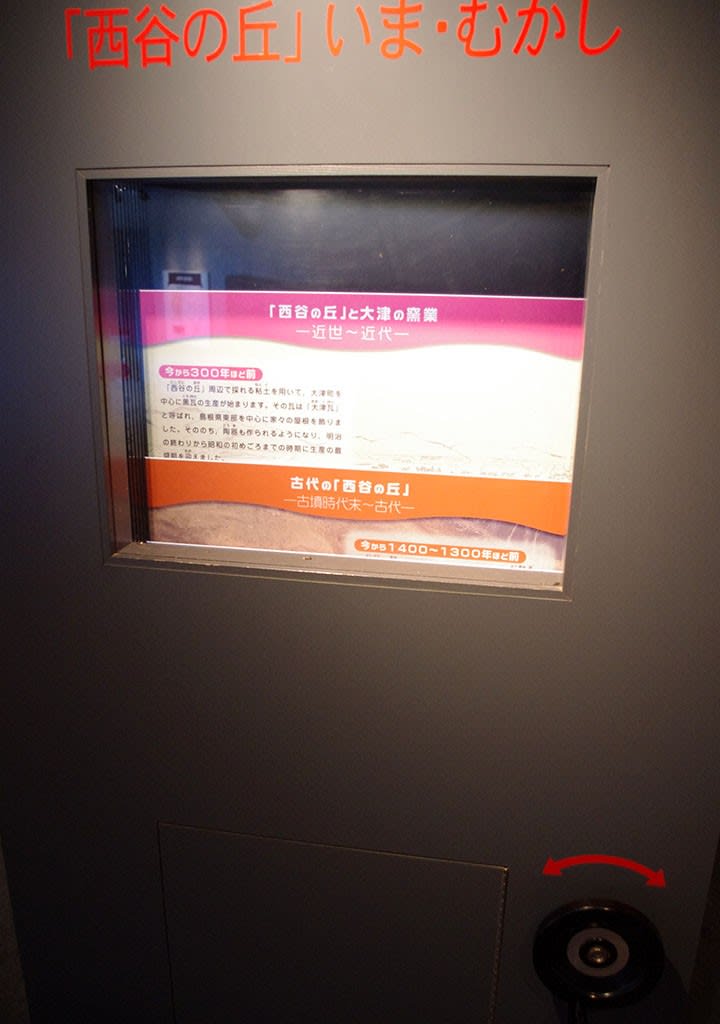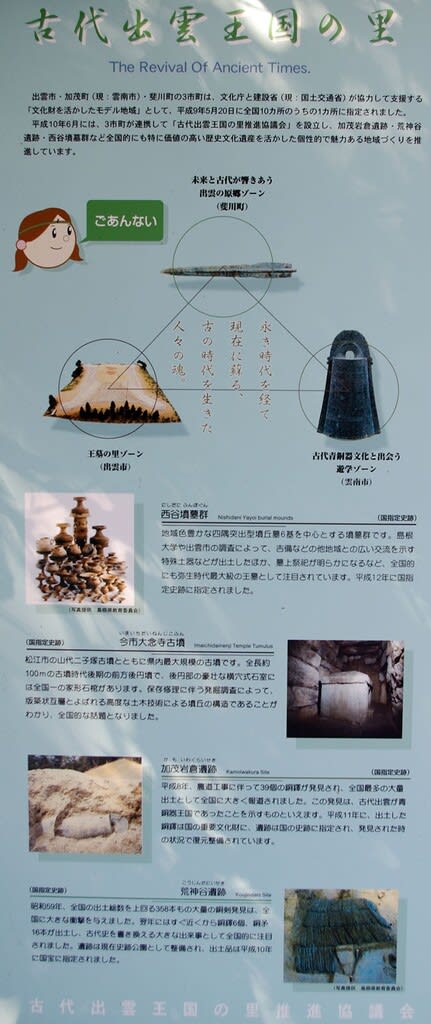⇒この記事の前の「沖縄空撮および島添大里城跡」はこちら
美味しい沖縄そばを食べて、腹ごしらえもバッチリということで、本日のメイン探訪地であるガンガラーの谷へやってきました。

たまにガンガラーの谷のことを、「ガンガーラの谷」と呼ぶ人がいますが、それはすなわち、GODIEGOの「ガンダーラ」の影響であり、世代がバレてしまいます。
私は確かあの頃は保育園児だった・・・
ガンガラーの谷は観光スポットととして著名ですが、古代史マニアの間では「サキタリ洞遺跡」という遺跡名で有名です。
ただし、勝手にひょろっと侵入して見学することはできず、入場料を支払って、きちんとガイドの方の説明を聴きながら歩くシステムになっているので気を付けましょう。

大きな洞窟が口を開けていますよ。


ガイドの開始時間まではカフェで寛いで待機します。

本物の洞窟の中にいますが、なんて快適なんだろうか。

もちろん整備してこういうふうになっているために居心地の良さが増しているのだと思いますが、洞窟遺跡のイメージが覆りました。
違う組のガイドが始まったようです。

少しして、私が属する組の番が回ってきました。

最初は椅子に座らされて全体的な説明があり、ついで、用意されたさんぴん茶の入った水筒を持って探訪開始です。
多くの参加者は「ガンガラーの谷」を楽しむために来ていると思いますが、私はサキタリ洞遺跡が気になります。
こちらがその発掘地点の一つです。


この地点から見つかった遺物。

沖縄県最古の石器が1万4000年前というのにはビックリしました。
というのも、1万4000年前って本土ではもう縄文時代ですから、沖縄って旧石器時代には石器が見つかっていないということになるじゃないですか。
旧石器時代なのに石器が見つかっていない。
沖縄には港川人をはじめとして、旧石器時代の人骨が多数見つかっているわけですが、彼らが使っていた石器は見つかっていないんですね。
※最古の釣針などの出土遺物はこの翌々日に訪れた沖縄県立博物館でレプリカが展示してありました。


なお、洞窟入口側のビニールシートを被らされている場所も発掘地点です。

では、出発!
洞窟から外に出て谷へ降りていきます。

うわ、太い竹!

というか、あらゆる植物がでかい。
今はオープンスペースになっているこの谷沿いの場所も、はるか昔は洞窟の中だったそうです。
というのも崖に鍾乳石が見えますが、鍾乳石は洞窟の中でしか生成されないため、崖にそれが見えるということはこの場所が洞窟の中であったことの証拠になるわけです。

でかい葉っぱ。

イモの仲間だそうですが食べられないそうです。
ガジュマルが現れました。

ガイドさんが唐突に「ガジュマルは歩くんです」と言いました。
禅問答でも始まるのかと思いましたが、ガジュマルは移動する植物だそうです。
というのも、この植物は気根が地面に向かって垂れ下がっていきますが、それが地面に付くと幹化して養分を吸収してしまうため、もともと幹だったものが枯れてしまい、そのため樹木自体が前進するというわけです。
私は植物に関してはほとんど知らないため、こういう説明を聴くのはとても楽しい!

つづいて良縁や安産のご利益があるというイナグ洞へ。


さらに谷の奥へ進んでいくと、またも洞窟が現れました。

イグナ洞は女性の洞窟でしたが、この奥はイキガ洞という男性の洞窟だそうです。


ガイドさんが用意してくれたランタンを持って奥へ行きます。


洞窟から出て、岩のトンネルを潜ります。

見事なガジュマルが現れました。

大主(ウフシュ)ガジュマルと呼ばれています。




気根が垂れ下がって地面に張り付いて幹化している状態。

迫力満点。

岩をガッチリと掴んでいるように見えます。

植物の根を張る力ってすごくて、横穴式石室でも木の根の力によって何トンもの石が動かされてしまうんです。


ツリーテラスへやってきました。

ここからは港川遺跡が見えるそうです。

海の方に橋が見えるのですがその右側の森がそうだということです。

ここからも歩いて行ける距離であることから、もしかしたら港川遺跡で見つかった港川人はこの谷を住処にしていたのかもしれないというガイドさんの解説はとても刺激的です。
最後は武芸洞にてまとめのお話です。

ここも発掘地点。
石で囲んだ土抗墓。


開けていますね。

沖縄では旧石器時代の人骨がいくつも見つかっており、例えば港川人は現代沖縄人の祖となったと考える研究者がいます。
しかしその一方で、狭い島内で人口を維持することは難しく、港川人は絶滅してしまったと考える研究者もおり、旧石器時代末期の1万8000年前の下地原洞人以降、貝塚人が現れるまで沖縄では人類の痕跡が途絶えたように見えていました。
ところが、近年調査が進んでいるこのサキタリ洞遺跡では、1万6000年前の子供の犬歯や9000年前の沖縄最古の土器が見つかっており、沖縄の旧石器時代人が死に絶えることなく貝塚時代まで命をつないだ可能性を完全に否定することもできません。
沖縄人だけでなく、日本人全体のルーツを調べるうえで、サキタリ洞遺跡の今後の発掘成果に期待したいです。


しかしこの武芸洞もとても居心地が良いです。
現代と港川人が生きていた2万2000年前は気候が違くて、当時の方が寒いですから確実なことは言えませんが、この洞窟は生活しやすかったと思います。
今日の時点で言えば、ここに住んでもいいと思えるくらい快適です。
たまたま良い時期に訪れたからかもしれませんが、先ほど述べた通り、洞窟遺跡のイメージが覆りましたよ。
やはり、遺跡は実際に訪れてみるべきですね。
そして今回はいつもと違って自分がガイドされる側に回りましたが、とても楽しかった。
初めて見聞きすることばかりだったので、非常に好奇心が刺激されたわけですが、おそらく古墳についてほとんど知らないお客様が、私の解説を聴いたときに受ける感想と同じじゃないかと思いました。
そう考えると私ももっと勉強したり、解説する方法を工夫したりして、お客様が喜んでくださるように努力しないといけないと決意を新たにしました。
⇒この記事の続きはこちら
⇒この記事の前の「沖縄空撮および島添大里城跡」はこちら
美味しい沖縄そばを食べて、腹ごしらえもバッチリということで、本日のメイン探訪地であるガンガラーの谷へやってきました。

たまにガンガラーの谷のことを、「ガンガーラの谷」と呼ぶ人がいますが、それはすなわち、GODIEGOの「ガンダーラ」の影響であり、世代がバレてしまいます。
私は確かあの頃は保育園児だった・・・
ガンガラーの谷は観光スポットととして著名ですが、古代史マニアの間では「サキタリ洞遺跡」という遺跡名で有名です。
ただし、勝手にひょろっと侵入して見学することはできず、入場料を支払って、きちんとガイドの方の説明を聴きながら歩くシステムになっているので気を付けましょう。

大きな洞窟が口を開けていますよ。


ガイドの開始時間まではカフェで寛いで待機します。

本物の洞窟の中にいますが、なんて快適なんだろうか。

もちろん整備してこういうふうになっているために居心地の良さが増しているのだと思いますが、洞窟遺跡のイメージが覆りました。
違う組のガイドが始まったようです。

少しして、私が属する組の番が回ってきました。

最初は椅子に座らされて全体的な説明があり、ついで、用意されたさんぴん茶の入った水筒を持って探訪開始です。
多くの参加者は「ガンガラーの谷」を楽しむために来ていると思いますが、私はサキタリ洞遺跡が気になります。
こちらがその発掘地点の一つです。


この地点から見つかった遺物。

沖縄県最古の石器が1万4000年前というのにはビックリしました。
というのも、1万4000年前って本土ではもう縄文時代ですから、沖縄って旧石器時代には石器が見つかっていないということになるじゃないですか。
旧石器時代なのに石器が見つかっていない。
沖縄には港川人をはじめとして、旧石器時代の人骨が多数見つかっているわけですが、彼らが使っていた石器は見つかっていないんですね。
※最古の釣針などの出土遺物はこの翌々日に訪れた沖縄県立博物館でレプリカが展示してありました。


なお、洞窟入口側のビニールシートを被らされている場所も発掘地点です。

では、出発!
洞窟から外に出て谷へ降りていきます。

うわ、太い竹!

というか、あらゆる植物がでかい。
今はオープンスペースになっているこの谷沿いの場所も、はるか昔は洞窟の中だったそうです。
というのも崖に鍾乳石が見えますが、鍾乳石は洞窟の中でしか生成されないため、崖にそれが見えるということはこの場所が洞窟の中であったことの証拠になるわけです。

でかい葉っぱ。

イモの仲間だそうですが食べられないそうです。
ガジュマルが現れました。

ガイドさんが唐突に「ガジュマルは歩くんです」と言いました。
禅問答でも始まるのかと思いましたが、ガジュマルは移動する植物だそうです。
というのも、この植物は気根が地面に向かって垂れ下がっていきますが、それが地面に付くと幹化して養分を吸収してしまうため、もともと幹だったものが枯れてしまい、そのため樹木自体が前進するというわけです。
私は植物に関してはほとんど知らないため、こういう説明を聴くのはとても楽しい!

つづいて良縁や安産のご利益があるというイナグ洞へ。


さらに谷の奥へ進んでいくと、またも洞窟が現れました。

イグナ洞は女性の洞窟でしたが、この奥はイキガ洞という男性の洞窟だそうです。


ガイドさんが用意してくれたランタンを持って奥へ行きます。


洞窟から出て、岩のトンネルを潜ります。

見事なガジュマルが現れました。

大主(ウフシュ)ガジュマルと呼ばれています。




気根が垂れ下がって地面に張り付いて幹化している状態。

迫力満点。

岩をガッチリと掴んでいるように見えます。

植物の根を張る力ってすごくて、横穴式石室でも木の根の力によって何トンもの石が動かされてしまうんです。


ツリーテラスへやってきました。

ここからは港川遺跡が見えるそうです。

海の方に橋が見えるのですがその右側の森がそうだということです。

ここからも歩いて行ける距離であることから、もしかしたら港川遺跡で見つかった港川人はこの谷を住処にしていたのかもしれないというガイドさんの解説はとても刺激的です。
最後は武芸洞にてまとめのお話です。

ここも発掘地点。
石で囲んだ土抗墓。


開けていますね。

沖縄では旧石器時代の人骨がいくつも見つかっており、例えば港川人は現代沖縄人の祖となったと考える研究者がいます。
しかしその一方で、狭い島内で人口を維持することは難しく、港川人は絶滅してしまったと考える研究者もおり、旧石器時代末期の1万8000年前の下地原洞人以降、貝塚人が現れるまで沖縄では人類の痕跡が途絶えたように見えていました。
ところが、近年調査が進んでいるこのサキタリ洞遺跡では、1万6000年前の子供の犬歯や9000年前の沖縄最古の土器が見つかっており、沖縄の旧石器時代人が死に絶えることなく貝塚時代まで命をつないだ可能性を完全に否定することもできません。
沖縄人だけでなく、日本人全体のルーツを調べるうえで、サキタリ洞遺跡の今後の発掘成果に期待したいです。


しかしこの武芸洞もとても居心地が良いです。
現代と港川人が生きていた2万2000年前は気候が違くて、当時の方が寒いですから確実なことは言えませんが、この洞窟は生活しやすかったと思います。
今日の時点で言えば、ここに住んでもいいと思えるくらい快適です。
たまたま良い時期に訪れたからかもしれませんが、先ほど述べた通り、洞窟遺跡のイメージが覆りましたよ。
やはり、遺跡は実際に訪れてみるべきですね。
そして今回はいつもと違って自分がガイドされる側に回りましたが、とても楽しかった。
初めて見聞きすることばかりだったので、非常に好奇心が刺激されたわけですが、おそらく古墳についてほとんど知らないお客様が、私の解説を聴いたときに受ける感想と同じじゃないかと思いました。
そう考えると私ももっと勉強したり、解説する方法を工夫したりして、お客様が喜んでくださるように努力しないといけないと決意を新たにしました。
⇒この記事の続きはこちら
⇒この記事の前の「沖縄空撮および島添大里城跡」はこちら

























































































































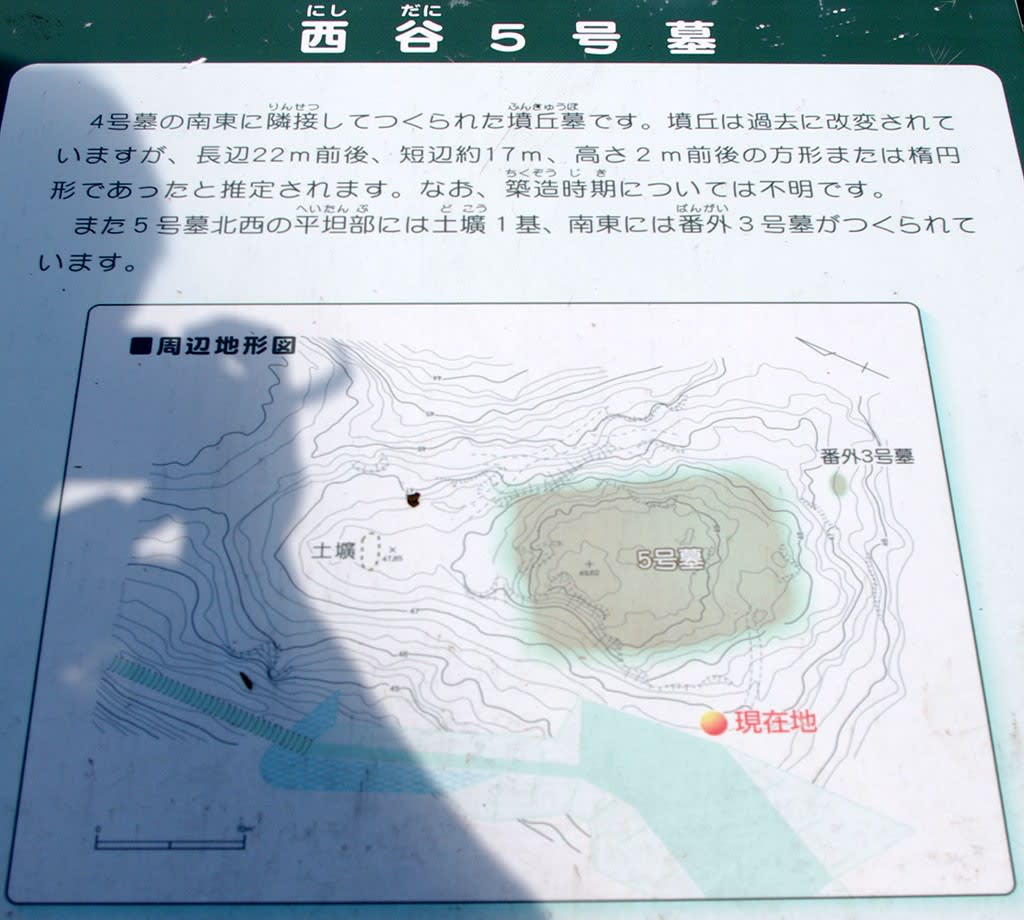










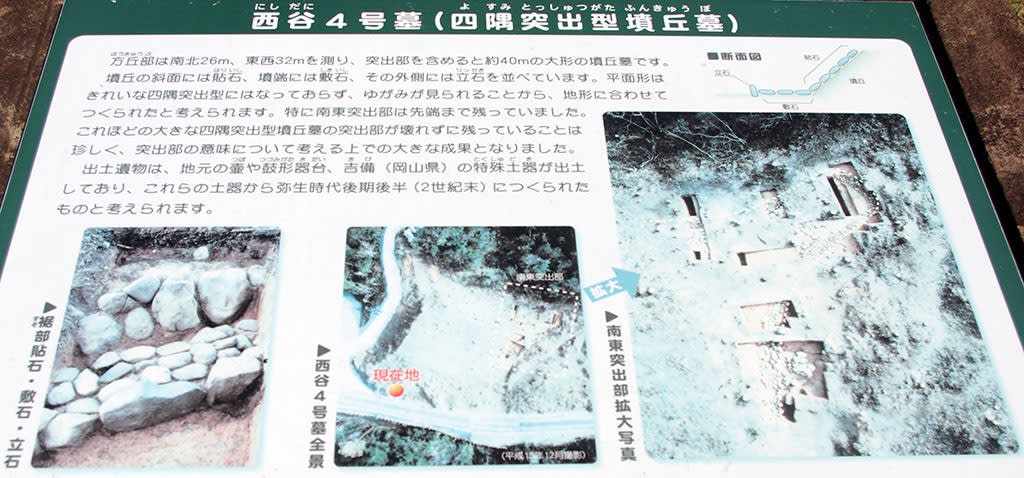










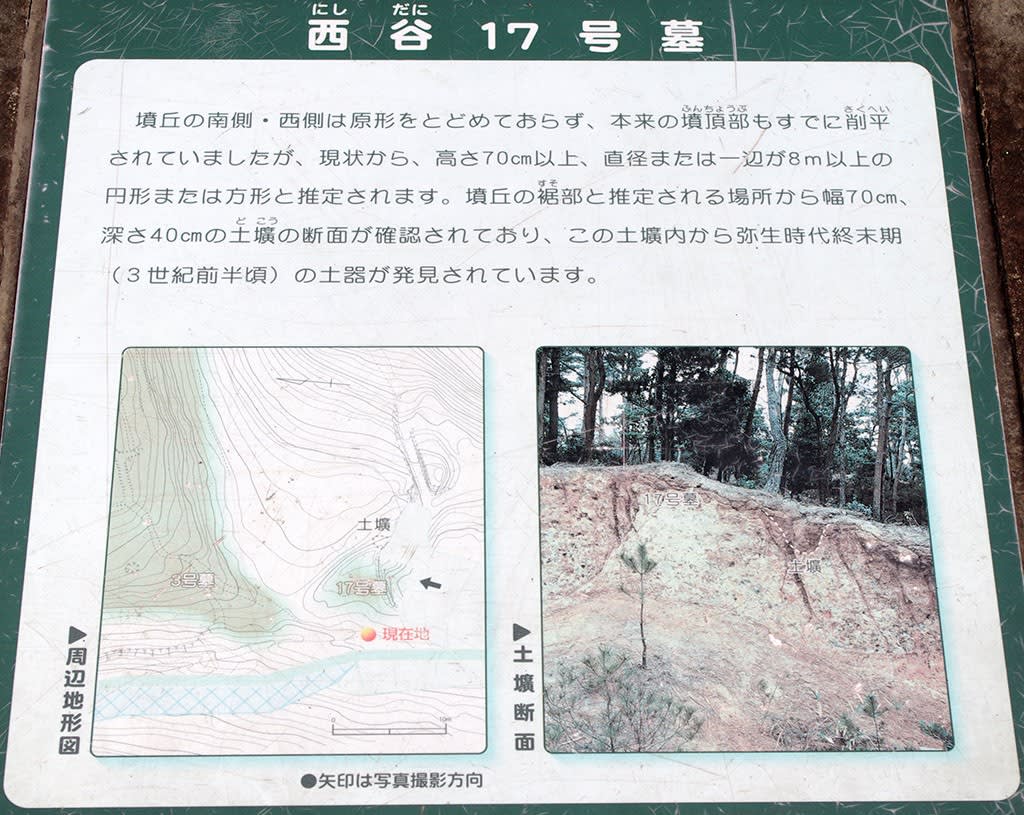





 javascript:void(0)
javascript:void(0)