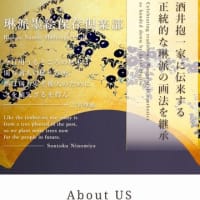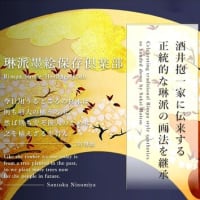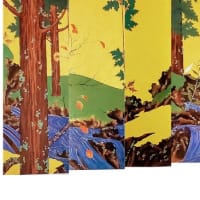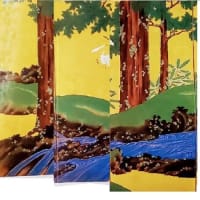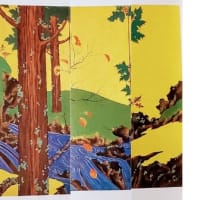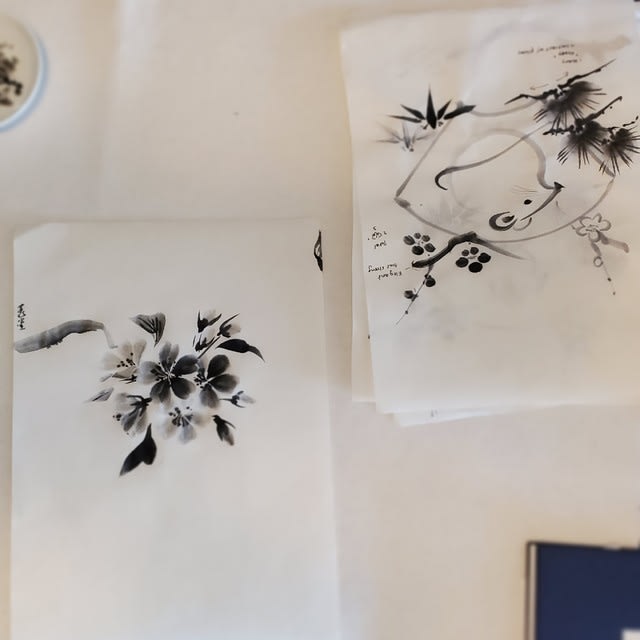
しかし、後から思いましたが、
その書道、華道、茶道の先生方は
どういう方だったのでしょう。
またどうせ外人だから仕方ないか、とでも
お考えだったのでしょうか。
どういう経緯で、「お前には出来る」と変な自信を持たせてしまったのでしょう。
まったく 不思議です。

(↑画像がどうしても反転して直らないのですが、芥子園画伝-山水から樹木を学ぶ。)
日本の事は 日本人と同じように学ばせて然るべきだと私は考えています。
面倒に思っても、説明しないといけないのが 義務というものです。
ついて来られないと言われたら、
その時こそ一歩も退かずに、
相手がついて来られるまで 真剣に忍耐する事が仕事です。
そうしなければ、
外国人に出会うたびに、信念がぐらぐら揺れてしまいます。
「相手は外人だからいいや。」と 外国人向けに対処することは、
小手先は器用に慣れて、処理しているようだけれど、
処理のうまさと国際化は別のものと考えています。
日本の文化を堂々と押しつける方が、より国際的であるという事です。
そのようにして、外国人を集めた英語の水墨画クラスでは、結構 私は
面倒臭がられたりして、
なんとなく、あれ?今一瞬、孤立したかなぁ。と思う事も
あります。

(芍薬に蝶の課題)
そんな時こそ、動揺したりせず、
どっしりと構えて、
コツコツと地道な運筆練習をしてもらいます。
そうすると、どうなるのか。
お稽古の終わりに皆さんは、お道具を洗ったりしまったりしながら、
ニコニコ笑って喋っていて、
爽やかな笑顔で満足して帰られます。
ジムのトレーニングのようになっています
琳派墨絵クラブ