 本記事も、先日の朝日新聞の記事からである。セブンイレブン・ジャパンの値引き制限は「不当」公取委が排除命令」との記事を掲載した中で、書店の話をしたが、今回の記事はまさにこの書店の流通の話である。朝日新聞の記事のタイトルは『返本の山 流通改訂 出版10社「責任販売制」 書店の取り分アップ 返品なら負担求める』で、書店流通の詳細と課題に付いて掲載されていた。私自身、大学の時にアルバイトで一番長くやっていたのが、実はこの書店(町の本屋さん)でのアルバイト:要はレジ係であり、その仕組みは既に大学の時に理解していたが、その仕組み自身が、その後殆ど変わりなく30年以上もやってこられたのは、不思議な気もする業界である。当時は2社の取次ぎ店が流通を支配しており、今現在どうなっているかは知らないが、まだ当時のトーハン等が流通を支配しているのは間違いないようである。また、マージンの率も当時とそれ程変わりは無いようであるが、これも変化したのかどうかは定かではないが、流通の仕組み自身は変化していないのは恐るべきだと感心する。セブンイレブン・ジャパンの値引き制限は「不当」公取委が排除命令」の例と全く逆と言うか、主流(委託販売)は、セブンイレブン・ジャパンの値引き制限は「不当」公取委が排除命令」で述べた様に場所貸し業である。つまり、本屋の利益率(取り分)は悪いが、その変わり、仕入れ値と同じ率で、返品ができるのである。
本記事も、先日の朝日新聞の記事からである。セブンイレブン・ジャパンの値引き制限は「不当」公取委が排除命令」との記事を掲載した中で、書店の話をしたが、今回の記事はまさにこの書店の流通の話である。朝日新聞の記事のタイトルは『返本の山 流通改訂 出版10社「責任販売制」 書店の取り分アップ 返品なら負担求める』で、書店流通の詳細と課題に付いて掲載されていた。私自身、大学の時にアルバイトで一番長くやっていたのが、実はこの書店(町の本屋さん)でのアルバイト:要はレジ係であり、その仕組みは既に大学の時に理解していたが、その仕組み自身が、その後殆ど変わりなく30年以上もやってこられたのは、不思議な気もする業界である。当時は2社の取次ぎ店が流通を支配しており、今現在どうなっているかは知らないが、まだ当時のトーハン等が流通を支配しているのは間違いないようである。また、マージンの率も当時とそれ程変わりは無いようであるが、これも変化したのかどうかは定かではないが、流通の仕組み自身は変化していないのは恐るべきだと感心する。セブンイレブン・ジャパンの値引き制限は「不当」公取委が排除命令」の例と全く逆と言うか、主流(委託販売)は、セブンイレブン・ジャパンの値引き制限は「不当」公取委が排除命令」で述べた様に場所貸し業である。つまり、本屋の利益率(取り分)は悪いが、その変わり、仕入れ値と同じ率で、返品ができるのである。
セブンイレブン・ジャパンの値引き制限は「不当」公取委が排除命令」との裏返しになるが、買い取り責任がお店にあるならば、価格のコントロールはお店の自由であり、つまり小売価格の強制を行なうのは、独禁法違反となると当然と思うが、この書店の例では委託販売、つまり価格指定での販売を委託する変わりに、売れなければ返品できる事になる。つまり、この2例は、どのお店で購入しても値段が同じではあるが、販売方法と言うか、利益と責任区分が全く異なったビジネス形態となっている。
改めで書店での流通を述べると
- 大手取次店(日本出版やトーハン)が流通を握っており、出版社発行の書籍を、委託販売の形で、書店に取り次ぐ。つまり各書店は取次店に注文を依頼する。 私が知る限り、大学当時殆ど毎朝、お店の前に書籍の束が、置かれていた。
- お店は、売れた場合に、22~23%前後が粗利益となる。この時に売れた書籍から、再度売れそうであれば取次店に注文する。
※但し、確かうろ覚えだが、雑誌類は10%も無かった様な気がする。5%以下?今はどうなっているのか分からない。
- 取次店は、売れた書籍の8%前後を出版社から受け取る。 ここまでで見ると、出版社は70%近くが粗利となるが、この中から、著作者への印税や印刷代等経費を負担しなければならないが、驚異的な粗率の為ホクホク物と思われるが実はそうではない。
- ある期間売れなければ、本屋さんは場所が限られている為、取次店を通して、仕入れ価格と同じ値段で、出版社に返品する。この返品率が90年代は30%台だったが、08年度は40.1%だったとの事。つまり、90年代をピークに書籍販売市場は減少する中で、更に輪を掛けて、返品率が上昇して行った事になる。
上記の様に、セブンイレブン・ジャパンの値引き制限は「不当」公取委が排除命令」の例とは逆に、古い流通システムの書籍販売システムでは、価格維持はされているが(委託販売の為)、返品できる所に、大元の出版社が、大きなリスクを負うことに成っている。つまりヒットする書籍を出版できれば良いが、ヒットしなかった場合は、そのリスクはかなりの物となる。逆にセブンイレブン・ジャパンの値引き制限は「不当」公取委が排除命令」のフランチャイズ本部の場合では、殆どノーリスクであり、何れこの問題が発生するのは予見できたはずである。
さて、この朝日新聞の記事の紹介では、この返品の課題を解決する一つの方法として、「委託販売」ではなく、「責任販売制」の導入を試験的に始めているとの事。
つまり「責任販売制」では、書店の粗利を35%に上げる変わりに、返品を30%でしか受け付けないという、リスクを出版社と書店も負担するやり方を導入しようとしている事である。此れの成果は、書店によって、どうも結果が分かれている様であるが、要はリスクをとるかとらないかの問題であるが、この「責任販売制」であっても、セブンイレブン・ジャパンの値引き制限は「不当」公取委が排除命令」のフランチャイズ本部による強制価格コントロールと返品無しのお店側の全負担では、余りにも違いが大きすぎる。最も生物の違いはあるが、リスクをとらない本部も問題はあると思う。
同じように何処でも同じ価格と言うのは書籍だけではない。おそらく著作権を扱う事からだと思うが、音楽業界、つまり昔ならレコード屋さん(今ならCD屋さん)も同様と成っているはずであるが・・・。つまり返品を受け付けられる流通網とレコード会社との関係と同じようになっていると考えられるが・・・???この辺の詳細は分からない。
















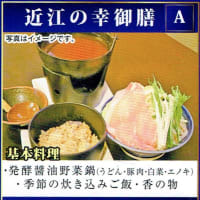
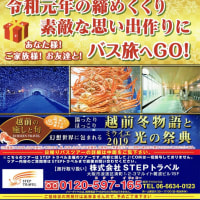


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます