本記事が4月27日(日)版の朝日新聞に掲載されていました(要約しています)。
「要は中国の工場でストライキが増えている。この背景には今年1月に施行された労働契約法が影響されているようだ。ブリヂストン江蘇州の工場では一律月200元(約3千円工場労働者の平均月収の1~2割り)の賃上げを要求。カシオ計算機(広東省広州市)でも1日半工場がの生産が止まった。同省のコニカミノルタでも2月のストで結局賃金を月690元から820元に引き上げた。
最も大きい影響を与えているのが、急激な物価上昇であり中国では、肉や魚などが値上がりし、2月のインフレ率は前年同月比8%になっている。これに伴い最低賃金が上昇し、上海では4月に前年の月840元から一気に960元(14%のアップ)になっている。
新しい労働契約法は、経営者側に雇用期間を長くするように促し、労働者の待遇改善を求めている。労働者の権利意識が高まり全般的にストが多くなっている」との話である。
さて、雇用期間を長くするようにしても、欧米並みに3年ぐらいで、転職するのが最近の中国であり、これだけ賃金が上がってくると、その背景のインフレは理解できるにしても、日本の企業が既に中国を生産の国としてではなく、市場と捕らえつつあるのがわかる。すなわち、中国で物を生産しても割が合わなくなってきつつある。元々労務費が安い事で、中国に進出していたが、多くの日系企業の進出に伴い、ここ10年あまりで、労務費を含め、一般消費財の値段の高等は目を見張るばかりである。その労務費を上げた日本企業にも責任の一端はあると思うが・・・。
日本語教室の現状を何回か話しているが、今は既にインドネシアやベトナムにシフトしつつあるのだろう。
















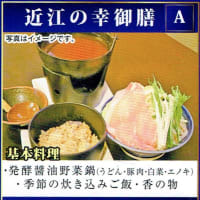
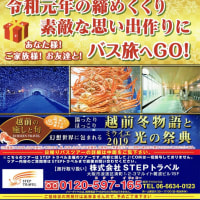


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます