書籍タイトルからわかるように今回の作品は、ノンフィクションである。一般の小説ならその内容をあらすじとして掲載するが、今回はそう言う訳にはいかない。もちろん、このノンフィクションを書かれた筆者の思いや背景もあるだろうから、今回詳細は割愛させてもらう。
しかし、筆者が愛知の工場で派遣社員として働かれた時期が2007年ではなく、そのわずか1年後の2008年或いは2009年だったら、この内容は激変しているだろう。筆者の「まえがき」や「あとがき」で、知り合ったブラジルや国内の派遣社員の方のその後について掲載されているが、ご自分のその後を含めてかなり厳しい状況となっている。特に2009年や今年に入ってからだとしたら、この作品(特に愛知県を中心として、工場で派遣労働者として勤める事)は世に出ていないだろう。
一方なぜ?この書籍を紹介するのか?前回の小栗左多里『ダーリンは外国人』と近いが、別な意味の興味からとなる。つまり当市のにほんご教室で、学習者の話を過去何回も取り上げているが、前回の小栗左多里『ダーリンは外国人』でも掲載した様に、研修制度を利用したインドネシア学習者達の話が、この書籍の内容(ブラジルからの出稼ぎ労働者)とオーバーラップするからだ。しかも当市のにほんご教室で私が知る事になった、学習者の内同じ様に日本に仕事で(つまり出稼ぎ労働者として)来日された方は、この本のブラジルの方を始めとして、スペイン、メキシコ、中国、韓国、台湾、フィリピン、インドネシア、ベトナム、タイ・・・と非常に多岐にわたる。その中で特に気になったのは最近特に親しくなったインドネシアから研修制度を利用して来日している学習者達だ。
本の書籍の「ブラジル」の方々とも多く知り合っているが、まだ「ブラジル」の方々は良い方だと私的には感じる。何をもって良いか?等は簡単な言葉ではないが、少なくとも「ブラジル」から来日されている多くの方は「日本にきて働ける特権が最初から認められている」が、今まで何回も掲載した中国をはじめとしてインドネシアやベトナム等多くのアジアの国の方が日本に来て働く手段として「研修制度」を利用せざるを得なく、かつこれが低賃金と3年間と言う期間を縛る制度となっている。しかし、多くの学習者の方が、この制度その物の結果については、不満等があるわけではなく、私達にとっても、毎回別れが訪れるが、それも仕方がないと思っている。むしろ地域社会としてこれらの制度があり、その結果地域社会が成り立っている事を知り、もはや日本人だけでは生きていけない、高齢化と少子化と此れへの対応としての国際化があることを身近に感じてもらい、その対応を地域として考えていく事が重要と思っている。
さて、この本のブラジルの方と同様に、日本に出稼ぎに来て働かれている多くの学習者から、その仕事に関して不平や不満、キツイとかツライとかの話を私は聞いた事がない。一方この本のブラジル人の方と同様に、お金に関して、つまり残業や休日出勤への要望が多い。この辺は大変明確と言うか!ハッキリしている。且つインドネシアの学習者は一様に、日本語学習に関しても大変熱心だ。それは研修期間が3年と限られている事から、何れは母国に帰った時に日本語を活用する事や日本での色々な知識などを生かして職に就きたいと考えている事などが、この本の「ブラジルからの派遣労働者」と大きく異なる事だろう。
いずれにしても最初に掲載して本作品は、書籍としては分厚いが、その内容からして、暗くなりそうな気もする中で、面白くあっと言う間に読める作品でした。あまり暗くなる事より、ブラジルの方と同じように常に楽しく明るく仕事もプライベートもこなす事が、非常に大切だと思う。この辺は、なかなか日本人はできないが、インドネシアやフィリピンの方と付き合う度に、これが痛感させられる。彼らは勉強中も、明るくまじめ(何処からがまじめなのかがわからない時もあるが・・・)で一旦イベントが始まると弾(はじ)けてしまい、トンでもないところまで飛んでいく。

















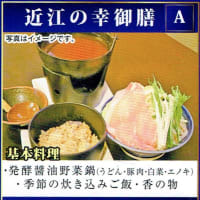
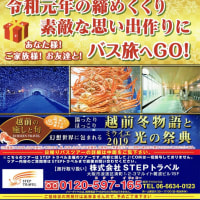


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます