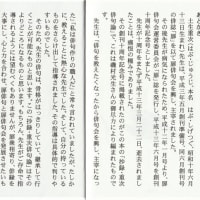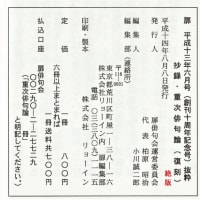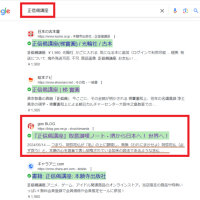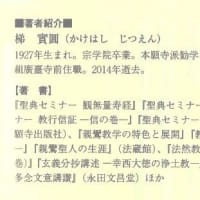「紀行記・風物詩」シリーズは、こちらから(トップページ左覧参照)
◆美しきドナウへの旅 フランス・ホームステイ
◆中国・長江文明 高句麗・前期都城 清朝建国の歴史 遼東半島・旅順博物館
◆アンコール遺跡 生れ故郷ソウル
◆再会・京都楽日 大阪天神祭“船渡御” DIC・川村美術館

前田秀一 プロフィール
家族! その「絆」を再確認する「旅」をしました!
本来なら、父親と夏休みの思い出と宿題のネタ作りのための旅行になるはずでしたが、図らずも、昨年11月初めに膵臓がんという大病に見舞われ“思い”を残して急逝したため、残りの人生を少しでも父親代わりになればと、NHK大河ドラマゆかりの地・世界遺産・安芸の宮島と明治維新胎動の地・松下村塾(山口県萩市)へ旅行をしました。
お迎え火、初盆供養、送り火、経木供養・・・。浄土真宗(本願寺派)の我が家にとって初めて経験する真言宗のお盆供養を済ませ、あわただしかって日々をねぎらうための旅行でもありました。
奇しくも、「家族旅行やね!」と新幹線の中で呟きが・・・、思わず心の中を垣間見た思いがしました。健やかに育ってほしい!あらためて家族の絆づくりのありようを求めて、夏の思い出づくりの家族旅行をしました。
さらに足を伸ばした津和野では、文豪・森鴎外(本名・森林太郎)の生きざまに触れ、明治新政府によるキリスト教禁止通達に伴う殉教の悲話に驚き、殉教者の遺徳を偲んで建てられた津和野カトリック教会の正面に堺にゆかりの深いイエズス会のレリーフを発見し、礼拝堂には十六世紀に来日した巡察師・アレサンドロ・ヴァリニャーノが「礼法指針」に書き著した茶室を想起させる畳が敷かれていることに感動しました。


世界遺産 国宝(平安時代) 厳島神社(広島県安芸市)

国宝(平安時代) 本殿遠景


神 殿 重要文化財(江戸時代) 能舞台


重要文化財 本社火焼前(ひたさき)より88間の海面にそびえる朱塗りの大鳥居
奈良の大仏とほぼ同じ高さの16m、重量は約60t。主柱は樹齢500~600年のクスノキの自然木。
根元は、松材の杭を打って地盤を強化し、箱型の島木の中に石を詰めて加重し鳥居の重みだけで立っている。

世界遺産を目指す 錦帯橋(山口県岩国市) 完成:延宝元年(1673)10月1日
岩国藩主・吉川広嘉が、明の帰化僧・独立(どくりゅう)から聞いた『西湖志』の絵にヒントを得て、小島のような頑強な橋脚を築き川の増水にも流されない橋として完成した。



長門湯本 温泉旅館 大谷山荘(ホームページより引用)
長門市にある曹洞宗・瑞雲萬歳山 大寧護国禅寺の住職が、住吉大明神のご神託によって発見し、1427年に開湯したとされる温泉郷。開湯時に発見した源泉は現在も湧出し、所有も同寺のもの。


大谷山荘 尾崎 保料理長 もてなしの夕食献立



萩焼 体験(指導:盤石窯・金本明夫氏) <夕食後のくつろぎのひと時> ナイト・バンドショ-


松陰神社 〔主祭神:吉田寅次郎藤原矩方命(吉田松陰)〕 「明治維新胎動の地」碑

国指定史跡 松下村塾 (幕末期に吉田松陰が主宰した私塾)



熟 舎 講義室
久坂玄瑞、高杉晋作、吉田稔麿、入江九一、伊藤博文(初代内閣総理大臣)、山縣有朋、山田顕義、品川弥二郎ら、明治維新の原動力となり、明治新政府に活躍した多くの逸材を育てた。


曹洞宗 覚皇山 永明寺(ようめいじ) 文豪・森鴎外菩提寺 森鴎外(本名:森林太郎)遺言

動画 津和野の四季


津和野カトリック教会 礼拝堂は珍しく畳敷で、鮮やかなステンドグラスが印象的
この聖堂は、明治新政府が発令したキリシタン禁止令〔1868年4月7日(慶応4年3月15日)、明治政府太政官通達「五榜の掲示」〕により長崎から流罪に処せられ連れて来られ、廃寺・光淋寺(津和野町乙女峠)で津和野藩による拷問により殉教したキリスト教信徒36人の遺徳をしのび、1931年(昭和6年)に建てられた。
建築様式は、新ゴチックにして正面レリーフ(紋)はフランシスコ・ザビエルの属していた修道会(イエズス会)が十六世紀から使っている紋をかたどっている。
毎年5月3日には殉教者を偲ぶ、乙女峠祭が行われ、町内の幼稚園児や関係者等県内外から約2000名による幻想的なミサが行われる
「明治新政府のキリスト教禁止令と弾圧」について
江戸幕府が瓦解すると、1868年4月7日(慶応4年3月15日)に明治政府から太政官通達「五榜の掲示」が示され、その第3条で再びキリスト教の禁止が確認された。
明治政府におけるキリスト教禁止令通達の背景は、かつて尊皇攘夷運動の活動家であった政府内の保守派は、廃仏毀釈に加えて「神道が国教である(神道国教化)以上、異国の宗教を排除するのは当然である」、「キリスト教を解禁してもただちに欧米が条約改正には応じるとは思えない」とキリスト教への反発を隠さず、禁教令撤廃に強硬に反対し、また長年キリスト教を「邪宗門」と信じてきた一般民衆の間からもキリスト教への恐怖から解禁反対の声が上がったためであった。
長崎裁判所総督を命じられた沢 宜嘉と外国事務係・井上 薫は、問題となっていた浦上の信徒たちを呼び出して説得したが、彼らには改宗の意思がないことがわかった。沢と井上から「中心人物の処刑と一般信徒の流罪」という厳罰の提案を受けた明治政府は御前会議を開いてこれを討議、諸外国公使からの抗議が行われている現状を考慮して「信徒の流罪」を決定した。
1968年7月9日(5月20日)、木戸孝允が長崎を訪れて処分を協議し、信徒の中心人物114名を津和野、萩、福山へ移送することを決定した。以降、1870年(明治3年)まで続々と長崎の信徒たちは捕縛されて流罪に処された。
彼らは流刑先で数多くの拷問・私刑を加えられ続けたが、それは水責め、雪責め、氷責め、火責め、飢餓拷問、箱詰め、磔、親の前でその子供を拷問するなどその過酷さと陰惨さ・残虐さは旧幕時代以上であった。
長崎・浦上村のキリスト教信徒153名を収容した廃寺・光淋寺(島根県津和野町乙女峠)では、津和野藩により信徒に対して酷い拷問が行われ、そのすさまじさから36名の殉教者を出した。その際、日本国内ではじめて聖母マリアが顕現した地とされている。
1871年12月23日(明治4年11月12日)から1873年(明治6年9月13日)まで、日本から岩倉具視を正使としてアメリカ合衆国、ヨーロッパ諸国に派遣した大使節団(政府首脳陣や留学生を含む総勢107名で構成)一行が、訪問先で禁教政策を激しく非難され、明治政府のキリスト教弾圧が不平等条約改正の最大のネックであることを思い知らされることになった。
1873年(明治6年)2月24日、日本政府はキリスト教禁制の高札を撤去し、信徒を釈放した。配流された者の数3394名、うち662名が命を落とした。生き残った信徒たちは流罪の苦難を
「旅」と呼んで信仰を強くし、1879年(明治12年)、故地・浦上に聖堂(浦上教会)を建てた。
引用資料:ウィキペディア


広島 原爆ドーム(平和公園) 広島駅新幹線ホーム JR500 カンセンジャー
SDGs魅力情報 「堺から日本へ!世界へ!」は、こちらから