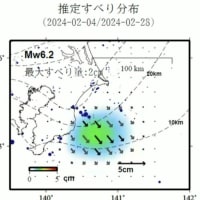「ねぶと」という魚をご存じだろうか。
「知っている」という方は、瀬戸内で暮らした経験がおありだろう。
標準和名はテンジクダイ。
ネンブツダイの近縁種である。
底引き網で大量に獲れ、私の故郷の魚屋の店頭ではごく普通に売られていた。
から揚げで食べても美味しいが、私はこの魚で作る練り物「じゃこ天」が好物である。

関東では釣りの外道として敬遠されるヒイラギも、よく食卓に上る。
強いぬめりと鋭い棘があって捌くのは大変だが、きちんと料理すればとても美味しい魚である。

同様に関東では外道扱いされるキュウセンも、地元では人気の高い魚。
性転換する魚として知られており、赤いキュウセンは全て雌。
群れの中で特に体が大きく強い個体が性転換して、青い雄になるのだという。
塩焼きや南蛮漬けにすると大変美味で、私の釣りの師匠である父にいたっては、一時期、これを専門に狙って釣行していたほどである。
私が初めて釣り竿を握ったのは、まだ物心ついて間もない頃。
私に釣りを教えた悪い人(笑)は、父と、母方の祖父。
島育ちの父は海釣りが得意で、一方の祖父は淡水釣りと投網の名人だった。
私は父や祖父が釣りに出鰍ッるたびについて回り、色々な魚の釣り方や投網の打ち方を教えてもらった。
家のすぐ近くに大きな川が流れ、海へも自転車で行ける距離だったこともあって、私はすっかり釣りの虜になった。
小学校高学年になる頃には、仲間を誘ってチャリンコ部隊を編成し、年がら年中、海や川で魚を釣ったり、河口でシジミやハマグリを採ったりして遊んでいた。
当時の釣り方は、主に投げ釣りとのべ竿での堤防ウキ釣りだったが、それでも色々な魚が釣れた。
カレイ、アイナメ、キス、キュウセン、クロダイ、スズキ、メバル、サヨリ、etc.・・・
私の釣果記録のうち、クロダイとマコガレイの最大サイズは小学生のときのもので、いまだにこれを破ることができずにいる。
房総ではャsュラーなターゲットであるアジやサバは、私の故郷では不思議と釣れなかった。
私が子供だから釣れなかったというわけではなく、大人たちが釣り上げるところも一度も見ていないので、やはり居なかったのだと思う。
同じくメジナも、私はずっと実物を見たことがなかった。
中学生になると、私は仲間とともにルアーフィッシングにのめり込んだ。
当時はまだ近所にブラックバスはおらず、川や池で釣れるフィッシュイーターは、ケタバス、ナマズ、ライギョなどだった。
河口近くでは、たまにスズキも釣れた。
ケタバスは、琵琶湖産の稚鮎に交じって放流されたもので、ウルトラライトアクションのタックルでのスピナーゲームがとても面白かった。
当時、中学生の小遣いでも買えるシェイクスピア製のスピニングロッドを使っていたが、とてもよくできたロッドだった。
リールは、カーディナルが欲しかったけれど買えなくて、大森製作所のマイクロ二世を使っていた。
そんなタックルにナマズやライギョが鰍ゥると、それはもう大騒ぎ。
ルアーを失いたくない一心で何とかランディングに持ち込んでいたが、今にして思えば子供ながらあっぱれである。
当時、近所の川でルアーフィッシングをやっていたのは私たちの仲間だけだったので、ときおり噂を聞きつけた大人が私たちの釣っているところに現れて、ルアーフィッシングを教えてくれと頼んできた。
生意気盛りの私たちは、いい気になってルアーのタイプがどうのこうの、泳がせ方がどうのこうのと偉そうに講釈を垂れていたが、本当に鼻持ちならないクソガキどもだったと思う。
当時の私が、いま目の前にいたら、思い切り尻を蹴飛ばしてやるところである(笑)。
後年、仲間の一人はバスプロになったと聞く。
進学のために上京してからは、故郷で釣りをすることはほとんどなくなった。
独身の頃は、たまに帰省した時に弟と一緒に近所の川でブラックバスやスズキを狙ったこともあったが、結婚して家族と一緒に帰省するようになってからは、一度も竿を出していない。
近所の川には、いつの間にかブラックバスとブルーギルが繁殖していた。
琵琶湖で増えたバスやギルの稚魚が、放流用の稚鮎に紛れ込んでこの川にも入ってきたようだ。
遠くからやってきた大勢のルアーマンが竿を振るようになり、なんだかアウエイな雰囲気になってしまった。
海の様子も年々変わっていった。
海岸線の整備が進み、観光施設が次々に建設された。
海中にも変化があり、父や弟によれば、私が子供の頃には姿を見ることが無かったアジやメジナ、アオリイカが普通に釣れるようになったという。
弟はルアーでのアコウ(キジハタ)釣りが面白いのだと言って、私たちの帰省に合わせて釣ってきてくれたりもした。
これも私が子供の頃には見たことのなかった魚である。
瀬戸内海の水温が、全体的に上がっているのだろうか。
私に釣りを教えてくれた父は、歳のせいもあって、最近では一人で釣りに出鰍ッることはなくなった。
機会があればまた一緒に釣りをしようという話はよくするのだが、なかなかゆっくり帰省することができず、いまだに実現していない。
数年前、一人で帰省した時に、自転車を借りて昔よく釣りをした海岸まで行ってみたことがあった。
綺麗に整備された海岸は、昔とはかなり雰囲気が変わっていたが、私が自己記録のクロダイを釣った小さな堤防は、そのままの姿でそこにあった。
この海で、久しぶりに釣りをしたいと思った。
今度帰省したら、父に釣りを提案してみよう。
弟も誘ってみようか。
寒い時期の釣りは父の体に障るから、暖かくなってからがいいかな。
ゆっくり休みを取って、子供の頃のように父と並んで竿を出して、キュウセン釣りを教えてもらおう。