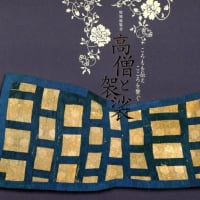今日は、この一節を学んでいきたい。
浄法界の身、本と出没無し。
大悲の願力、去来を示現す。
仰いで照鑑を願い、俯して真慈を請う。
南閻浮提大日本国北陸道 国 庄 山 寺開闢〈某甲等〉
今月十五日、恭しく本師釈迦如来大和尚入般涅槃の辰に遇う。
謹んで香華灯明の微供を弁備し、以て最後の慇懃の供養を伸ぶ。
恭しく現前の一衆を集め、秘密神咒を諷誦す、集むる所の殊勲は、上み慈蔭に酬いん者なり。
右、伏して以れば、
常在霊山の微月、幽光遠く輝き。
泥洹双樹の残花、余薫尚お郁る。
涅槃常楽の接化、今時なる迄も、
無為実相の徳用、来際を被う。
是を以て上乗一心の法供養、面面の五十二類は供具を捧げ、
万行首楞の秘密咒、各各に異口同音の仏事を作す。
伏して願くは、
法界遍く無量声光の告に驚き、
群類悉く如来常住の化に預からんことを。謹んで疏す。
禅林寺本『瑩山清規』「涅槃会疏」
一応、曹洞宗に於ける涅槃会疏では、最古の一本である。この涅槃会とは、仏陀釈尊の涅槃に於いて、その意義を学ぶ意図がある。疏の内容も、そのような内容として執っていくべきであろう。
前半部分は定型句であり、供養するための読経や、供物についての話であり、今回は敢えて採り上げる必要がない。問題は、「右、伏して以れば」以下になる。ここが、曹洞宗の太祖・瑩山紹瑾禅師が、涅槃に際して読み込まれたその意義になる。
まず、霊山とは仏陀が説法し続けている場所とされる霊鷲山で、『妙法蓮華経』「如来寿量品」の思想的基盤を受け継いで説かれた瑩山禅師『伝光録』首章からすれば、そこには、常在なる釈尊=微月があり、その幽かなる光、仏陀の在す功徳が、あらゆる場所にまで及んでいることを示された。しかし、「幽か」であることが問題となる。
同じく、釈尊が涅槃に入る時に寝ていた沙羅双樹に残った花には、その香りが今にもまだ残っているとされる。これは、仏陀の涅槃の意義、参究されることで仏教徒に無常の真実を示したが、それが残っているのである。そして、この月の光、花の香り、両方を感受するためには、我々衆生の精進を要する。
然るに、今度は仏陀の側から見てみますと、涅槃に入ることで、常に楽になるという意義の導きは、今に到るまで止むことがなく、それは無為実相の働きとして、未来までも覆っている。
ここから、我々の精進は、行ずれば、正しく仏陀が応じてくれることが分かる。それは、上乗一心での法供養になる。仏陀の面前にいる五十二位の修行者は、皆供物を捧げ、『楞厳呪』を唱えて、異口同音の仏事供養を実現された。
そして、願うところは、法界の全てに、限り無い声によって伝えられる説法に驚き、あらゆる生きとし生けるものが、如来が常に行っている導きに預かることが出来るように、ということである。つまり、最終的には、自分たちだけが、仏陀からの功徳を得るのではなく、一切の法界衆生に回向している様子が分かる。
拙僧つらつら鑑みるに、この「疏」を通して、普段行う供養が、涅槃の意義への理解をもたらし、釈尊の常住法身へと気付かせてくれることが分かる。しかし、それは安住が許されず、常住法身からの功徳を得る我々の精進を促すことでなくてはならない。まさしく、本証妙修といえよう。
本証妙修として読めば、この「疏」は、理解が容易だといえよう。涅槃会という絶好の機会を通して、まさしく、諸行無常と勤精進を説かれたのである。
#仏教