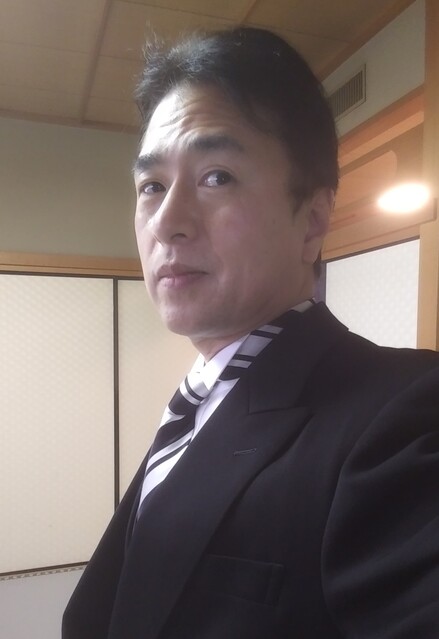あっ、これ〰️エイプリルフールジョークですよ〰️。この画像はトミーですよ。
でもねー、姪っ子に似てるんだよね〰️🎵
近年、実用化に向けて、世界中で研究が行われている「培養肉」。
動物の個体からではなく、細胞を体外で組織培養することによって得られた肉のことで、主に「ミンチ肉」を作製する研究が進められている。
これまでの研究では「ステーキ肉」のような食感を生み出すことはできていなかったのだが、こうした中、3月22日、肉本来の食感を持つ「培養ステーキ肉」の実用化につながる発表を、日清食品ホールディングスと東京大学生産技術研究所の竹内昌治教授の研究グループが行った。
牛肉由来の筋細胞を用いて、“サイコロステーキ状のウシ筋組織”を作製することに世界で初めて成功したのだという。
“サイコロステーキ状のウシ筋組織”とは?
日清食品の看板商品「カップヌードル」に入っている、通称"謎肉"というサイコロ形状の肉の“謎”の正体は大豆であったが、今回の「培養ステーキ肉」はまた違うものなのだ。
そしてなぜ、“サイコロステーキ状のウシ筋組織”が「ステーキ肉」の食感につながるのか?
まず、肉本来の食感は、筋肉に含まれる筋組織の立体構造から生み出される。そして、この立体構造を体外で人工的に作製するためには、筋細胞を増やすだけでなく、筋細胞をより成熟させる、厳密にいえば、“細胞同士を融合させ、細長い構造に変化させる”必要がある。
しかし、体外で筋細胞を成熟させるためには、必要な栄養を行きわたらせ、細胞を適切に配置する技術が求められていた。そこで研究グループは、培養過程でウシ筋細胞にビタミンCを与えることで、ウシ筋細胞の成熟が促進されることを確認。
また、厚みのある培養肉を得るために、ウシの筋細胞を従来の平面的な培養ではなく、コラーゲンゲルの中で立体的に培養したところ、筋組織に特有の縞状構造 「サルコメア」 を持つ、細長い筋組織の作製に成功。
さらに、この筋細胞を層状に重ねて、特殊な方法を用いて培養することにより、世界で初めて、長さ1センチ、幅0.8センチ、高さ0.7センチの「サイコロステーキ状 」の弾力のあるウシ筋組織の作製に成功した。
これらの技術を発展させることで、今後、さらに大きな筋組織の作製も可能と考えられ、肉本来の歯応えを持つ「培養ステーキ肉」の実用化への第一歩になるのだという。
現時点ではまだ小さく、決して肉には見えない、開発中の「培養ステーキ肉」。
実際に食べられるようにするにはどのような課題があるのか?
日清食品ホールディングスとともに「培養ステーキ肉」の開発を進めている、東京大学生産技術研究所の竹内昌治教授に話を聞いた。
課題の1つは「味をステーキ肉に近づけること」
――現時点では「長さ1センチ、幅0.8センチ、高さ0.7センチ」の培養肉を、ステーキぐらいの大きさにするためには何が必要?
「ウシから採取した細胞を安価に大量に培養する方法」と、「厚みを持つ組織内部に血管構造を設け、養分を内部まで供給しながら、長期間、培養する方法」が必要です。
――ステーキの食感はできあがったと考えてよい?
今回は筋肉内にある長細い筋ができたというものです。
血管や脂肪などは存在していないので、まだそのものができたとは考えておりません。
――ステーキの味わいや肉汁などは、どうやって再現する?
脂肪や血管構造、血球を付与していくことで近づけることを考えております。
――その他、実用化に向けた課題は?
安価で量産する方法を検討することと、味をステーキ肉に近づけていくことです。
実用化の時期は「現段階では未定」
現段階では様々な課題がある「培養ステーキ肉」。
実際に食べられるようにするにはどのぐらいの年数がかかるのか?日清ホールディングスの担当者に話を聞いた。
――日清が「培養ステーキ肉」の研究を始めた理由は?
近年、世界中で「培養肉」の研究が行われていますが、そのほとんどが、「ミンチ肉」を作製する研究です。
そこで、日清食品ホールディングスと東京大学生産技術研究所の竹内昌治教授の研究グループでは、肉本来の食感を持つステーキ肉を「培養肉」で実現するため、筋組織の立体構造を人工的に作製する研究に取り組むことになりました。
――実用化は何年後ぐらいになりそう?
現段階では未定です。
――実用化したら、「培養肉ステーキ」は200グラムでいくらぐらいになる?
現段階では未定です。
――「培養ステーキ肉」を実用化できた際にはどのようなかたちで活用しようと考えている?
現段階では未定です。
――日清のカップヌードルに「培養ステーキ肉」を活用する可能性は?
現段階では未定です。
実用化の時期は「現段階では未定」だという「培養肉ステーキ」。
課題も多いが、肉本来の歯応えが再現され、実用化される日が楽しみだ。
日本初「食べられる培養肉」成功 “培養ステーキ肉”へ一歩
FNNプライムオンライン
日本初となる「食べられる培養肉」が登場。 「培養肉」とは、動物の細胞を研究室で育ててつくる肉のことで、日清食品ホールディングスなどは、すべて食べられる素材のみで「培養肉」を作ることに、日本で初めて成功したと発表した。 日清は2025年3月までに、「培養ステーキ肉」の実現を目指している。
<button id="articleReactionButton3" class="ArticleReaction__ReactionButton-fldxDu kQdFAz rapid-noclick-resp cl-noclick-log" data-ylk="rsec:like;slk:newpov;pos:1;" data-cl-params="_cl_vmodule:like;_cl_link:newpov;_cl_position:1;" data-rapid_p="87">【関連記事】</button>