
2014年に発表された論文によると、内発的動機と外発的動機はそれぞれの対極にあるものではなく、共存もしくは独立した要素なのだという。
それを踏まえたうえで、内発的動機と外発的動機の特定の組み合わせや内在化された動機は成績を向上させる要因になったという。
周りからの指示や命令のすべてが悪いものではない。対象をよく知る両親や親友、コーチなどからの指摘のように、明らかに対象の利益のために組まれたものや対象の能力を考慮したものもある。
周囲からの期待にこたえたく行動し、実を結び、自他ともに多大な利益を受け取ることもある。
自分の意志で決断したもののすべてが良いものではない。対象自身をバイアスで覆い隠し目をそらした対象の決断のように、明らかに対象を不利にするものや対象の能力を考慮していないものもある。
重箱の隅をつついたり貶めたり支援を無視したりしてわざと孤立無援の状態を作り、無我夢中に机上の空論を作ることもある。
もちろん、これらの逆もありうる。対象をよく理解していない知人の指示が対象にとって不利であることも、自身をよく学んでいる対象の決断が対象にとっての利益であることも。
ここからわかることは、2つ。
内発的動機や外発的動機にはそれ自体に善悪・真偽はない。
それぞれの動機が効力を発揮するかどうかは、その動機によって起こる行動の方向性や度合い、その動機を構築するに至った知識や行使する側の能力に密接にかかわってくる。
自分で決断したから、周りからの指示だから、で判断するのは適当とは言えない。重要なのはやはり、動機の動機ともいえる部分なのだろう。
この辺りのお話は「内在化された動機」と一緒に学ぶとより分かりやすいはずだ。
ーーー成績や行動などの分野において、
基本的に内発的動機が外発的動機に勝っている原因は、
やっぱり『自分が決断したから』という補正があるからなのだろうか?
参考文献
Marina S.Lemos,LurdesVeríssim (2014) The Relationships between Intrinsic Motivation, Extrinsic Motivation, and Achievement, Along Elementary School.










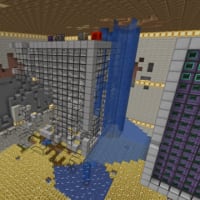
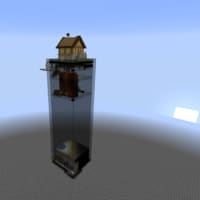



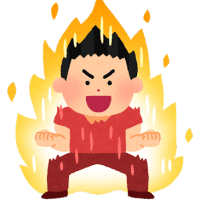



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます