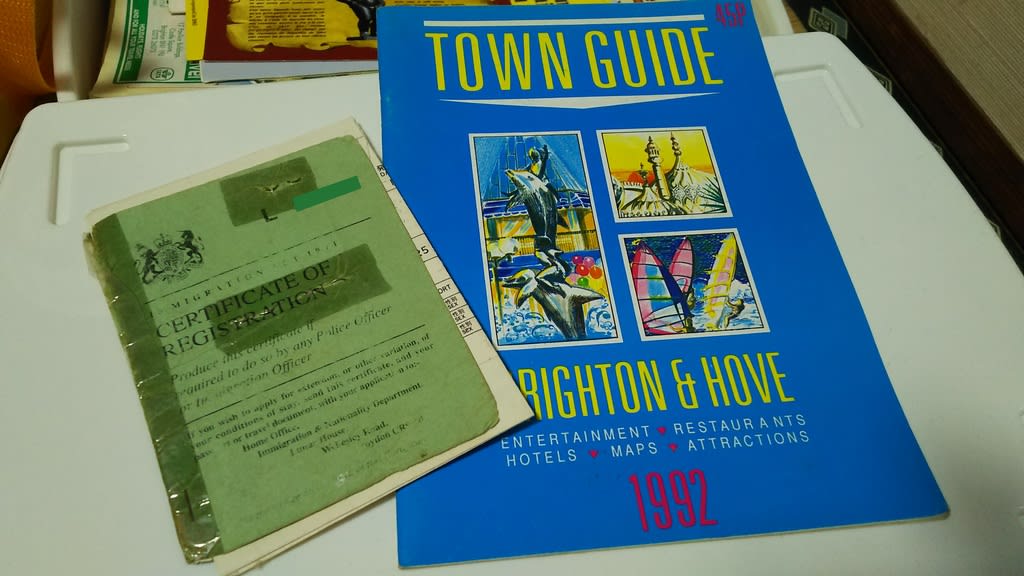
「やぁ,お帰り,ソーヤン」
ナイトさんが火を焚く手を止めて穏やかに話しかけると,奥さんもこちらに微笑みかけた。
「ナイトさん,本当にありがとうございます」
「自動車のことかい」
「ソーヤン,電話しようと思ってたのよ。その顔はどうしたの」
僕が眉の傷を触ると,老夫婦は少しだけ間を置いてから続けた。
「まぁ,先ずはきちんと着替えてカリンと一緒に来なさい」
「そんな恰好じゃまだ寒いでしょう,しょうがないわね」
僕は嬉しさの余り興奮していたから2人の戸惑った様子の意味がすぐには分からなったが,自分がズボンも靴下も履かずにコート1枚だけの奇妙な服装であることに気付いて慌てた。ベンとマシューが大笑いして,少し遅れてナイト夫妻もクスクスと笑った。
気温が低く,皆白い息を吐いていて,その様子が逆に僕の心を温めてくれる。皆生きているんだ。
「すみません,ナイトさん」
「まぁ,無事で何よりだ。パーティは5時からだからね」
「折角仕上がった自動車だから大切に乗るのよ,マシューにも感謝して」
「今夜は君が主賓だ,何も気にせず手ぶらでおいで」
「は,はい」
僕は後ずさりして何度か足をもつらせながら車に戻った。そして,笑いながら温かく見送ってくれるベンとマシューの姿が少しずつ小さくなっていくのをミラーで確認しながら,僕は走ってきた道を今度は十分に落ち着いてゆっくりと戻って行った。もうギアとクラッチの動作が自分に馴染んでいくのを感じる。ボンネットをつや消しのブラックに塗られた小洒落たローバーミニはキングズウェイを東に,右側のガラスにブライトンの穏やかな海を映しながら走った。
人の出会いや繋がりは実に不思議なものだ。円山さんが借りていた家のオーナーだったナイト夫妻に初めて会って事情を説明したのは1回目のミッションから戻った当日のことだった。アジャとイーゴとの別れと引き換えに,神様が・・・もし神様という存在が本当にあるならば,「生きよ」と言わんばかりのいくつもの出会いを,失われた絆とほぼ同じくらいのスピードで僕に与え給うたのかもしれない。
かくして,人生を旅に例えるならば,出会いとは行く先々に広がる様々な景色なのであろうか。長く留まりたい場所であっても,いずれ出発の汽笛が鳴れば否応にも後にしなければならない事もあろう。懐かしくて戻りし素敵な場所であっても,いざ辿り着いてみたら以前ほどの魅力を備えていないこともある。正に「一期一会」とはこのことで,僕たちの人生はこの出会いと別れの連続なのかもしれない。永遠を約束された出会いなどこの世にはない。この世に生まれ出でて,ひたすら死に向かって歩み続けるしかない僕たちの出会いには絶対に避けて通れない別れが常に影を潜めている。それは決して出会いの意味を否定するものでもない。別れを意識することであらゆる出会いを充実させることができるのだし,もしかすると,そうすることで僕たちは優しくなれるのかもしれない。ならば死を前提にした生こそは僕たちの人生の本来のあるべき姿なのだ。後悔しない生き方とはそこにあるに違いないが,しかしながらそう実践するのも容易なことではないというのもまた事実だ。
「Separation starts at the first meeting.」
誰のものだか忘れたが,とても印象的で記憶していた詩を僕は口ずさんだ。
ベン達と派遣先で再会したのは,スイスで訓練を受けて各地に向かってから2週間ほど経った頃で,あの時僕には時間の感覚が既に失われていたが,以来数日の内に彼らとは切っても切れない絆で結ばれた様な深い仲になった。車窓を通して視界を流れて行く平和な街並みを心地よく感じていた僕は,キングズウェイからキングスロードに差し掛かる頃,突然神秘的な経験が脳裏に甦ってはっとした。
「そういえば・・・」
日曜市が中止になってからの数日の事は今でも朧気にしか覚えていない。アジャとイーゴの死を振り払おうとしていたのか,僕はホスピタルでのW.W.としての任務を拠り所にして「遺言」を記録することに邁進していた。たった数日の内に20,30と記録が増えていくのを数えながら,もしかすると僕の精神状態は崩壊に向かっていたのかもしれない。それを察してか,リアノが僕だけを車に乗せてホスピタルを後にした。別れ際,ジェイが思いの他残念そうに僕を見送ってくれたのだけははっきりと記憶している。彼に求められてイギリスの住所を彼に渡したことは後から教えられた。あの夏の出来事はあらゆることがぼんやりとしていて殆ど覚えていないが,1つだけ,未だに説明できない不思議な出会いをしたことは確かだった。あの幼い兄妹は実在したのだろうか・・・それすら疑わしいと思う矛盾した感覚の中で,その兄妹の笑顔が今も忘れられない。









