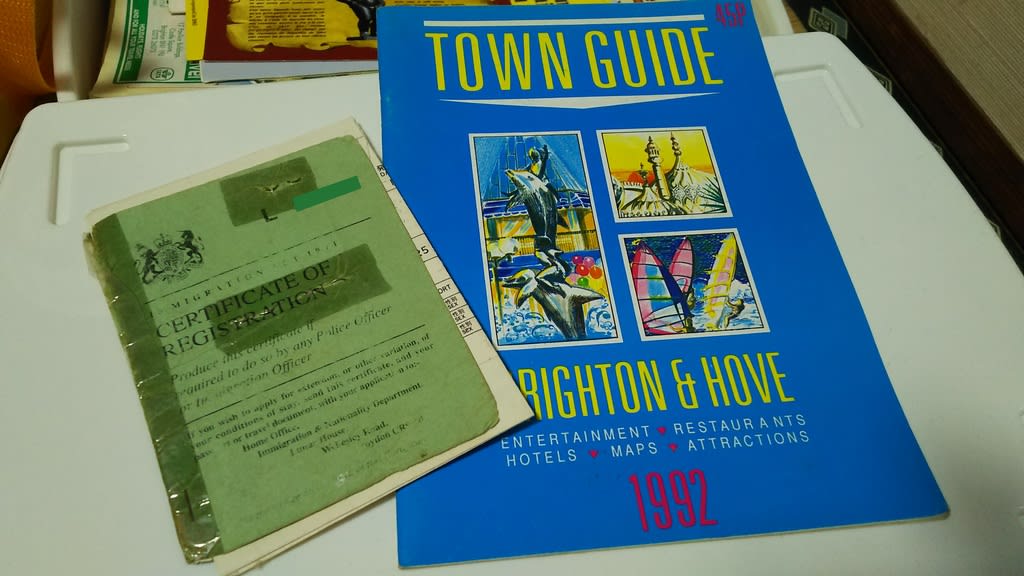僕は夢を見なくなっていた。あの頃は現実が過酷になっていたせいか,唐突に睡魔に襲われ気づくと,ワープした様に目の前の景色が変化している,といった感じで,自分でもいつ眠って目覚めたのか区別がつかない様な毎日を送っていた。どのくらい時が流れたのか,ついさっき自分が何をしていたのかもあやふやな,言ってみれば現実そのものが夢の中の出来事の如く存在していた。
ある夕暮れ時,イーゴと一緒に埋葬した写真の中で楽しそうに微笑むアジャとイーゴを思い浮かべながら,僕はホスピタルの2階から向こう側を流れる河を眺めていた。こちら側は河に沿う様にして大きな通りが見えたが,向こう側には靄が立ち込めていて,薄っすらと森のシルエットが確認できた。あの川を渡れば,アジャの命を奪った敵の拠点に辿り着くはずだが,当然の如く橋は破壊されていたし,かつては県境に過ぎなかった河のこちら側にも敵側の民兵が数えきれないほど潜り込んでいて,ホスピタルに運ばれるけが人や遺体の数は減ることがなかった。それでも,僕が滞在してた7月下旬というのは,その町が敵の猛攻撃を受ける1か月も前のことだったのだ。
「ウィンプ,今日は終わりか」
リアノが僕の背後から声をかけた。僕は返事もせず開けていた窓をパタンと閉めた。その日は朝から4人の埋葬に立ち会ったが,その中の1人は右足を無くした年端も行かぬ女の子だった。半狂乱の母親の前で横になり血の気が引いた真っ白な顔をした少女はリナという名前だった。
「支度をしておけ,今夜出発だ。20:00,エントランスに来い」
リアノが階下へ進む足音に重なる様に女の子が息絶えた時の母親の苦しそうな嗚咽の残音が微かに耳の中で響いていた。
自分が寝ているのか起きてるのか分からないくらいに体中の感覚がぼんやりとしていた。水は飲み過ぎるくらい喉は乾いたが,食事はもう何日も喉を通ってなかった。最初の頃は3日に1回程度の缶詰の支給が少ないと不満をもっていたのに,時間の感覚を失うにつれて1日に3回食事をするという当たり前だった事が飽くまでただの習慣に過ぎないのだと証明するに至った。
支度とは言っても荷物なんか特に持ち合わせていなかったから,僕は同じ場所で暫くぼーっと過ごしてから,待ち合わせの時間より少しだけ早くエントランスに向かった。車寄せには古臭いデザインの車高の異様に高いトラックがエンジンをかけたまま止まっていて,僕は何の迷いもなくその荷台によじ登った。荷台には遺体を運んだあとの血痕や治療の時に脱がせたと思われるシャツや靴などが散乱していた。僕は運転席側にしゃがみ込んで膝を抱え込んでうずくまった。間もなくしてリアノも勢いよく乗り込んできて,僕のすぐ隣に腰を下ろした。そのままトラックが重たそうな音を上げながら走り出した。見送りに来たジェイやラファエルが荷台の向こうで心配そうに眺めているのがわかった。北上して戻るのだろうと思っていたが,トラックは河を左手にして南に向かうのに気付いた。それでも,もう僕は何も気にならなくなっていたから,写真と引き換えに受け取ったアジャのお守りを取り出して眺めた。ジェイから事情を聞いたのだろう,リアノが「お前にも引き金を引く理由ができたのか」とふざける様に言ったが,僕は黙ったままお守りを胸のポケットにしまった。不可解なことにリアノは言葉を発しない僕との同行をまるで心地良いと感じている様な素振りだった。
「もう8月か・・・」
リアノはそう呟くとヘルメットを深く被ってライフルにしがみ付く様にして眠り始めた。日本ではあり得ないほどの日の高さだったが,1時間もすると辺りは暗がりに包まれていった。後で知らされた事だが,実はその時僕たちは国境をもう一つ南側に越えて別の支配勢力の胸元に入り込んでいた。その地域も“連邦政府”から攻撃を受けていてアジャたちと同じ民族も多く住んでいる場所だったから,手引を受けながら容易に侵入することができていた。
イギリスを出発したのが7月13日の土曜日だったから,その日が8月1日だとすると既に2週間以上が過ぎたことになる。そんなことを思って顔を上げると,トラックはいつの間にか森の中を走っていて,生い茂る木々の向こう側に薄紫色の夜空と満天の星が見えた。ふと僕はまるで天国への入り口を見つけた様な変な気持ちになっていた。そのくらい死が身近にあったし,死に対する恐れすら感じなくなっていた。