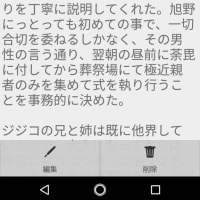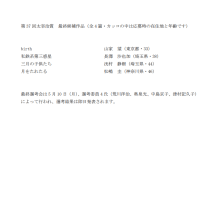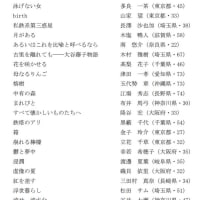ブランズウィックで飲み直そうと提案したのは僕だった。海辺にあるブランズウィックの方がやはりのんびりと寛げたし,自分のフラットから歩いて10分ほどの所だという安心感もあった。それに,日本から来た“OL”だという彼女たちもイギリスに来てほんの数日で実は語学学校も住む場所も決めていないという状態だったから,僕が通っていたホーヴ駅近くの学校や比較的安価なフラットが並ぶ通り等についても興味があるみたいだった。
ブリティッシュグリーンのメトロというマシューの小さな愛車に乗りこんで移動することになった。見た目からは想像出来ない程室内が広く,後部座席の小柄なベンが王様になった様な態度で邦子と直美の隣で満足そうに座していた。ブランズウィックはKing&Queenに劣らず多くの人で賑わっていた。車から降りてすぐに何ともいえない胸の苦しさを覚えて,僕は駐車場側の入り口の数メートル手前で足を止めた。馴染みの客も多いから,僕の姿を見つけると「久しぶりだな」と声をかけてくれる人もいたが,僕は笑顔を向けるのが精一杯で何となく店内に入るのが怖くて仕方なかった。もうそこにはアジャもイーゴもイレイナも円山さんもいない。ブランズウィックは何も変わっていないはずなのに,僕にとっては全く見知らぬ場所になってしまったことをその時初めて思い知らされたのだ。
邦子や直美を口説くのに夢中になっているベンとマシューは,僕のそんな思いなど気にも留める様子がなかった。だから僕がすぐ先にある海辺に酔い覚ましに歩くことを提案すると何の躊躇いもなく快諾してくれた。イギリスの夏は日が長く,そろそろ8時になるというのに昼間のような明るさだった。最初はブランズウィックから逃げるようにして海岸を目指した僕だったが,キングズウェイを渡って海辺の歩道に辿り着いた途端,少し前にブランズウィックで感じた恐怖感に似た感情にまたも支配された。日本では見かけない石浜にはまだ大勢の人たちが散在していて時々はしゃぐ様な叫び声が聞こえてくる。得体の知れない力の様なものに足止めを食らっている僕に流石のベンも訝しさを感じたのか「大丈夫か」と聞いてきた。僕は不機嫌な声で「少し疲れた」とだけ答えた。そのやりとりに少し気が紛れたのかなぜか自然と足が前へ出て,いつしか誰が先頭ということもなくガヤガヤと話しながら海岸沿いを西の方へ進んだ。僕らは勿論英語で談笑していたのだが,邦子や直美がベンたちに日本語を教え始めて,時々僕も意見を挟み込みながら15分程歩いた。ホーブストリートまで来たところでブランズウィックに戻るつもりで北上しているうちに,6月まで通っていた英語学校まで足を延そうという流れになってしまった。僕はいつの間にか,アジャ達との楽しかった1ヶ月を思い起こす様なルートを辿りながら気が付いたときには円山さんが住んでいた家の前で立ち止まっていることに気付いた。最後に見かけた時に掲げられていたFOR RENT”の看板は取り除かれている。すると表で庭仕事をしていた初老の女性が家の様子を見つめていた僕に気づいて声をかけてきたから,僕はフェンス際に走り寄って尋ねた。
「ここを借りられたんですか」
「借りた?」
「ええ,前に“FOR RENT”の看板を見かけたものですから」
「ああ・・・」
僕が開け放たれた窓の奥に円山さんと組み立てていたミニの姿を認めたのに気づいたのか,今度はその女性が尋ねてきた。
「自動車が好きなのかしら?」
突然マシューが近づいてきて話に割って入った。
「キットカーを組み立ててるんですか,すごいですね」
「いいえ,アレはもう処分するところよ」
「ええ! 勿体ない!」
僕が暫く黙ったまま2人のやりとりを見守っていると玄関の方からご主人らしき男性が近づきながら元気よく話しかけてきた。
「前に住んでいた日本人の知り合いかい」
「まぁ,そうなの・・・?」
僕がどう説明しようか迷っていると,ベンがマシューの肩を抱いて言った。
「昔直してたミニよか上等だな」
「結局だめだったからな」
「部品は全部揃ってるんだ・・・」
自分の一言で生じた一瞬の沈黙の中,僕がそのミニに纏わる話を簡単に説明すると,聞き入っていたご主人が何の前置きもなく僕たちを部屋の中へ招待した。
部屋の中にはいくつか見慣れない家財道具があったが,以前とそれほど見栄えは変わってはおらず,カウンターの向こう側にジャッキアップされたミニが所狭しと鎮座しているのが見えた。開いた窓から風が流れて油と鉄のにおいを運んでくる。それを懐かしく味わおうと深呼吸をした途端,なぜか強烈な悲しみが沸き起こってきて,僕はそこにヘタリと座り込んで立てなくなってしまった。驚いた邦子とベンが僕に駆け寄って体を支えてくれたが,僕は涙が止まらなくなってそのまま2人の腕の中で目をつぶって黙ったまま自力ではすぐに立ち上がることはできなかった。痙攣する瞼の向こうで慌てた老夫婦がグラスに水を浪波と注いで直美に渡すのが見えた。マシューは老夫婦に自分たちが数時間前に帰国したことや,旅先での活動のことについて触れながら,きっとその疲れが一気に出ただけなのだと説明していた。マシュー達が老夫婦と紹介し合っているのを見ながら直美に水を飲ませてもらっている内にぼんやりとした視界が徐々にはっきりとしたコントラストを取り戻して,セピア色に映っていた景色が色合いを帯びていった。
それが運命だとするならば,僕は何かに導かれていくように新たなる出会いの中に無理矢理引き戻されて,神という存在が本当にあるのならば,意地悪にも冷たい別れを前提とした優しい出会いという物を僕たちの前に並べて,その様子をほくそ笑みながら眺めているのかもしれない。
ナイト夫妻は元々円山さんが借りていた家のオーナーで,円山さんとの契約が終わった後すぐに入居の募集を考えたものの,円山さんが処分するはずだった組み立て途中のミニが置き去りにされていたこともあって,結局ブライトン中心部にある自宅を売り払って海辺に近いこの家で余生を過ごそうと決心したのだという。幼い頃に機械工の父を亡くしたマシューが高校生の時分に近所から拾ってきたボロボロのミニを直そうと自宅のガレージで悪戦苦闘した経緯に「リベンジを果たさないか」という提案をしたナイトさんは「新しい人生の幕開けに相応しい一大イベントになりそうだ」と良い意味で鼻息を荒くしていた。僕たちに紅茶とスコーンを振る舞ってくれた奥さんもワクワクした様子が隠せず, 「いきなり子供が何人もできたみたい」と嬉しそうに呟いた。すっかり気分が落ち着いた僕はマシューとミニのパーツを一通り確認して,毎週土曜日の午前中にナイト邸で落ち合って円山さんのミニを完成させる段取りをした。