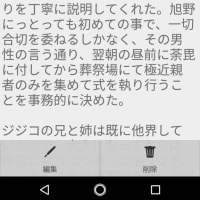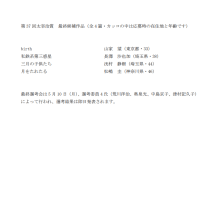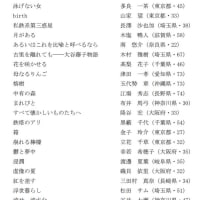“Dream, dream, dream, dream
Dream, dream, dream, dream・・・”
12月13日。僕たちは久しぶりに皆で集まってブランズウィックで寛いでいた。海側のエントランス手前に設置されたジュークボックスからは,僕がリクエストした“Everly Brothers”の名曲が流れている。ナイト夫妻も大いに喜んで,そそくさとパイントグラスを立ち飲み用のテーブルに置くと,カウンター前で2人で踊り始めた。店は例の如く混雑していたが,2人の上品なダンスに誰もが心を奪われて場を囲む様に広がったから,いつの間に舞台が出来上がった。
「ねぇ,私達も踊る?」
カリンが悪戯っぽい眼差しで僕に声を掛けた。
「じゃあ,今度,君と2人だけの時に」
そう言ってはぐらかしてから,僕はナイト夫妻のダンスを眺めて曲を聴いていた。カリンは嬉しそうに微笑んで,テーブルの上でグラスを休ませていた僕の右手の甲に指先でリズムを刻みながら,いつもの様に鼻歌交じりに歌を追いかけた。
その頃,僕の時間は順調に針を進めていた。この平和な時間が永遠に続くことを願いつつも,実はそれには実態もなく,だからこそ英語の“peace”は不可算名詞なのだと実感した。英語と言えば,2度目のミッションで僕が跳弾を受けて左腕に大けがをした時,その弾丸が砕いたコンクリートの破片でパックリと口を開けた額をホチキスみたいな道具で縫い留めながらビクターが話をしてくれたことがある。
「見えるか?」
「ああ,何とか」
僕の左瞼は,丁度眉の上で開いた傷のせいで開かなくなっていたけど,傷を縫ったお陰で辛うじて開けるようになった。それでも額からは思いのほか大量の血が流れ落ちて目にも入り込んでいたから見える景色は赤色に染まって恐ろし気に映った。
「まるで地獄にいるみたいだよ,ビクター」
「でも,本当に地獄に堕ちた訳じゃないよ」
「ジェイは天国に行ったのかな・・・」
ビクターは何も答えず例のごとくヒヒヒと笑ったが一瞬顔を曇らせた。そして僕の傷の上に絆創膏を貼り付けると,今度は僕の左袖をハサミで二の腕間で割いて具合を診てくれた。
「折れてないな。少し切れてるけど」
「ああ,感覚も少し戻ってきたみたいだ」
「じゃあ大丈夫だな」
彼はそう言うと肘の傷に絆創膏を貼って,折角切り裂いた袖を僕の傷を縫ったホチキスでバチバチと留めてくれた。僕はそのまま仰向けに寝て本当は青いはずの「赤い空」を眺めていた。
遮蔽物の向こう側から,1発銃声が轟いた。ガチャガチャという金属のスライドが廃莢と装弾を同時に行う音の後,「10インチ,右」という声と同時に銃声が聞こえた。それは明らかに人間の命を奪う為のやりとりで,その後も何回か繰り返され,やがてあの雨音の様な着弾音は止んだ。安堵のため息とガヤガヤとした話し声が周囲から漏れてきた。
赤い空に少しずつ青味が戻ってくると,僕は上を向いたまま,誰にと言うことではなく,むしろ自分自身に対してポツリと呟いた。
「僕は何で生きてるんだろう」
さっき頭から転んで耳鳴りが激しかったせいか声が大きかったのだろう。間髪を入れずにビクターが応えた。
「We must live to die」
「死ぬために?」
「辿り着く先はね。だから“We must live today to die”ってことだよ。コックニーさ」
英語の授業で前置詞のtoは自分が見ている先を示すもので,時刻や場所を表す語の他に次に行おうとしている動詞を置くことができるのだと習った。まだ距離がある場合に用いられるから行先や動作はいろいろと変更する余地もあるのだと。「生きる」という意味の“live”前の“must”には「絶対」という覚悟がある。差し詰め「どうせ誰しも死に向かってるんだから今日を覚悟して生きよ」ということなのだと僕は解釈した。
するとリアノが傍らに座って僕の様子を覗き込みながら付け加えた。
「ま,小説みたいなもんだよ」
「小説?」
「ああ。1ページずつ読んでくから面白えんだ。いきなり最後は読まねぇだろ」
いつになく優しい口調のリアノが僕を見下ろしていた。最初のミッションの帰り道で敵の攻撃を予見したなんてことをリアノは本気で信じていたらしく,奇妙な物を見る様な眼差しを僕に向けることがあった。
“When I want you in my arms
When I want you and all your charms
Whenever I want you
All I have to do is dream
Dream, dream, dream
When I feel blue in the night
And I need you to hold me tight
Whenever I want you
All I have to do is dream・・・”
ナイト夫妻は,嬉しそうに周囲を囲む客たちの真ん中で優雅に踊り続けていた。僕もふと我に返って,目の前のカリンの幸せそうな様子を眺めながら,「この時間こそ,かけがえのない瞬間なんだな」と感じていた。カリンがリズムを取りながらナイト夫妻の方へ気を取られた時,それとは反対側から笑い声交じりの大きな声で話す声が僕の耳に届いた。
「物凄いぜ。1発で血の海さ」
僕は夫妻に見とれている数人の客の向こうのテーブルで,すっかり出来上がった若者3人組の話に耳を傾けた。
「オレはそのメルセデスの運転席に狙いを定めた」
「それで?」
ダッフルコートを着た短髪の体格のいい若者が自分の武勇伝を仲間に聞かせていたのだが,しばらく聞いていて,それが明らかにアジャの国での出来事なのだと僕は確信した。
「まぁ,慌てるな。そいつらは荷物を屋根にロープで括り付けて逃げようとしてたんだ」
「それを撃ったのか」
「ああ,逃がすもんか」
“・・・I can make you mine
Taste your lips of wine
Anytime night or day
Only trouble is
Gee whiz
I'm dreamin' my life away・・・”
「ガラスがバシャっと真っ赤に・・・」
「おい,そんな話やめろ,人殺し!」
僕は無意識にそいつを怒鳴りつけていた。
「なんだ,お前」
「そんな話は聞きたくないんだって言ってんだ!」
「お前に話しちゃいねぇだろ」
「黙れ,人殺し!」
僕は自分のテーブルから離れて,騒然と引き下がる客の間を縫って迫りくるその男と対峙した。20㎝くらい高い所から見下ろす男は僕の胸倉をギュっと掴んで,酒臭い息を吐きながら僕の顔面に向けて「この野郎」と威圧した。僕は自分を制御できないくらいの怒りが混み上がってきて,思い出すと自分でも恐ろしいくらいの汚い言い方で彼を罵倒した。
「人殺しがしたくて行ったんだろう,お前はキチガイだ!」
次の瞬間,彼の拳が僕の左顔面を捉えていた。僕はテーブルの上のグラス諸共薙ぎ飛ばされ床に倒れ込んだ。騒然とした店内から女性の悲鳴が重なって聞こえた。口の中が切れてしまったが,僕は血を吐き出しながら更に彼を罵倒し続けた。
“I need you so, that I could die
I love you so and that is why
Whenever I want you
All I have to do is dream
Dream, dream, dream, dream・・・”
その男が息を荒くして僕が倒れている所へ歩み寄ってくるのが見えた。店内が静まり返ってジュークボックスの音が耳鳴りの向こうから木霊の様に聞こえてくる。僕は自分の血液が口内で甘く広がっていくのを感じていた。