(シューマンの「新しさ」?(その2)のつづき)
シューマンの評論を読んでいると、管弦楽曲でもピアノにアレンジされて
出版されたスコアを見ながら評論しているらしいことに気づく。
ベートーヴェンのピアノソナタは管弦楽曲のようにきこえ、
部分部分でオーケストラのどの楽器が担当しているといった風な想定をさせるともいう。
すると、ベートーヴェンの音楽はピアノ曲を意図していても
管弦楽を響かせるスケールを持っているということであろう。
ショパンのピアノ曲にもこれに近いスケールを感じるが、
ショパンの場合は、ピアノそのもののスケールが大きい気がする。
だからショパンの衝撃は大きいのだろうと、常々一人で満足している。
それまでのピアノ曲、シューベルトやメンデルスゾーンやシューマンなどは、
きれいでかっこいい(2回目)。
19世紀前半に、現在のピアノフォルテの形が完成する。
これと時期を同じくして、形式面から脱却するロマン派の自由な着想があらわれ、
さらに表現の美しさや甘美さなどの個性が加味される。
そこにピアノフォルテを弾く技量があれば、
一人ですべてを表現できてしまう時代に入ったといっていいような気がする。
(後にブラームスのハンガリー舞曲やドヴォルザークのスラブ舞曲集などが
作られるが、これらは、お金持ちの家に据え付けられるようになった
ピアノを家庭で連弾でもして楽しめるようにという
商業的な意図も含めて作られたらしいことが、
ピアノという楽器の性格を表しているような気もする。)
そんなこんなを比べてみると、ウィーン古典派の時代というのは、
対位法よりむしろ和声法をフル回転して、ソナタ形式が表現のかたちを整えた。
バロック音楽と呼ばれるころまでは、和声法や調性音楽があるにもかかわらず、
管弦楽作品の編成が小さい。
おそらく対位法は、それぞれが多くの禁則に縛られながらも、
あまりにも各音が独立しているから、
楽器編成が小さくとも作品の緻密さは聴く人を満足させるのであろう。
交響曲のようなスタイルが確立して管弦楽作品がそうした規模に馴染んでくるが、
和声法はどう考えても別の音が響きを作って平行移動をするので、
次に出てくる欲求はより重厚な響きで、
それが管弦楽や交響曲をさらに大きくしていったのだろう(きっと)。
形式と和声法で音楽が大きくなり始めた(あるいは大きくしたのかもしれない)
ウィーン古典派の人たちが、「良い音楽」をつくろうと思えば、
あらゆる響きの可能性が頭の中をグルグルとめぐったことだろうと
勝手に推測してみる。
とすれば、モーツァルトもベートーヴェンも、
鍵盤楽器であれ管弦楽やオペラであれ、大きなものを築き上げる構想の中で、
様々な曲を書いたのであろうから、
もはやピアノの時代の人々とは構想の規模が違うのかもしれない。
ピアノ時代の一流の作曲家(音楽家)は一流の音楽家ゆえに
管弦楽法などにも通じている。その知識を使えば、管弦楽曲も作ることができる。
しかしそれは天分の向き不向きとは別問題ではないかという気がする。
19世紀前半のドイツ人たちの交響曲が「今ひとつ」と思う人たちには、
こう考えることで、納得も我慢もできるのではないだろうか。
シューマンが、ショパンのピアノやベルリオーズの管弦楽を新しいとするのも、
そこにあるのではないか。
--------
フルトヴェングラー/バイロイトの「第9」を聴きながらだと、
かくも筆が走るものかは。




シューマンの評論を読んでいると、管弦楽曲でもピアノにアレンジされて
出版されたスコアを見ながら評論しているらしいことに気づく。
ベートーヴェンのピアノソナタは管弦楽曲のようにきこえ、
部分部分でオーケストラのどの楽器が担当しているといった風な想定をさせるともいう。
すると、ベートーヴェンの音楽はピアノ曲を意図していても
管弦楽を響かせるスケールを持っているということであろう。
ショパンのピアノ曲にもこれに近いスケールを感じるが、
ショパンの場合は、ピアノそのもののスケールが大きい気がする。
だからショパンの衝撃は大きいのだろうと、常々一人で満足している。
それまでのピアノ曲、シューベルトやメンデルスゾーンやシューマンなどは、
きれいでかっこいい(2回目)。
19世紀前半に、現在のピアノフォルテの形が完成する。
これと時期を同じくして、形式面から脱却するロマン派の自由な着想があらわれ、
さらに表現の美しさや甘美さなどの個性が加味される。
そこにピアノフォルテを弾く技量があれば、
一人ですべてを表現できてしまう時代に入ったといっていいような気がする。
(後にブラームスのハンガリー舞曲やドヴォルザークのスラブ舞曲集などが
作られるが、これらは、お金持ちの家に据え付けられるようになった
ピアノを家庭で連弾でもして楽しめるようにという
商業的な意図も含めて作られたらしいことが、
ピアノという楽器の性格を表しているような気もする。)
そんなこんなを比べてみると、ウィーン古典派の時代というのは、
対位法よりむしろ和声法をフル回転して、ソナタ形式が表現のかたちを整えた。
バロック音楽と呼ばれるころまでは、和声法や調性音楽があるにもかかわらず、
管弦楽作品の編成が小さい。
おそらく対位法は、それぞれが多くの禁則に縛られながらも、
あまりにも各音が独立しているから、
楽器編成が小さくとも作品の緻密さは聴く人を満足させるのであろう。
交響曲のようなスタイルが確立して管弦楽作品がそうした規模に馴染んでくるが、
和声法はどう考えても別の音が響きを作って平行移動をするので、
次に出てくる欲求はより重厚な響きで、
それが管弦楽や交響曲をさらに大きくしていったのだろう(きっと)。
形式と和声法で音楽が大きくなり始めた(あるいは大きくしたのかもしれない)
ウィーン古典派の人たちが、「良い音楽」をつくろうと思えば、
あらゆる響きの可能性が頭の中をグルグルとめぐったことだろうと
勝手に推測してみる。
とすれば、モーツァルトもベートーヴェンも、
鍵盤楽器であれ管弦楽やオペラであれ、大きなものを築き上げる構想の中で、
様々な曲を書いたのであろうから、
もはやピアノの時代の人々とは構想の規模が違うのかもしれない。
ピアノ時代の一流の作曲家(音楽家)は一流の音楽家ゆえに
管弦楽法などにも通じている。その知識を使えば、管弦楽曲も作ることができる。
しかしそれは天分の向き不向きとは別問題ではないかという気がする。
19世紀前半のドイツ人たちの交響曲が「今ひとつ」と思う人たちには、
こう考えることで、納得も我慢もできるのではないだろうか。
シューマンが、ショパンのピアノやベルリオーズの管弦楽を新しいとするのも、
そこにあるのではないか。
--------
フルトヴェングラー/バイロイトの「第9」を聴きながらだと、
かくも筆が走るものかは。










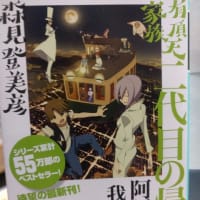









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます