誰だったか、、
「悲観論に陥るのはすごく簡単なこと」って言ってて
なんだか自分のことを言われているようで恥ずかしさもあり、
それをきっかけに、いつもの悲観論のあと、
ひとまず楽観論も考えてみるよう試みだした。
少し自分自身落ち着いてきたと思う。
周囲はどう感じてるのだろうか。。
少しは好かれてるといいなあ

うつ・不安ネット
心のスキルアップ・トレーニング
http://www.cbtjp.net/downloads/skillup/
上記ページ資料より
【落ち込んでいるとき 否定的認知の3徴】
◆ 自分自身に対して
自分はダメな人間だ
自分には何の力もない
◆ 周囲との関係に関して
まわりの人たちは迷惑だと考えている
まわりの人たちから嫌われている
◆ 将来に対して
これからもつらいことばかりだ
良いことなんか起こるはずがない
(同上、資料より一部抜粋)
悩みを抱えたある人が、「死ぬ気になったら何でもできるというのは頭ではわかるけど、一人では死ぬ気にはなれないんだ」とおっしゃっていました。
たしかにそうなんです。
たしかにそうだ。
心理的にそばにいてくれる人がいると思えると、強くなれる。
それは家族だったり、友人だったり、尊敬できる人だったりするけど、、
ああ、だから‘お金で対応してくれる専門家’に頼むのは
自分がそういう対象を自ら開拓できないって認めるようで、私には難しいのかも
ただ、専門家はきちんと学んでいるから
必要に応じ、手助けを得るのはおかしいことじゃないのだけど。
悩んでいる人のケアの中で、その人の周囲がその人とよい関係を築けるようにもサポートしてくれる
っていうのは、専門家だからこそ説得力を持つ気もする
(↓同上資料より抜粋)
悩んでいる人を手助けしている人は伴走者ですし、応援団です。
コーチでもあります。
コーチというのは、伴走をしながら、専門的スキルを使ってあるところまで送り届ける人です。
その専門的スキルの中心になるのが、認知療法では、このカギ括弧の中身、「そのときに、頭に浮かんだ考えやイメージ」です。
これが「自動思考」です。
デンマークって、すごくうつが多いらしい。
だからだろうか、働く人の3分の1が公務員で、
その多くが社会的仕事をして、たいていの人が‘療法’を学んでるって感じがする
日本もそうなのだろうか
ああ、今やっと療法とか心理学ってすごく社会に役立つんだとの実感がでてきた…
(同上資料より抜粋)
この自動思考を手がかりに一緒に現実を見ていくようにします。
確かに落ち込んでいるときには、悪い側面ばかりが気になります。
これはつらいのですが、必要なことでもあります。
何か改善をしないといけないから落ち込んでいるわけで、そのためには改善する必要のある悪い側面に目を向けないといけません。
しかし、悪いところばかりを見ているとたまらなくつらくなります。
うまくいかないことがあっても、普通は悪いことばかりということはなく、良いことだってあるはずです。
良さ、悪さにも、それぞれ程度があります。
ですから、もう一度現実に目を向けて、何か見落としていることがないのか、良い材料はないのかを考えてみます。
確かにうまく行っていないかもしれません。
しかし、もしそれが本当だとして、これからどのようなことが起きるのかを考えてみます。
そのときに、最悪の展開と最善の展開を考えてみるといいでしょう。
これを専門的には「シナリオ法」と言います。
そうすると、両極端の真ん中辺りに、現実的なほどほどのところが見えてきます。
このように極端に悲観的になった考えを、現実に照らし合わせながら見直していくのが認知療法・認知行動療法です。
マイナス思考になっているからといって、必ずしもプラス思考になる必要はありません。
プラス思考が良くないことだってあります。
例をひとつ挙げてみましょう。
よく使われる例です。
コップに水が半分入っているときに、「水が半分しか入ってない」と考えると不安になって焦ってきます。
ですから、「水が半分も入っている」と考えれば良いじゃないか、そのように考えれば気持ちが楽になる、と言われます。
確かに、今私たちが街の中で生活しているときにはそれで良いでしょう。
しかし、山奥や砂漠で、すぐに水が手に入らないような場所にいる時に「水が半分も入っている」と考えて全部飲んでしまうと、あとで大変な思いをすることになります。
自分の考えが役に立つかどうかは、常に現実の中で判断しないといけないのです。
このように私たちが現実に生きていくのに役に立つ考えを「適応的思考」といいますが、そのポイントはその人にとって役に立つかどうかです
それには現実に照らし合わせながら判断をすることが大事です。
現実を見ないまま「水が半分しか入ってない」と考えるのも、「半分も入っている」と考えるのも、どちらも決めつけです。
そのときに、一方に決めつけないで、現実を見ながらしなやかに判断をしていくようにします。
「しなやか」というのは、ひとつの考えに凝り固まらないで、情報をたくさん集めて判断するということです。
情報を集めれば、いろいろな可能性や解決策が見えてきます。










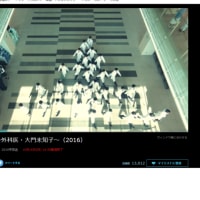


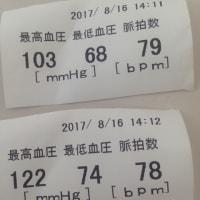


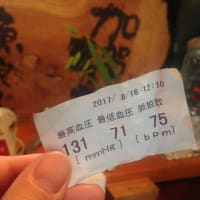



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます