「GDPギャップ」を一般的には「需給ギャップ」と言い、
[GDPギャップ]=「総供給]-[総需要]>0
の時が「デフレ」であると、多くの場合は誤解されています。現実の世界では常に、
[総供給]=[総需要]・・・(〇)
です。勿論、生産量以上に買うことは出来ないので、
[総供給]<[総需要]・・・(X)
が成り立たないのは分ると思いますが、
[総供給]>[総需要]・・・(X)
ならば成立すると思われがちです。つまり、生産過剰で売れ残りがある場合です。ここで誤解されているのが「需要=消費」と思っている場合です。実は、「売れ残り額」には既に「前段階の需要額」や「加工費(支払い済みの労務費など)」が含まれていて、「次の段階の供給(或いは消費)」に回らなくても、「需給バランス」は取れていると云う事です。
例えば、小売店が売れると思って過剰に仕入れた商品は、既に問屋に支払い済み(買掛け仕入れでも会計上は買掛金として計上済みで、金銭の貸借と見做される)なので、個別に[金額ベース]で見ると、
[政府]
(↑↓消費税を仮払いし、輸出の場合は還付を受ける)
[メーカー(供給)]=[問屋(需要)]
↓(利潤を上乗せし、消費税を仮払い↑)
[問屋(供給)]=[小売店(需要)]
↓(利潤を上乗せし、消費税を仮払い↑)
[小売店(供給)]=[消費者(需要)]
↓(付加価値の合計と、消費税全額を支払う↑)
[消費者(消費)]
が成立していて、その総計が、
「総供給額]=[総需要額]
となり、「売れ残り品」は次の「供給」に回らない状態なので、以前の「需給」はバランスが取れていて等価となります。
つまり、
[GDPギャップ]=[潜在的な生産能力]-[現実の生産額(供給額)]
が正しい計算式で、需要の無い不良在庫品や仕掛け品(半製品)・原材料などは「潜在的な生産能力」に含まれ、「現実の生産額(供給額)」には含まれていません。
ここで、「潜在的な・・・」には二通りあって、
・最大概念;過去の実績を踏まえ、生産手段を可能な限り総動員した場合の最大値。
・平均概念;過去の実績を踏まえ、その実績の平均値。
です。現在は「平均概念の生産能力」を「潜在的な生産能力」としているので、政策的にはGDPが低くなりがちです。「GDP」を低く抑えると国力も衰えるのですが、同時に円安にもなるので、輸出企業や海外に投資している金持ちは笑いが止まりません。
円安になると輸入物価が上がり、富(通貨)が海外に流れてデフレ(この場合はスタグフレーション)が起きる可能性が有ります。デフレとは「通貨収縮」を意味するので市中の通貨量(流動資金)が減少する一方、「蓄財されている資金の価値(量ではない)」が相対的に増加します。これまた金持ちは笑いが止まりません。
デフレ、特にスタグフレーションで損をするのは、常に可処分所得で目いっぱいの消費支出を強いられる貧乏人です。外貨建て資金を保有している金持ちは、物価が上がる分以上に、円安で「円換算の資金(利息も加算)」が増加します。
「デフレ(通貨収縮:通貨価値の上昇)」は、可処分所得と蓄財が多い人が有利になる経済状況と言えます。
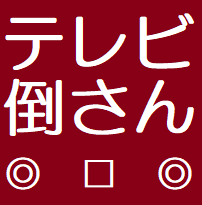
[GDPギャップ]=「総供給]-[総需要]>0
の時が「デフレ」であると、多くの場合は誤解されています。現実の世界では常に、
[総供給]=[総需要]・・・(〇)
です。勿論、生産量以上に買うことは出来ないので、
[総供給]<[総需要]・・・(X)
が成り立たないのは分ると思いますが、
[総供給]>[総需要]・・・(X)
ならば成立すると思われがちです。つまり、生産過剰で売れ残りがある場合です。ここで誤解されているのが「需要=消費」と思っている場合です。実は、「売れ残り額」には既に「前段階の需要額」や「加工費(支払い済みの労務費など)」が含まれていて、「次の段階の供給(或いは消費)」に回らなくても、「需給バランス」は取れていると云う事です。
例えば、小売店が売れると思って過剰に仕入れた商品は、既に問屋に支払い済み(買掛け仕入れでも会計上は買掛金として計上済みで、金銭の貸借と見做される)なので、個別に[金額ベース]で見ると、
[政府]
(↑↓消費税を仮払いし、輸出の場合は還付を受ける)
[メーカー(供給)]=[問屋(需要)]
↓(利潤を上乗せし、消費税を仮払い↑)
[問屋(供給)]=[小売店(需要)]
↓(利潤を上乗せし、消費税を仮払い↑)
[小売店(供給)]=[消費者(需要)]
↓(付加価値の合計と、消費税全額を支払う↑)
[消費者(消費)]
が成立していて、その総計が、
「総供給額]=[総需要額]
となり、「売れ残り品」は次の「供給」に回らない状態なので、以前の「需給」はバランスが取れていて等価となります。
つまり、
[GDPギャップ]=[潜在的な生産能力]-[現実の生産額(供給額)]
が正しい計算式で、需要の無い不良在庫品や仕掛け品(半製品)・原材料などは「潜在的な生産能力」に含まれ、「現実の生産額(供給額)」には含まれていません。
ここで、「潜在的な・・・」には二通りあって、
・最大概念;過去の実績を踏まえ、生産手段を可能な限り総動員した場合の最大値。
・平均概念;過去の実績を踏まえ、その実績の平均値。
です。現在は「平均概念の生産能力」を「潜在的な生産能力」としているので、政策的にはGDPが低くなりがちです。「GDP」を低く抑えると国力も衰えるのですが、同時に円安にもなるので、輸出企業や海外に投資している金持ちは笑いが止まりません。
円安になると輸入物価が上がり、富(通貨)が海外に流れてデフレ(この場合はスタグフレーション)が起きる可能性が有ります。デフレとは「通貨収縮」を意味するので市中の通貨量(流動資金)が減少する一方、「蓄財されている資金の価値(量ではない)」が相対的に増加します。これまた金持ちは笑いが止まりません。
デフレ、特にスタグフレーションで損をするのは、常に可処分所得で目いっぱいの消費支出を強いられる貧乏人です。外貨建て資金を保有している金持ちは、物価が上がる分以上に、円安で「円換算の資金(利息も加算)」が増加します。
「デフレ(通貨収縮:通貨価値の上昇)」は、可処分所得と蓄財が多い人が有利になる経済状況と言えます。
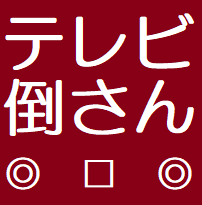










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます