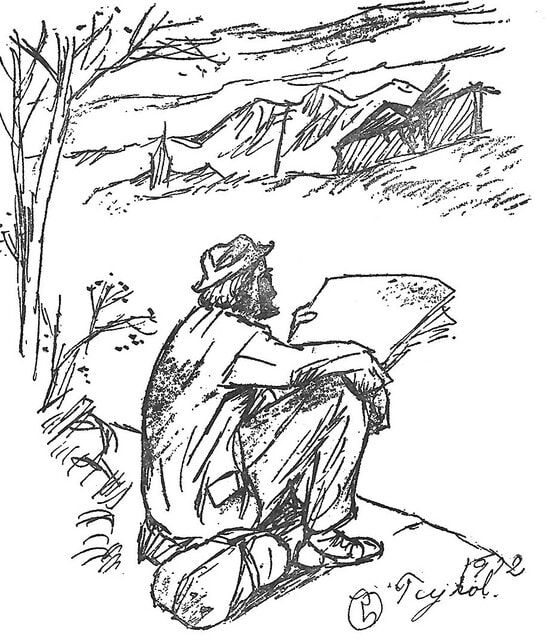今回は作家の鎌原正巳です。
1931年(昭和6)、夢二は翁久允に誘われて、「榛名山美術研究所」設立の計画を一時中止し、アメリカへ旅立ちました。
ところが、夢二がほとんど無銭状態だったことがわかったり、アメリカの新聞社の労使対立に巻き込まれたりして二人は仲たがいし、夢二はその後独り身で流浪の旅を続けました。折悪しくアメリカは大不況の中にあり、絵を売ってその資金でフランスに行こうという当初の計画は破綻しててしまいます。
それでも借金してヨーロッパに渡った夢二でしたが、貧困に苦しみながらも多くの国を巡り歩きました。そして1933年(昭和8)、ドイツのベルリンにある画塾で日本画を教えることになりましたが、ナチスの台頭によりユダヤ人学生を失い、とうとう帰国を余儀なくされたのです。
夢二は帰国後1か月余りで台湾へ旅立つのですが、このエッセイはそのわずかな在日期間に夢二と会った記録という内容で、当時の夢二に関する資料が少ないため、非常に価値のあるものと思われます。(次男の不二彦は、夢二が変わり果てた姿で帰国し、その後は眠ったり原稿を書いたりしていたと書いています。)
正確には、夢二は1933年9月18日に神戸港に到着、そして10月23日に神戸港を台湾に向けて出発していますので、訪問はその間ということになります。「晩秋」とされていますが、定説では、晩秋は10月23日~11月6日のようなので、これよりは少し前、ということになると思います。ただ、その頃夢二は台湾に行く準備をしていたはずですが、当時は台湾は日本統治下にあったため、国内という意識も強かったので、特に言及されていないのかもしれません。
*本文は、女学生雑誌『白鳥』第1巻第5号(1947.8)に掲載された「晩年の夢二と語る」です。
東京の郊外、世田谷区松原に竹久夢二を訪ねたのは、一九三三年の晩秋のある晴れた日の午後であった。
郊外電車の駅に下車して五分ほど歩くと低い丘が続き、その一画がクヌギとアカシアの倭林にかこまれている。その林のなかの小径は、黄色や褐色の落ち葉におおわれ、歩くとバサ、バサと乾いた音がする。秋の足音である。
丘の下からは見えなかった赤レンガ建の家が、林の間から見えてくる。オニツタのからんだ家、相当古びたその家は、ポーの『アッシャー家の没落』を思わせる。
玄関わきの呼び鈴をツタの葉の間に探し、ボタンを押す。室内のどこかでベルの音が響き、やがて老婆が顔を出す。家政婦らしい。
玄関にはいる。うすぐらい光の中に、土間の片すみに据えられた橋の欄干様の装飾が目にとまる。近づいてよく見ると、擬宝珠のついている本物の欄干で、「天文四年、大坂農人橋」という文字が刻まれている。
やがて通された応接間で、わたしはしばらくの間主人公の現れるのを待っていた。
夢二といえば、いまの若い人たちには余り親しみのない人間かも知れない。しかしその年譜を見ると、明治・大正時代の抒情画家としての足跡は大きい。生まれたのは明治十七年(一八八四)岡山県の片田舎においてである。明治三十四年上京、早稲田大学の商科に学んだが間もなく退学し、絵画に専心し、抒情画を試み、全国の青年子女を魅了した。明治四十年以降約十五年間にわたり、声明を得たのである。
のち新聞、雑誌の挿画に筆を染め、また大正三年九月、東京日本橋に自作錦絵、婦人装身染織品などの店「港屋」を開いて装飾美術に対する才能を示し、さらに商業美術への進出を志し、同十二年にドンタク図案社を設立した。昭和五年から三ヵ年にわたり欧米を漫遊帰朝後、宿痾の肺患のため静養の日々を送っていた。
わたしの訪れたのは、そのような「旅路の果て」にある夢二のもとであった。
六畳ほどの洋風の応接間には、背にこまかな彫刻のしてあるロココ風の椅子、かつての豪華さをしのばせる色あせたソファ、暗い壁間には夢二の筆になる「少女の像」が一枚かけてあるだけ。ほかに何一つ置いてない殺風景で陰気なふんい気のただよっている応接室である。
窓から見える裏庭には、午后の日ざしを受けて山茶花が咲きにおっている。つややかな葉に、こぼれるように秋の日がおどっている。夢二の家と、明るい山茶花は、ちょっと不釣合いな感じである。崩れかけたヴェランダ、はげ落ちそうになっている天井の壁、庭先の葉の落ちつくしたアカシヤ、庭隅の枯れたクマザサ――夢二はむしろこのようなところに、彼の安住の場を見出しているのかもしれない。
やがて廊下に足音がして夢二が現れた。
彼を横浜の埠頭に見送ってから、すでに三年の歳月が流れていた。欧米各地の放浪の画の旅から、彼は何をもって帰ってきたのであろうか。彼の頭髪にはめっきり白髪がふえている。そして眼鏡の奥に光る瞳には深い憂いのかげがきらめいていた。
「よく来てくれましたね」
夢二はじっとわたしの方を見つめてつづけた。「近ごろは毎日寝てばかりいます。日本に帰って来たら、眠むくて仕方ないんですね。東京の街にもさっぱりごぶさたしていますよ。君たち若いものが訪ねてくれると、ほんとうにうれしいですよ」
夢二はテーブルの上から外国煙草を取り上げてわたしにすすめる。
すでに五十にもなっている人間のどこに、欧米を放浪して歩いた情熱がひそんでいるのであろうか。ほほはこけ、やせて弱々しいからだのどこにそんな力があるのだろう。サンフランシスコからニューヨークに行くのに、汽車賃が足りなくて、パナマ運河をまわる貨物船に乗って東海岸に渡ったというエピソードを持つこの老芸術家のどこに、そのような生活力がひそんでいるのだろうか。
夢二はしずかに語る。
「人間を信じることができなくなるのはおそろしい。人生にとってこんな不幸なことはない。だがぼくは人を信じすぎ、そしていつも裏切られる。人々に利用され、そして揚句のはてに捨てられる。ぼくのなかに最後に残されるものは、人を信じられないということです。欧米の旅において、また帰国後の一、ニの小旅行において、いつもはぼくが握らされるのは、適当な報酬ではなくて、人間不信のにがい汁ばかりです」
人のいい芸術家を利用して、金儲けに狂奔する商売人は、いつの時代にも幅をきかせている。
夢二はまたつづける。
「ぼくには一人の息子がいます。時々顔を合わせるがめったにゆっくり話したこともない。でも先日、ちょっと浅草までいっしょに出てみました。しかしその息子ともぴったりしない。そのときも考えたけれど、ぼくが今、死の床についたとしても、息子に看とられて死んでいこうとは思いませんね。ほかの肉親の者も、むかし恋人だった女も、誰も知らないうちに、ひとりで静かに死んで行きたいという気持ちですね」
わたしは夢二の顔を見ていた。あまりにもいたいたしい言葉に思えたからである。だが彼の顔は平静である。
傾きかけた窓外の日ざしを眺めながら、夢二はまた語りはじめた。
「電車に乗ったとき、ふと前の坐席にいる人間を観察し、ぼくはふとこれは人類ではないのではないかと思ったりすることがある。ある者は馬に見え、ある女は風船玉だったり、重役然とした男がカワウソに見え、その隣の中年男が豚に見えたりする。万事こんな調子なんです」
「それはゲオルグ・グロッス的ですね。グロッスの風刺画の発想も、案外そんなところにあるのかもしれませんね。先生の今後のお仕事に、そういう画が出てきたらおもしろいですね」
わたしはそんなことをしゃべりながら、豚のような資本家、金のために貞操を捧げる若い女、搾取される労働者などを画題にしたあのドイツの画家と、この老風俗画家とを対比して考えていた。それは余りに距離のある対比にちがいなかった。グロッスの意識した現実把握のきびしさとはげしさは、おそらく夢二には欠けたものであろう。そして夢二の独特な抒情は、グロッスのなかにはその片鱗さえも残していないであろう。むしろグロッスはそのような抒情は意識して排除した画家ではなかったろうか。
しかもわたしは、この大きな距離感を持った二人の画家に共通なるあるものを感じるのだ。それは画材を常に庶民の風俗のなかに見出したということである。そしてそれを、それぞれ自分のものとして一つの完成にまで到達させたということである。
夢二は、わたしの訪問した一ヵ月後、信州の富士見高原療養所に入院した。そして翌年、彼の希望通り、肉親にも看とられることなく、ひとり淋しく五十一歳の生涯を高原療養所のベッドに閉じた。昭和九年九月一日のことである。
(編者注1)鎌原正巳(かんばら まさみ(1905年5月14日 - 1976年3月15日)
日本の作家。長野県埴科郡松代町(現:長野市)に生まれ、松本高等学校文科乙類卒、京都帝国大学文科中退。早稲田大学出版部にて雑誌編集等に携わる傍ら、1939年に古谷綱武、森三千代らと同人誌『文学草紙』を創刊。1947年-1966年東京国立博物館に勤務し資料室長となる。1954年「土佐日記」で芥川賞候補、「曼荼羅」で再度候補。70年文化財功労者となる。(wikipediaより)
(編者注2)ゲオルグ・グロッス:1893-1959 George Grosz/ジョージ・グロス(ゲオルゲ・グロッス)
20世紀最大の風刺画家(諷刺画家)と呼ばれたジョージ・グロス。ちなみにゲオルゲ・グロッスという表記は間違い。彼はダダイストであり、ドイツ表現主義でもありました。海外の著名人だけではなく、日本の作家や芸術家にも影響を与えた人物です。最初に紹介する本もグロスに影響を受けた柳瀬正夢が編著した本になります。この本は日本の画家である松本竣介にも影響を与えました。(「文生書院」サイトより)