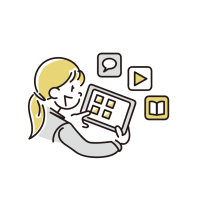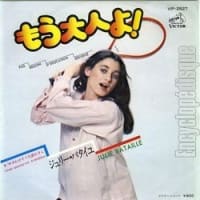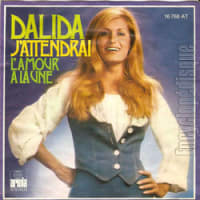日経の朝刊を読んでいたら、元鳥取県知事、元総務大臣の片山善博氏のインタビュー記事が目に付きました。「教育岩盤」というシリーズ記事で今日の見出しは『地域は国の指示待ち脱せ』というものでした。いくつかの論点はありますが、「明治時代の学制発布で教育制度が整備された時は、教育は極めて地域の問題だった(中略)今は国の問題だとみなす人が多い。地方自治の問題、教育委員会の責任という意識はほとんどない。」ということが大きな問題提起の一つでしょう。
教育に限らず、我が国は国と地方のありようが常に問題になってきました。「常に」と言うより「明治以降」と言った方が良いでしょうか。
教育に関して言えば明治以前、教育は各藩の問題であり、身分制の中で教育を受けることが出来るのは藩士の師弟で農民や商人、職人などは上方で言う「寺子屋」江戸でいう「筆学所」「幼童筆学所」に行きました。まあ、今では「寺子屋」の方が一般名称のようですが・・・。
ウィキの記事を流用させて頂くと、『1883年に文部省の全国調査を基に編集した『日本教育史資料』によると安政から慶応の時代、全国に16560軒の寺子屋があったといい、江戸だけでも大寺子屋が400-500軒、小規模なものも含めれば1000-1300軒ぐらい存在していた。 』とのことです。これは大変な数字です。2019年の全国の小学校数は約19,000校とのことですから、江戸時代の地方の初等教育は国家による統制がなくとも現在の水準に近かったのかもしれませんね。
明治以降、富国強兵の中央集権政治の下、皇国史観をたたき込む教育が行われ、日本人全体として・・・それまで教育を自分たちの問題と捉える意識から国家的な命題とするようになりました。勿論日本という資源小国にとっては人財は宝物であり優れた教育は不可欠であるにしても。
でも、戦後70年以上経っても、また、地方分権一括法が成立し、改めて教育は「自治事務」だと示されても、文部科学省から末端の市町村教育委員会や小中学校に至る「上意下達」の体質は少しも変わりません。
仮に、小学校に問題が発生したら、市町村の教育委員会は「厳しく指導して行きます。」と答えるでしょう。同じように、市町村の教育行政に問題が生じれば都道府県の教育委員会は「厳しく指導を徹底します。」と答えます。
そう「指導」です。文科省を頂点に「指導する」体制は戦前と何も変わりません。
更に、教科書の問題もあります。法令上の位置づけなどは飽くまで『参考』しかし、その精神的な意味合いは明らかな国家統制なのに、もうそれが当然になっています。教科書問題に踏み込むと長くなりますのでこの辺にしますが、国民も自分の子供のことになると、幼稚園から大学まで「良い学校」に入れる事が目標、公立より私立の方が東大に入りやすい・・・
教育を自分たち地域の問題としては考えていません。おそらく、人口の減少と相まって、日本の人財力の低下は顕著な現象となりつつあるのではないかと懸念せざるを得ません。次の百年、日本はどうなるのでしょう・・・