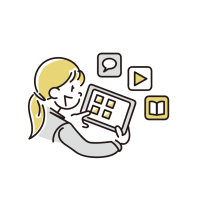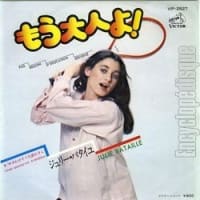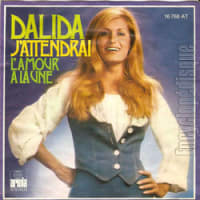新聞で気になる記事を見つけても、毎日の細々とした事柄に取り紛れブログを更新するのが間遠になります。実は先週の17日金曜日の日経新聞夕刊の記事が気になりました。「シネマ万華鏡」というコラムに社会学者の宮台氏が「ベネデッタ」とい映画を紹介していました。17世紀の修道女で同性愛で告発されたベネデッタ・カルリーニの裁判記録に基づいて「ロボコップ」のポール・バーホーヘンが映画化したものとのこと。
もちろん、このコラムは映画ベネデッタを通して、ベネデッタに象徴されるような同性婚などで社会は何も変わらない、本来人に備わったものを本来のものと認識するだけだ・・・という議論だろうと思います。
そういう意味で、宮台氏の指摘事項の本筋とは少し離れますが、このコラムの文中で気になる言葉がありましたので、あえて、引用させていただきます。『・・・所詮は維新政府の統治の都合によるこしらえものを日本の伝統だと思い込み・・・』
私の懸念とは・・・・・・・。
「保守派」に限らず現在の多くの日本人が、『明治維新』『維新の志士』などを称賛していること。それは、当時の拵え物としての「皇国史観」「脱亜入欧」とそれに伴った「帝国主義」を引き継ぐことになるという自覚もないままであること。
それらを信奉して行動した当時の些か単純な若者や、それらの行動を利用した薩長を中心とした明治政府によって主導された「日本の伝統」とは、基本的に作り物であり、全く日本の伝統ではないこと。
江戸時代や江戸幕府の一部に芽生えた合理主義を、武家政権の封建的・身分制的政治体制と一緒くたにして潰してしまったのではないか、などです。
人が異なれば意見も異なります。私に賛同する人はそんなに多くいないはずです。しかし、日本の本当の伝統とは、ひいては民主主義の本質とは「多数決」ではなく「あらゆる意味で自分とは異なる価値観や意見を持つ少数者を切り捨てない」ことにあるのだと思っています。