


 ← ブログランキングに登録しています。よろしければ、左の緑色部をクリックしてください
← ブログランキングに登録しています。よろしければ、左の緑色部をクリックしてください暮らしは都市化、洋風化、工業製品化
衰える手仕事、商売がある(注1)
思うに絶滅危惧職商
その一つに和傘
雨中の和傘を見ない
和傘専門店、傘専門店は少ない
されど京都の街にはある、きっとある
その思いを抱き歩く
あった! 和傘屋さん(上の写真)
多彩な傘かかる
思いを裏切らない京都の街
注1 桶屋さん:弊ブログ2014年11月24日
執筆・撮影者:有馬洋太郎
撮影日:2018年03月29日
撮影地:上記



 ← ブログランキングに登録しています。よろしければ、左の緑色部をクリックしてください
← ブログランキングに登録しています。よろしければ、左の緑色部をクリックしてください
 写真2
写真2  写真3
写真3









 写真1
写真1 写真2
写真2 写真3
写真3 写真4
写真4 写真5
写真5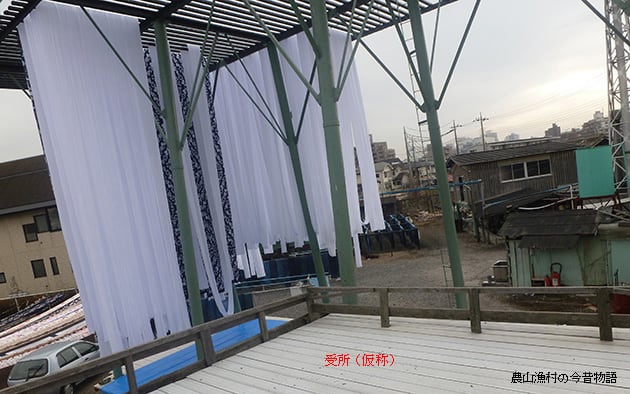 写真6
写真6