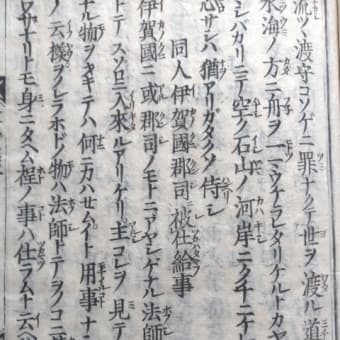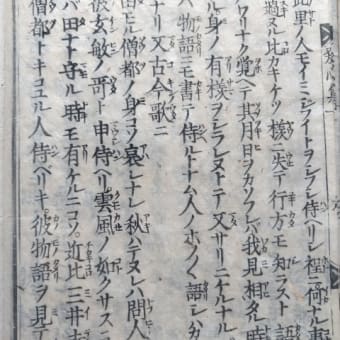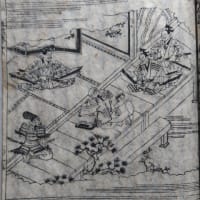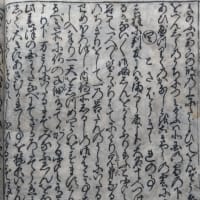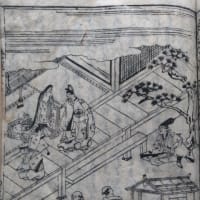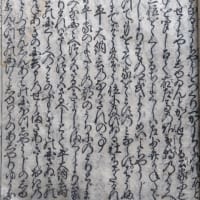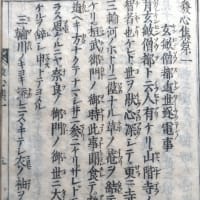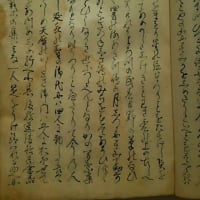平家物語 巻第一
十 しゝの谷の事
是によつて、主上御げんぶくの御さだめ、其日はのびさせ
給ひて、同じき廿五日、院の殿上にてぞ御げんぶくの
御定は有ける。摂政殿さてもわたらせ給ふべきならねば、

同じき十二月九日の日、かねてせんじをかうぶらせ給ひ
て、同じき十四日太政大臣にあがらせ給ふ。やがて同じき
十七日、よろこび申の有しか共、世の中は猶、にが/\しうぞ
みえし。去程に今年もくれぬ。かおうも三年に成にけ
り。正月五日の日、主上御げんぶく有て、同じき十三日、朝
きんの行かう有けり。法王女院まちうけ参らさせ給ひ
て、うゐかうふりの御よそほひ、いかばかりらうたく思し
召れけん。入道相国の御むすめ、女御に参らせ給ふ。御とし
十五さい、法王御猶子のぎなり。妙音院殿、其比はいま
だ内大臣の左大将にてまし/\けるが、大将をじし
申させ給ふ事有けり。ときに徳大寺の大納言じつてい
の卿、其任にあひあたり給ふ。又花山院の中納言兼
まさの卿も所まう有。その外故中のみかどの藤中納
言家成の卿の三男、新大納言なりちかの卿もひらに
申さる。此大納言は院の御きしよくよかりければ、様々

いのりを始らる。まづ八はたに百人の僧をこめて、しんどくの
大はんにやを七日よませられたりけるさい中に、甲良の
大明神の御前なる橘の木へ、男山のかたより、山ばと三つ
とび來つて、くひあひてそしにゝける。
鳩は八幡大ほさつの
㐧一の使者也。宮寺にかゝるふしぎなしとて、ときのけん
けうきやうせい法印此よし大りへそうもんしたりけれ
ば、是たゞ事にあらず御うら有べしとて、神ぎくわんにし
て御うら有。おもき御つつしみとうらなひ申す。但これは
君の御つゝしみにはあらず、臣下の御つゝしみとぞ申ける。
それに大納言おそれもいたされず、ひるは人めのしげけれ
ば、よな/\ほかうにて、中のみかどからす丸の宿所より
かもの上の社へ、七夜つゞけて参られけり。七夜にまんずる
夜、宿所に下かうして、くるしさに少まどろみたりける
夢に、かもの上の社へ、参りたると思しくて、御ほうでんの
御戸をしひらき、ゆゝしうけだかげなる御こゑにて

桜花かもの川風うらむなよ散をばえこそとゞめさりけれ
大納言、是に猶おそれもいたされず、かもの上の社に、御宝
殿の御うしろなる、杉のほらにだんを立、あるひじりを
こめて、たきにの法を百日行はせられけるに、ある時俄に
空かきくもり、いかづちおびたゝしうなつて、かの大杉に落
かゝり、らいくわもへあがつて、宮中すでにあやうく見え
けるを、宮人共はしりあつまりて、これをうち消。さて
かの下法行ひけるひじりをおひ出さんとす。我たうしや
に百日さんろうの心ざし有てけふは七十五日になる。
まつたく出まじとてはたらかず。此由を社家より大内
へそうもん申たりけれは、たゞ法にまかせよとせんじを
下さる。其時神人しらづえをもつてかのひしりがう
なじをしらけて、一条の大路より、南へおつこしてけり。
神はひれいをうけずとこそ申に、此大納言、ひぶんの大将
をいのり申されければにや。かゝるふしぎも出來にけり

其比の叙位ぢもくと申は、院内の御はからひにもあら
ず、摂政関白の御せいばいにもおよばず、たゞ一向平家のま
まにて有ければ、徳大寺花山の院もなり給はず、入道相国
のちやく男、小松殿其時はいまだ大納言右大将にてま
し/\けるが、左にうつりて次男むねもり、中納言にておは
せしが、すはいのじやうらふをてうおつして、右にくはゝら
れけるこそ、申はかりもなかりしか。中にも徳大寺殿は、
一の大納言にて、花族ゑいゆう、才覚いうちやう、けちやく
にてまし/\けるが、平家の次男むねもりの卿に、かゝい
こへられ給ひぬるこそいこんのしだいなれ。定て御出家など
もや有んずらんと、人〃さゝやきあはれけれ共、徳大寺殿は
しばらく世のならんやうをみんとて、大納言をじゝて籠
居とぞ聞えし。新大納言なりちかの卿の、宣ひけるは、徳
大寺花山院に、こえられたらんはいかにせん。平家の次男宗
もりの卿に、かゝいこえられぬるこそ、いこんのしだいなれ。いかにも

して平家をほろぼし、本まうをとげんと、宣ひける社
おそろしけれ。父の卿は此よはひでは、わづか中納言まで
こそいたられしが、その末子にて、位正二位、官大納言に
へあがつて、大国あまた給はつて、子そく所じう、てう
をんにほこれり。何のふそく有てかゝる心つかれけん、
偏に天まのしよゐとぞみえし。平治にもゑちごの中
将とて、信頼の卿に同心のあひだ、其時すでにちうせ
らるべかりしを、小松殿のやう/\に申して、くびをつぎ給へ
り。然るに其をんを忘れて、外人もなき所に、兵ぐをと
とのへ、軍兵をかたらひおき、朝夕はたゞ軍合戦のいとな
みの外は、他事なしとぞみえたりける。東山しゝの谷と
云所は、うしろ三井寺につゞいて、ゆゝしき城郭にてぞ
有ける。それに俊寛僧都の山荘有。かれにつねは寄合
/\、平家ほろぼすべきはかり事をぞめぐらしける。
ある夜法皇も御かうなる。故少納言入道、信西のし

そく、じやうけん法印も御供仕らる。其よのしゆえんに
此よしを仰合られたりければ、法印あなあさまし人あ
またうけ給はり候ぬ。只今もれ聞えて、天下の御大事に
および候なんずと申されければ、大納言けしきかはつて、
さつと立れけるが、御前に立られたりけるへいじを狩衣
の袖にかけて、引たをされたりけるを、法皇ゑいらん有て、
あれはいかにと仰ければ、大納言立帰て、平氏たふれ候ぬと
申されける。法皇もゑつぼに入せおはしまし、もの共ま
いつて、さるがく仕れと仰ければ、平判官やすよりつと
参つて、あゝあまりに平氏のおほう候に、もてゑひて
候と申す。俊寛僧都さてそれをば、いかが仕るべきやらん。西
光法しただくびをとるにはしかじとて、へいじのくびを
取てぞ入にける。法印あまりのあさましさに、つや/\
物も申されず。かへす/\もおそろしかりし事共也。さて
よりきの輩たれ/\ぞ。あふみの中将入道れんじやう


俗名なりまさ、法性寺の執行俊寛僧都、山城の守基
もとかぬ、しきふの大輔まさつな、平判官やすより、宗判官
のぶふさ、新判官すけゆき、ぶしには多田の蔵人行つな、
を始として、北面の者共おほくよりきしてけり