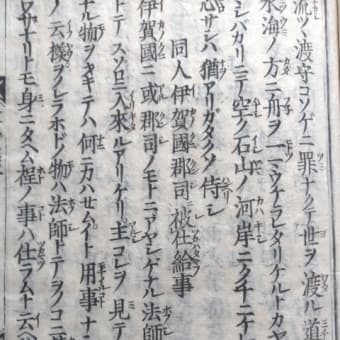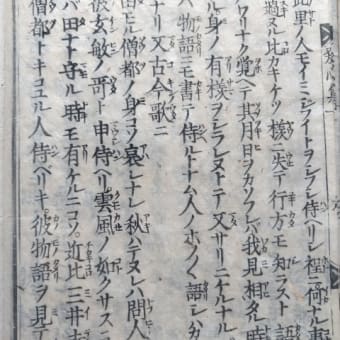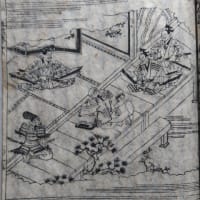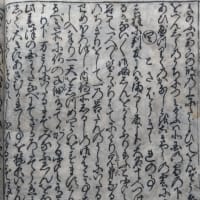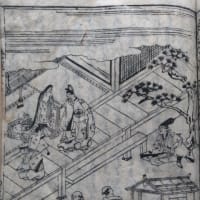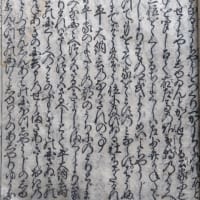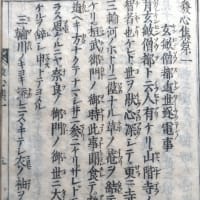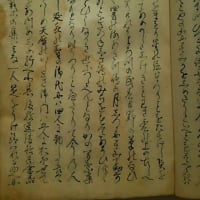平家物語 巻第一
九 てんかののりあひ
去程に、かおう元年七月十六日、一院御出家有。御出家
の後も、ばんきのまつり事をしろしめされければ、院内
わくかたなし。院中にちかう召つかはれける。公卿殿上人、
上下のほくめんにいたるまで、官位ほうろく、みな身
にあまるばかり也。され共人の心のならひにて、猶あきた
らで、あつぱれ其人のうせたらば、其国はあきなん。其人の
ほろびたらば、其官にはなりなんなど、うとからぬどちは

よりあひ/\さゝやきけり。一院も内〃、仰なりけるは、昔
より代〃のてうてきを平げたる者おほしといへ共、
いまだかやうの事はなし。さだ盛ひで郷が将門を討
頼義がさだたうむねたうをほろぼし、義家がたけ
ひら家平をせめたりしにも、けんじやう行はれし事、
わづかじゆりやうには過ざりき。今清盛が、かく心の
まゝにふるまふ事こそ、しかるべからね。これも世すへに
なりて、王法のつきぬるゆへ也とは、仰なりけれ共、つゐで
なければ御いましめもなし。平家も又べつして、朝
家をうらみ奉らるゝ事もなかりしに、世の乱そめ
けるこんぼんは、去じかおう二年、十月十六日に、小松殿
の次男、新三位の中将すけ盛、其時はいまだ、越前の
守とて、生年十三になられけるが、雪ははたれにふつ
たりけり。かれのゝけしき、まことに面白かりければ、わかき侍
共、卅きばかりめしぐして、れんだいの雪や紫野、うこん

のはゝにうち出て鷹共あまたすへさせ、鶉ひばりを
追立/\ひねもすにかりくらし、はくぼにおよびて六は
らへぞ帰られけれ。其時の御せつろくは、松殿にてぞま
し/\ける。東洞院御所より、御さんだい有けり。有はう
門より入御有べきにて東洞院を南へ、大炊のみかどを
西へ入御なるに、すけもり朝臣、大炊のみかどゐのくまにて
殿下の出御にはなつきに参会御供の人共何ものぞ
らうぜきなり。御出なるに乗物よりおり候へ/\といらで
けれ共、あまりにほこりいさみ、世をよともせざりけるうへ、
めしぐしたる侍共も、みな二十よりうちの、若者共なれ
ば、礼儀こつほう、わきまへたる者一人もなし。殿下の御
出共いはず、一切下馬の礼儀にもおよばず、只かけやぶつ
てとをらんとする間、くらさはくらし、つや/\太政入道
のまご共しらず又少〃はしつたれ共、そらしらずして、
すけもり朝臣を始として、侍共みな馬より取て引きお


ろし、頗ちじよくにおよびけり。すけもり朝臣、はう/\
六はらへ帰りおはして、おほぢの相国ぜんもんに、此由訴
申されければ、入道大きにいかつて、たとひ殿下なりとも、
浄海があたりをば、はゞかり給ふべきに、さうなうあのお
さなき者に、ちじよくをあたへられけるこそ、いこんのしだ
いなれ。かゝる事よりして、人にはあざむかるゝぞ。此事殿
下に思ひしらせ奉らでは、えこそ有まじけれ。いかにもし
てうらみ奉らばやとの給へば、重盛の卿申されけるは、是は
すこしもくるしう候まじ。頼政みつもとなど申す源氏共
にあざけられても候はんは、まことに一門のちじよくにて
も候べし。重盛が子供とて候はんずる者が、殿の御出に
参あふて、乗物よりおり候はぬ事こそ、かへす/\もびろ
うに候へとて、其時事にあふたる侍共、みなめしよせて、自
今以後なんぢら、よく/\心うべし。あやまつて殿下へぶれ
いのよしを、申さばやと思へとてこそ帰されけれ。其後入道
小松殿には、かう共の給ひもあはせずして、かたゐなかの侍
の、きはめてこはらかなるが、入道の仰より外、世に又おそろ
しき事なしと思ふ者共、なんば世のおを始として、つがふ
六十よ人召よせて、きたる廿一日、殿下御出有あべかん也。いづく
にても待うけ奉り、せんくみずいじん共が、もとどり切て
すけもりがはぢすゝげとこその給ひけれ。兵共畏承て
まかりいづ。殿下是をば夢にもしろし召れず、主上明年
御げんぶく御かくわん、はいくわんの御定の為に、しばらく御
ちよくろに有べきにて、つねの御出よりは、引つくろはせ給
て今度は待賢門より入御有べきにて、中のみかどを西へ
御出なるに、ゐのくまほりかはのへんにて、六はらの兵共、ひた
甲三百よき、待うけ奉り、殿下を中に取こめ参らせて
ぜんごより一度に、ときをどつとぞつくりけるせんぐみず
いしん共が、けふをはれとしやうぞくしたるを、あそこにお
つかけ、こゝにおつつめ、さん/\にりようりやくし、いち/\

にみなもとどりをきる。ずいしん十人のうち、右の府生た
けもとがもとどりをもきられてげり。其中に藤蔵人
の大夫たかのりがもとゞりをきるとて、これはなんぢがも
とゞりと思ふべからず、しうのもとゞりと思ふべしと、いひ
ふくめてぞきつてける。其後は御車のうちへも、弓のはづ
つき入などして、すだれかなぐりおとし、御うしのむなが
ひきりはなち、かくさん/\にしちらして、よろこびのと
きをつくり、六はらへ帰り参りたれば、入道神妙なりとそ
の給ひける。され共御車そひには、いなばのさいづかひ、鳥
羽の国久丸といふおのこ、下らふなれ共、さか/\敷もの
にて、御車をしつらひ、乗奉て、中のみかどの御所へ
くわん御なし奉る。そくたいの御袖にて、御涙をおさへさせ
給ひつゝ、くわん御のぎしきのあさましさ、申もなか/\
愚なり。太しよくくわん、たんかいこうの御事は、あげて申
におよばず、忠仁公、せうせんこうより以來、摂政関白の

かゝる御めにあはせ給ふ事、いまだうけ給はり及ばず。これこそ
平家の悪行の始なれ。小松殿此よしを聞き給ひて、おほ
きにをそれさわがれけり。其時行向ふたる侍共、みなかんだう
せらる。たとひ入道いかなるふしぎを下知し給ふといふ共、など
重盛に夢ばかりしらせざりけるぞ。およそはすけもり
きくわい也。せんだんは二葉よりかうばしとこそみえたれ。
すで十二三にならんする者が、今は礼義をぞんぢし
てこそ、ふるまふべきに、かやうのびろうをげんじて、入道
のあくみやうをたつ。ふけうのいたり、汝ひとりに有けり
とて、しばらくいせの国へおひくださる。されば、此大将をば、
君も臣も御かんありけるとぞきこへし。