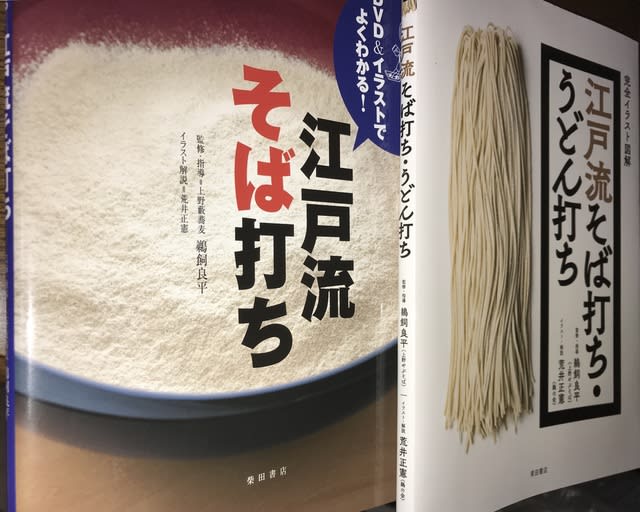更科そばを完成させるためには、更科そばを知ることが不可欠と考え、更科発祥の老舗店に行ってきました。
発祥といえる三つのお店 ①「麻布永坂 更科本店」 ②「永坂更科 布屋太兵衛」 ③「総本家 更科堀井」は、いずれも麻布十番駅から徒歩圏にあります。今回訪れたのは②と③の二店舗です。
最初に訪れたのは、「総本家 更科堀井」です。



お目当ての更科そばが出てきました。


切り幅が見事に揃っているきれいなおそばです。一口啜るとそば特有の香りは強くないものの、ほんのり旨味があり風味豊かで喉越しの良いおそばでした。
店員の方にいろいろとお話を伺ったところ、つなぎの小麦粉を二割配合した二八そばであることが分かりました。なるほど喉越しの良さはそこから来ているのかと納得しました。また、機械打ち(切り作業も含め)であることも分かりました。
更科堀井を後にして、次に向かったのは「永坂更科 布屋太兵衛」です。


ここでも更科そばを注文。

なんと、もり汁(つゆ)が二種類出てきました。店員の方からこのおそばには甘い方をお薦めしていると説明を受けました。せっかくなので二種類の汁で食べ比べをしたかったので、蕎麦猪口をもう一つお願いしました。

ここのおそばは、食感が最初のお店で食べたものと異なり、表面がつるっとしていないと言うか、喉越しよりもおそばの存在感(食感)を楽しめる感じでした。
もり汁に関してはから汁の方が良かったです。甘い方がお薦めと言っていた店員さんと再度話をする機会があったので、私の感想をお伝えしたところ、その店員さんも個人的にはから汁が好みだとか。ここのおそばは十割(すなわち更科粉100%)で機械打ちであることも教えていただきました。
今回、二種類のおそばをいただきましたが、それぞれ個性があり、いずれも美味しいおそばでした。この体験を生かして、いよいよ本格的に試作段階に入っていきたいと思います。