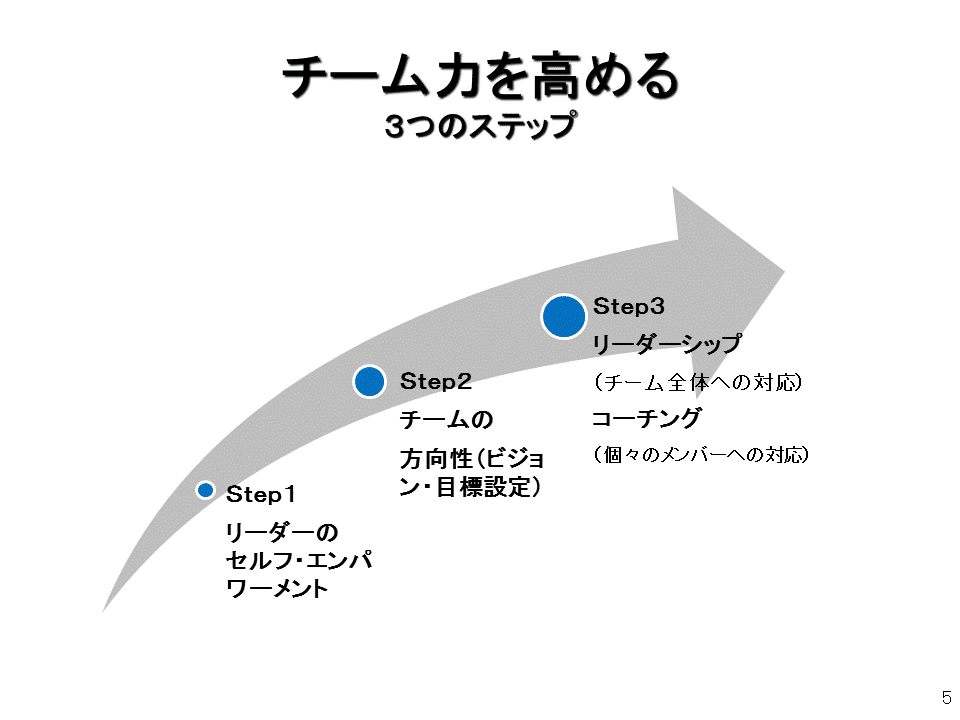
エンパワーメント経営の背景
1993年ASTD(American Society for Training & Development)の大会に初めて参加したときに出会ったキーワードがこの「Empower(エンパワー)」であった。各セミナーのタイトルや展示会場の書物に、このキーワードが多く使われていた。
「Power」ということばは当然知っていたが「Empower」ということばは初めてなので、関係者にその意味を確かめると、多くの人からエンパワーとは「権限委譲」や「コントロールの反対概念」であると説明を受けた。しかし、それだけでは言いあらわせない深い意味や、背景があるように感じ取られた。
マネジメントで使われているエンパワーメントも単なる「権限委譲」ではなく、前述したいくつかの定義にあった基本的理念が背景にあるようだ。
1998年9月号のハーバード・ビジネス誌(ダイヤモンド社)の「エンパワーメント経営」の中で高橋俊介氏はアメリカでエンパワーメント経営が生まれた背景として次のように説明している。
1.先進企業の多くで、従来のピラミッド型組織の管理から脱却し、自律的な組織運営に向けた抜本的な改革が起こりつつある。
2.人材に対する考え方が労働力(Labor)から株主利益を生み出していくための経営資源である人的資源(Human Resource)へ、そして人材そのものが価値を生み出すヒューマン・キャピタル(人的資本)へと変遷している。
3.市場が成熟しているためモノそのものより顧客にとっての付加価値を高めることで顧客満足を高める。
4.規制緩和の進展、デジタル化や情報ネットワークに象徴されるように技術環境も一変した。
いつどこから新しいタイプのコンペティターが出現するかわからない時代になっている。
アメリカのみならず日本でも同じ様な状況になっている。
当時日本においては海外や先進企業のまねを行ない、そして企業の都合で売りたいものを顧客に押しつけるようなプロダクトアウト型であったり、マーケット技術を駆使して市場に適応した商品を提供していくマーケットインが多くみられた。しかし今日では顧客でさえ何が本当に欲しいのか、必要なのかがはっきりとわからなくなってきている。
顧客に最も近い現場が自発的に顧客と対話し、その対話を通じて高い付加価値のものを模索するといったやり方でしか対応できなくなってきているのが日本の企業がおかれている現状であろう。
このような状況下においては、第一線の人材が自律的に環境変化に対応し、創造的に付加価値を生み出していかなければ競争に勝ち残れなくなっている。
エンパワーメント経営の特徴
それでは、エンパワーメント経営と従来の経営ではどこが違うのだろうか?図表1に基づき解説を試みた。
エンパワーメント経営の特徴を説明すると次のようになる。
1.フラット型組織
一人ひとりの職務が固定されたり、機能別縦割りの特徴をもった官僚型ピラミッド組織に対して組織の階層を少なくしたフラット・ネットワーク型組織になっている。
2.権限委譲
トップダウンのコントロール型マネジメントに対して、権限を委譲し、目標達成の方法など実行については、社員の主体性(意志)に任せるマネジメント。まる投げではなく責任は委譲者にもある。
3.「What」のマネジメント
マネジメントは本来「What(何をするか)」と「How(どのような方法で行なうのか)」といった2つのサイクルからなりたっている。
「What」についてはトップマネジメントや経営企画室が何をするかを決め、これを中間管理職が「How」に分解し末端の社員が「Do」をすることが多かった。すなわち一般社員は効率性をベースとした「How」のサイクルのマネジメントが重要視された。
しかし組織がフラットになることによって末端の社員が「How」のみならず「What」のマネジメントのサイクルの行使も求められている。
4.内因的コミットメント
コミットメントとは自分への拘束のことである。クリス・アージリスは「コミットメントには外因的なものと内因的な2つがある。エンパワーメントと密接な関係を持ち、その成否もカギを握るのは内因的コミットメントの方である。社員が自らの人生に積極的に取り組み責任を全うしてもらいたいと望むなら内因的コミットメントを促すような環境を整えていかなければならない。内因的コミットメントは本人のやる気、自発性に基づく取り組みのことである」と指摘している。ちなみに外因的コミットメントとは目標、職務遂行、仕事内容など多くの項目が他者によって決定され、そして拘束されることである。(前述「エンパワーメント経営」)
5.自律型チーム
上位部門や上位者の単なる下請的なワーキングチームである従属的チームに対して、自律型チームは自らのミッション(存在意義)やビジョン、チームメンバーが行動するときの価値観を持っている。そして激しく様変わりする競争環境の中で、組織やチームがどのような状況であるかといった情報がいつも共有されている。
6.主体的メンバー
上位者から指示されたことのみをこなしたり没個的な隷属的メンバーではなく、自らの人生に積極的に取り組み責任を全うする主体的なメンバーが求められる。自らの人生哲学に基づいた指針やビジョンを持ち、目標指向行動ができ、自己選択と自己責任で行動できるメンバーが必要になってくる。そして何でもこなすことができるジェネラリストからより専門的な知識や技能を持ったスペシャリストが求められている。これは営業やマネジャーも例外ではない。
7.コーチング
旧来のOJT(On the Job Training)で知識・技能・態度をトレーニングし、仕事の習熟度を高める目的だけではなく、メンバーの主体性を高め組織やチームの成熟者になるようなコーチングが必要になってくる。
コーチングもメンバーの個性に合わせ、メンバーの持つ意欲や能力を最大限引き出すアウトプット型の支援方法やスキルが必要になっている。
図表 1 エンパワーメント経営の特徴
|
|
従来型経営 |
エンパワーメント経営 |
|
組 織 |
官僚型組織 ピラミッド型 |
フラット型組織 ネットワーク・ウエッブ型 |
|
組織運営 人材マネジメント |
コントロール 指揮命令 |
エンパワーメント 権限委譲 |
|
マネジメント・ サイクル |
HOW
|
WHAT
|
|
コミットメント |
外因的 |
内因的 |
|
チーム(部門) |
従属型チーム |
自律型チーム |
|
個人(メンバー) |
隷属的 ジェネラリスト |
主体的 スペシャリスト |
|
メンバー育成 |
トレーニング |
コーチング |















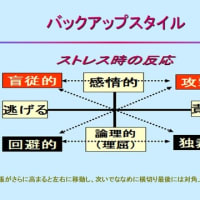











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます