例えばこの恰好が今から行く場所にふさわしいのかどうか判断がつきかねる時。
そんな経験は誰にでもあるはずだ。
相談してみると
「ああー大丈夫、おるおる、そんな人」
と言われ、ではまあ…ということで良しとする。これも誰にでもある経験ではないだろうか。
ひで氏です。
今日、たまたまこのやり取りがあった。自分ではなく、目の前で聞いたのだ。自分がこのやり取りをするときは、なんとなくもやもやしながらも「そうかぁ」と終わっていたのだが、人のやり取りを目の当たりにしたことで、いつも自分が感じていたもやもや感の正体がわかったような気がしたのだ。
これは良く考えたら思い切りポイントがすり替えられたやり取りではないのか。
聞き手としては「今から行くところに果たしてこの恰好はふさわしいのか」が分からないわけであって、言外に「一般的な常識と照らし合わせてどうだろうか」ということを聞いている。更に言うと自分を良く知る人に聞いている時点で「自分という人間としてどうだろうか」ということも同時に聞いているわけである。
対してこの「そんな人いる」という答えは、「そういう格好で行く人は世の中に存在しうる」という宣言をしているだけで、そのレベルで言うならどんな時も「居ないということは無い」事になってしまうだろう。つまり葬式に全身ネオンカラーのスーツで行く人も「そんな人いる」だし、転職の面接に作務衣で行く人も世の中見渡せば「そんな人いる」という事になってしまう。
そうか、「自分がこの恰好をすることがどうか」を聞いているのであって「そういう人も世の中にはいるから大丈夫」などと言われても全くホッとしないのはそういうことか!
と妙に納得したわけである。
さらに別の弊害もある。
身近な例で想像してみてほしい。
「明日の会社の飲み会は定年退職される部長の送別会。案内には特に服装については触れられていないし、部長はとても気さくな人だ」というようなケースでスーツを着るべきか、ノーネクタイのカジュアルでいいか、というような非常に微妙な状況で最終的にカジュアルを選んだ時。念のため近しい人間に相談したとしよう。
ここで返される「いるいる、そんな人」という言葉はむしろ「完全におかしいとは思うし異常だとは思うけど世の中にはそういう人も必ずいるはずだからマァいいんじゃないか」と、もはや暗に批判されているのではないかとさえ感じるわけである。
そうなると聞いた側の不安は払拭されるどころか益々増幅し、また判断に迷うことになる。
さすれば聞かれた側は「まだ迷うならなぜ聞いたのだ」ということになり、
互いになんとも後味の悪いことになっているのでは…
そう考えた私ひで氏。
ではどうすればこのもやもや感が解決する気持ちいいやり取りができるのか。
そこまで考えてようやく何か社会に貢献できるのでは…そう思って出た答えは、
「いいと思う!」
と答えることだ。
全て肯定することで、聞いた側は一旦自分で出した答えの最後の一押しをもらって安心するし、
聞かれた側も元々「そんな人いる」と答えそうになっている時点で相手の意思を尊重したい気持ちがあるわけだから、余計な波風を立たせずに済む。
だからみんな、もし友人が作務衣で転職の面接に行こうとしていても自信を持ってこう言ってあげよう。
「いいと思う!」
と。
そんな経験は誰にでもあるはずだ。
相談してみると
「ああー大丈夫、おるおる、そんな人」
と言われ、ではまあ…ということで良しとする。これも誰にでもある経験ではないだろうか。
ひで氏です。
今日、たまたまこのやり取りがあった。自分ではなく、目の前で聞いたのだ。自分がこのやり取りをするときは、なんとなくもやもやしながらも「そうかぁ」と終わっていたのだが、人のやり取りを目の当たりにしたことで、いつも自分が感じていたもやもや感の正体がわかったような気がしたのだ。
これは良く考えたら思い切りポイントがすり替えられたやり取りではないのか。
聞き手としては「今から行くところに果たしてこの恰好はふさわしいのか」が分からないわけであって、言外に「一般的な常識と照らし合わせてどうだろうか」ということを聞いている。更に言うと自分を良く知る人に聞いている時点で「自分という人間としてどうだろうか」ということも同時に聞いているわけである。
対してこの「そんな人いる」という答えは、「そういう格好で行く人は世の中に存在しうる」という宣言をしているだけで、そのレベルで言うならどんな時も「居ないということは無い」事になってしまうだろう。つまり葬式に全身ネオンカラーのスーツで行く人も「そんな人いる」だし、転職の面接に作務衣で行く人も世の中見渡せば「そんな人いる」という事になってしまう。
そうか、「自分がこの恰好をすることがどうか」を聞いているのであって「そういう人も世の中にはいるから大丈夫」などと言われても全くホッとしないのはそういうことか!
と妙に納得したわけである。
さらに別の弊害もある。
身近な例で想像してみてほしい。
「明日の会社の飲み会は定年退職される部長の送別会。案内には特に服装については触れられていないし、部長はとても気さくな人だ」というようなケースでスーツを着るべきか、ノーネクタイのカジュアルでいいか、というような非常に微妙な状況で最終的にカジュアルを選んだ時。念のため近しい人間に相談したとしよう。
ここで返される「いるいる、そんな人」という言葉はむしろ「完全におかしいとは思うし異常だとは思うけど世の中にはそういう人も必ずいるはずだからマァいいんじゃないか」と、もはや暗に批判されているのではないかとさえ感じるわけである。
そうなると聞いた側の不安は払拭されるどころか益々増幅し、また判断に迷うことになる。
さすれば聞かれた側は「まだ迷うならなぜ聞いたのだ」ということになり、
互いになんとも後味の悪いことになっているのでは…
そう考えた私ひで氏。
ではどうすればこのもやもや感が解決する気持ちいいやり取りができるのか。
そこまで考えてようやく何か社会に貢献できるのでは…そう思って出た答えは、
「いいと思う!」
と答えることだ。
全て肯定することで、聞いた側は一旦自分で出した答えの最後の一押しをもらって安心するし、
聞かれた側も元々「そんな人いる」と答えそうになっている時点で相手の意思を尊重したい気持ちがあるわけだから、余計な波風を立たせずに済む。
だからみんな、もし友人が作務衣で転職の面接に行こうとしていても自信を持ってこう言ってあげよう。
「いいと思う!」
と。












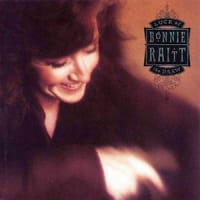


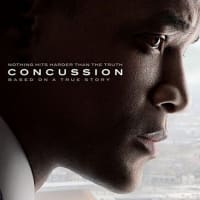
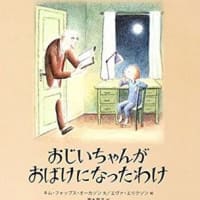


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます