
ギターにはビンテージギター市場というものがあり、世界には熱心なビンテージギターコレクターがいる。
楽器としての価値はもちろん、投資対象としての価値を見出して集めてる人もいるだろう。
ビンテージという言葉はある意味「称号」のような感覚すら感じる。
我が家にも、ビンテージギターと呼んでさしつかえないギターはある。
それは、ライブには持っていくことは、ほとんどない。
だが、レコーディングなどの機会にはもってこいだ。
サウンド以上に、付加価値がそのギターの値段をつりあげている。
そうなると、うかつに手を加えられなくなる。歴史的価値・・といった側面が高いギターであればあるほど。
噂や伝説のビンテージギターを購入した時の喜びや興奮は、マニアなら多くの人が感じるだろう。
その一方で、ビンテージギターに対して、アンチな立場をとる人もいる。
楽器は弾いてなんぼで、付加価値で値段が膨らんでしまって、傷つけるのが怖くてうかつに弾けなくなるぐらいなら、そんなギターいらない・・・という考えの人も多くいて、私もそういう人の気持ちはよくわかる。
どちらかというと、私はそっちの考え方に近いのだが、ただ、ビンテージギターに対するあこがれもまたあるのは正直なところだ。
知り合いが高価なビンテージギターを持ってたら、やはり弾かせてもらいたいと思うし、お金の問題がなければ、本当に憧れてるギターなら欲しいと思うから。
ただ・・・ビンテージギターというものは、買う時はよくても、そのあとの維持・管理が大変なのだ。
ビンテージギターを買うということは、それが価値のあるものであればあるほど、その維持・管理への責任を背負うことなのだ。
なぜなら、そういうギターは、その持ち主が亡くなっても、次のオーナーに引き継がれていかねばならない楽器だからだ。
なので、「買う」というより、「預かる」といった感覚が正しいかもしれない。
歴史的価値のあるビンテージギターの維持・管理を光栄と捉えるか、苦痛と捉えるか・・・で、分かれるのだろう。
私の持ってるビンテージギターは、これまでに2本ほどリペアに出している。
経年変化によるもので、テイルピースを交換したり、ピックガードを交換したり。
本音としては、なるべくパーツは交換したくない。できればオリジナルのままにしておきたい。
だが、交換しないと、弾けない・・・・そういう状態になってしまうこともある。
交換しないと、それこそただの「骨董品」として眺めるしかない・・・・そうなってしまったら、もうそれは「楽器」ではない。
やはり、楽器は弾けてなんぼ。
弾ける状態で維持していきたい。
今、リペアに出す時期が・・・決断をくだすべき時期が近付いているビンテージギターが我が家にあり、少し複雑な気分でいる。
そう・・・今回考えてるギターもまた、マーチンD-76の時と同様に、ピックガードが持ち上がってきてるのだ。
今はまだオリジナルのままでも弾けるけど、いずれ・・このままピックガードが持ち上がっていったら弾けなくなる時期はくるだろう。
とりあえず、新しいピックガードに交換しても、取り外したオリジナルのピックガードもちゃんとケースに入れて保存はしておこうとは思う。
大地震が来たり、火事にまきこまれた時、どれか1本ギターを持って逃げる時は、私は迷わずこのギターを選ぶと思う。
だが、一刻を争うような咄嗟の瞬間や、余裕が全くない時に、持ち出せなかった場合のことを考えると、・・・・怖い。
特に今回の東日本大震災の惨状を見るにつけ、そう思う。
津波が迫ってきて、逃げる場合に、そんな余裕があるだろうか。
ギターはかさばるし、ハードケースに入れてると、けっこう重い。
全速力で駆け足で逃げる場合、走る邪魔にはなるだろう。
そう考えると、不安になる。
生命の危機に、ギターを持ちだす余裕などなくてもおかしくない。
そうなると、瓦礫の中に、粉々になった高価なギターの破片が混ざって、ゴミとして処理される可能性も・・ある。
しかも、人知れず・・。
今回の大震災で特に被害が大きかったエリアにお住まいの方の中には、ビンテージギターを持ってた人もいるかもしれない。
もちろん命が一番大事だが、ビンテージギターを持ってる人にとっては、そのギターも相当大事なはず。
そういう人は、どうしたのだろうか。
その方の命と共に、そのギターも無事であってくれることを祈るばかりだ。
つくづく、今回の震災が恨めしい。










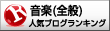

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます