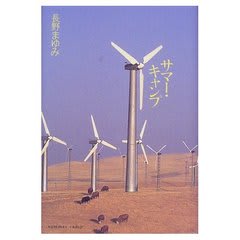
両親の愛情不足を理由に強がる主人公 温(ハル)、浅慮に対して容赦なく断じる周囲の大人、実は愛情があっての台詞だが主人公の思い込み・幼さ故に気付かない、という構図は、『白昼堂々』シリーズに良く似ている。
『超少年』では生物相と植物相のゆらぎを描いていたが、ここでは染色体による性表現と意識による性自認のズレを描きつつ、ABITAS-C1という設定を作り他者の認識と外界とのつながりの希薄で不確かさを描いている。
そういうアプローチを読むのは楽しめるのだが、前者のような傾向や文庫本のあとがきで思い切り言ってしまう著者の主張は、自己嫌悪・自己否定からくる人間憎悪に根ざしているように見えて、作品に意図的ではなく表れてしまうならともかく、自ら同じ本の後書きに入れるべきではないと思う。
と言っても嫌いな作品ではない。
そのうちまた手に取って読んでもいいと思う1冊。
単行本:2000年4月
文庫本:2003年5月
「(重要なモチーフ)入れすぎて混乱をきたしているんですけれど。…クローンなんです。でもクローンをやるのに記憶がはずせなくなって、記憶をやると泥沼に入るのはわかっていたけれどもそらすわけにはいかなかった。途中から結局<超男性>のYYの問題が出てきて、それを書きたいんだなって思ったときにはもう後半(笑)。」
(別冊文藝より 著者談)
「…物語の細部にちりばめられた謎が謎を呼び、生と性が人工的な操作によって複雑な共犯関係を結ぶ世界が構築されている。…血脈、家系を守るための人工的な人間の再生産は、染色体のレベルで異変をきたし、それが外見と内面のジェンダー認識のギャップに繋がり、さらに家族という制度が培ってきた既成概念の変更を迫る結果となる。残酷なかたちで自分の本当の姿を知る温にとっての<サマー・キャンプ>を描いた秀作。」
(別冊文藝より 大串尚代評)
以前、この本の感想をブログで書いた気がするので、探して、読み返してみた。
コレ。
2センテンス目なんて、だいぶ言っていることが違う…、なんて自分でもどう思っていたのかよく分かりませんが、苦笑、うん、風景は綺麗だとは今も思いました。
そしてつらつら考えたことを確かめるべく、最初から読み直してここまで至りました。
なかなかよくやったと自分を褒める。
内容とかでなく、継続して続けている事に対して、ネ。
「…話法は云い換えや反語ばかりだから、どうとでも解釈できるんだけど、…」
この「どうとでも解釈できる」のが長野まゆみの愉しさであると思います。
文庫のオビなんて
「愛情など、断じて求めない、はずだった。」ですから。
『超少年』では生物相と植物相のゆらぎを描いていたが、ここでは染色体による性表現と意識による性自認のズレを描きつつ、ABITAS-C1という設定を作り他者の認識と外界とのつながりの希薄で不確かさを描いている。
そういうアプローチを読むのは楽しめるのだが、前者のような傾向や文庫本のあとがきで思い切り言ってしまう著者の主張は、自己嫌悪・自己否定からくる人間憎悪に根ざしているように見えて、作品に意図的ではなく表れてしまうならともかく、自ら同じ本の後書きに入れるべきではないと思う。
と言っても嫌いな作品ではない。
そのうちまた手に取って読んでもいいと思う1冊。
単行本:2000年4月
文庫本:2003年5月
「(重要なモチーフ)入れすぎて混乱をきたしているんですけれど。…クローンなんです。でもクローンをやるのに記憶がはずせなくなって、記憶をやると泥沼に入るのはわかっていたけれどもそらすわけにはいかなかった。途中から結局<超男性>のYYの問題が出てきて、それを書きたいんだなって思ったときにはもう後半(笑)。」
(別冊文藝より 著者談)
「…物語の細部にちりばめられた謎が謎を呼び、生と性が人工的な操作によって複雑な共犯関係を結ぶ世界が構築されている。…血脈、家系を守るための人工的な人間の再生産は、染色体のレベルで異変をきたし、それが外見と内面のジェンダー認識のギャップに繋がり、さらに家族という制度が培ってきた既成概念の変更を迫る結果となる。残酷なかたちで自分の本当の姿を知る温にとっての<サマー・キャンプ>を描いた秀作。」
(別冊文藝より 大串尚代評)
以前、この本の感想をブログで書いた気がするので、探して、読み返してみた。
コレ。
2センテンス目なんて、だいぶ言っていることが違う…、なんて自分でもどう思っていたのかよく分かりませんが、苦笑、うん、風景は綺麗だとは今も思いました。
そしてつらつら考えたことを確かめるべく、最初から読み直してここまで至りました。
なかなかよくやったと自分を褒める。
内容とかでなく、継続して続けている事に対して、ネ。
「…話法は云い換えや反語ばかりだから、どうとでも解釈できるんだけど、…」
この「どうとでも解釈できる」のが長野まゆみの愉しさであると思います。
文庫のオビなんて
「愛情など、断じて求めない、はずだった。」ですから。




















なんかテレヴィジョン・シティの簡易版っていうイメージがあったんですが(笑)。
忘れた頃に思い出す感触が似た系統な気はします。