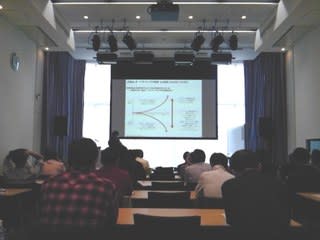
去る3月13日(土)、霞ヶ関にて、日本プロジェクトマネジメント協会(PMAJ)の一委員会「組込みシステム開発プロジェクト研究委員会」が主催する、人材育成関連のセミナーに参加しました。
タイトルは、「組込みシステム開発プロジェクト成功のための人材育成法-組込みシステム開発プロジェクト基盤の調査研究に基づくモデル研修-」というもの。
「組込みシステム」とは、一般人には聞きなれない用語ですが、炊飯器やエアコン等の家電、自動車や複写機などの機器に組み込まれたコンピュータシステムのことで、直接目に触れずとも、私達の生活に不可欠なソフトウェアとして浸透しています。
昨今ますます需要が高まっていることを背景に、如何にその開発プロジェクトを成功させるか、そのための人材育成が課題になっており、組織モデルと人材育成法が今回のテーマでした。
システム開発は専門外の私が参加した理由は、最先端の現場におけるプロジェクトマネジメントが抱える課題と、その中で人材育成がどのように行われているかを知るためでした。
プログラムは以下の3部構成で、ソフトウェア開発の関係者が40人以上集まり、業界の関心の高さを感じます。
講演「People CMMを活用した人と組織のWin-Win関係構築」前田卓雄氏
講演「擦り合わせ開発での人材育成課題」金子龍三氏
討論「組込みシステム開発の人材育成」笹部進氏×金子龍三氏
このうち、最も興味深かったのは、最初の前田卓雄さん(匠システムアーキテクツ株式会社/代表取締役)の話で、特に次の3点が印象的でした。
・ITやソフトウェアは、「人」に依存したビジネスである。
・人口減少社会にありながら、ソフトウェア需要は増大を続けるため、技術者の確保が困難になる。ソフトウェア生産性向上の伸びより、ソフトウェア需要の伸びの方が大きい。生産性の向上が鍵である。
・Capers Jones氏の著書「ソフトウェア開発の定量化手法」を基に、品質要因の差による品質への影響が3.3倍の開きに対し、生産性要因の差が生産性に与える影響は400倍もあることを指摘。生産性(成果)が向上するように人を活かすことが重要である。
「やはり」と言うべきか、「ここでも」と言うべきか、ボトルネックは「人と組織」に集約されるようです。本調査研究の報告書では、実に全9章のうち一章分が「組織と人材」に割かれいました。
「People CMM」の翻訳本を出されている前田さんに直接お聞きしたところ、日本の企業では米国ほど「People CMM」が浸透していないようでしたが、その哲学は現代のあらゆる組織に共通すると感じたので、最後に記しておきます。
【People CMMの10の哲学】
1.成熟した組織では、人的組織の真の実力は直接事業の成果に結び付いている。
2.人的組織の真の実力は、競争に打ち勝つための課題であり、戦略的な優位性を確立する源である。
3.人的組織の真の実力は、組織の戦略的事業目標に結び付けて定義されなければならない。
4.知識集約型の仕事では、単なる仕事の要素から人的組織のコンピテンシに重点が移っている。
5.人的組織の真の実力は、個人、ワークグループ、人的組織のコンピテンシ、組織の複数レベルで評価を改善することができる。
6.組織は、事業の核となるコアコンピテンシを決定する人的組織のコンピテンシの真の力を改善することに投資しなければならない。
7.事業運営上の管理は、この人的組織の真の力に対し重い責任を負っている。
8.人的組織の真の実力を改善することは、証明済みのプラクティスや手続きから構成されるプロセスとして追求することができる。
9.組織は、この改善機会を提供することに責任があり、個人はそれを活用することに責任がある。
10.技術や組織の形態は急速に変化するため、組織は継続して自己の人的組織のプラクティスを進化させ、新たな人的組織のプラクティスを開発しなければならない。
(匠システムアーキテクツ資料より)
タイトルは、「組込みシステム開発プロジェクト成功のための人材育成法-組込みシステム開発プロジェクト基盤の調査研究に基づくモデル研修-」というもの。
「組込みシステム」とは、一般人には聞きなれない用語ですが、炊飯器やエアコン等の家電、自動車や複写機などの機器に組み込まれたコンピュータシステムのことで、直接目に触れずとも、私達の生活に不可欠なソフトウェアとして浸透しています。
昨今ますます需要が高まっていることを背景に、如何にその開発プロジェクトを成功させるか、そのための人材育成が課題になっており、組織モデルと人材育成法が今回のテーマでした。
システム開発は専門外の私が参加した理由は、最先端の現場におけるプロジェクトマネジメントが抱える課題と、その中で人材育成がどのように行われているかを知るためでした。
プログラムは以下の3部構成で、ソフトウェア開発の関係者が40人以上集まり、業界の関心の高さを感じます。
講演「People CMMを活用した人と組織のWin-Win関係構築」前田卓雄氏
講演「擦り合わせ開発での人材育成課題」金子龍三氏
討論「組込みシステム開発の人材育成」笹部進氏×金子龍三氏
このうち、最も興味深かったのは、最初の前田卓雄さん(匠システムアーキテクツ株式会社/代表取締役)の話で、特に次の3点が印象的でした。
・ITやソフトウェアは、「人」に依存したビジネスである。
・人口減少社会にありながら、ソフトウェア需要は増大を続けるため、技術者の確保が困難になる。ソフトウェア生産性向上の伸びより、ソフトウェア需要の伸びの方が大きい。生産性の向上が鍵である。
・Capers Jones氏の著書「ソフトウェア開発の定量化手法」を基に、品質要因の差による品質への影響が3.3倍の開きに対し、生産性要因の差が生産性に与える影響は400倍もあることを指摘。生産性(成果)が向上するように人を活かすことが重要である。
「やはり」と言うべきか、「ここでも」と言うべきか、ボトルネックは「人と組織」に集約されるようです。本調査研究の報告書では、実に全9章のうち一章分が「組織と人材」に割かれいました。
「People CMM」の翻訳本を出されている前田さんに直接お聞きしたところ、日本の企業では米国ほど「People CMM」が浸透していないようでしたが、その哲学は現代のあらゆる組織に共通すると感じたので、最後に記しておきます。
【People CMMの10の哲学】
1.成熟した組織では、人的組織の真の実力は直接事業の成果に結び付いている。
2.人的組織の真の実力は、競争に打ち勝つための課題であり、戦略的な優位性を確立する源である。
3.人的組織の真の実力は、組織の戦略的事業目標に結び付けて定義されなければならない。
4.知識集約型の仕事では、単なる仕事の要素から人的組織のコンピテンシに重点が移っている。
5.人的組織の真の実力は、個人、ワークグループ、人的組織のコンピテンシ、組織の複数レベルで評価を改善することができる。
6.組織は、事業の核となるコアコンピテンシを決定する人的組織のコンピテンシの真の力を改善することに投資しなければならない。
7.事業運営上の管理は、この人的組織の真の力に対し重い責任を負っている。
8.人的組織の真の実力を改善することは、証明済みのプラクティスや手続きから構成されるプロセスとして追求することができる。
9.組織は、この改善機会を提供することに責任があり、個人はそれを活用することに責任がある。
10.技術や組織の形態は急速に変化するため、組織は継続して自己の人的組織のプラクティスを進化させ、新たな人的組織のプラクティスを開発しなければならない。
(匠システムアーキテクツ資料より)














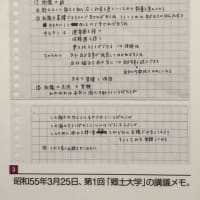

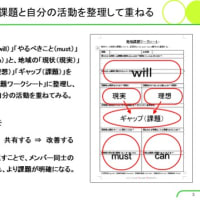
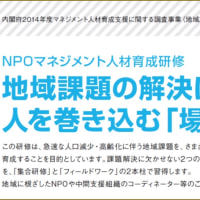
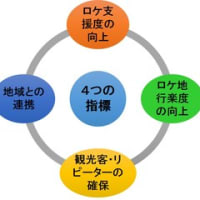








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます