 | イザベラ・バードの『日本奥地紀行』を読む (平凡社ライブラリーoffシリーズ)宮本 常一平凡社このアイテムの詳細を見る |
「非常に冷静に、しかも愛情を以って日本の文化を観てくれた一人の女性の日記」「彼女がこの時期(明治11年、1878年)に東京から北海道まで歩いてくれたことは、日本人にとってこの上ない幸せだった」。
庶民の生活を記録し続けた20世紀最大の旅人にして民俗学者の宮本常一氏(1907年~1981年)による講読会の貴重な記録。
宮本常一氏は英国の大旅行家/イザベラ・バードの著書『日本奥地紀行』について上記のように語っています。宮本常一氏もまた、いやそれ以上に、地球4周半に相当するほど日本を旅し、各地で暮らす庶民の姿を人々に語り続けてくれたことは、日本にとってこの上ない幸せでした。
本書の中で宮本さんは言います。
日本の"店"は、そもそも"見せる"ことから始まったのだと。
それは品物を見せるだけではなく、仕事を、作っているところを見せた。
ところが、戦後ショーウィンドウが一世を風靡すると、物はウィンドウに並べられて、人が奥へ入り込んでしまう。その時に日本の伝統工芸が滅びはじめた。
しかし、近頃レストランで料理するところを見せるようになったが、物を売る場合も同じではないか、と。
最近のニュースでは、食の安全・安心が話題にあがりますが、「見せる」という昔ながらの商売のやり方は、食の安全とは全く別の次元、もっと単純に心に直接訴えかける部分で人々の関心を惹き付けるのだと思います。
商売は、いくら価値の高い商品を作っても、それを伝える手段(コミュニケーション)を持たなければ真価を発揮することはできない。
まちづくりも商売も、商品という”結果”だけを見せるのではなく、結果に至るプロセスを如何に”見せる”か、これを工夫することが人を惹き付け、”魅せる”ことにつながるのではないでしょうか。














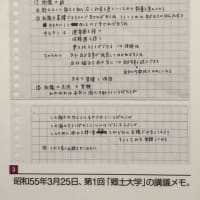

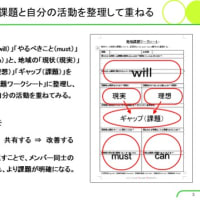
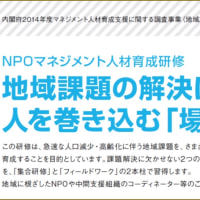
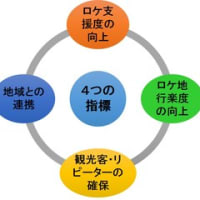








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます