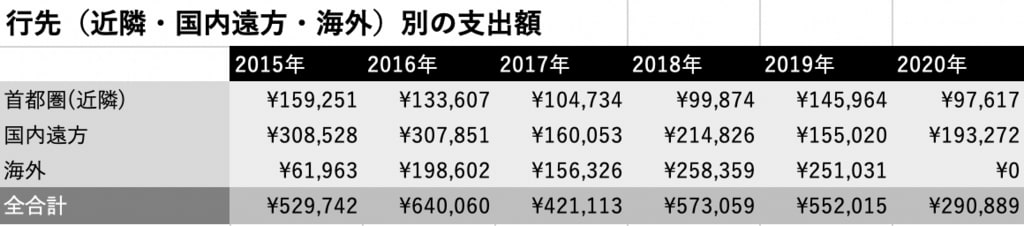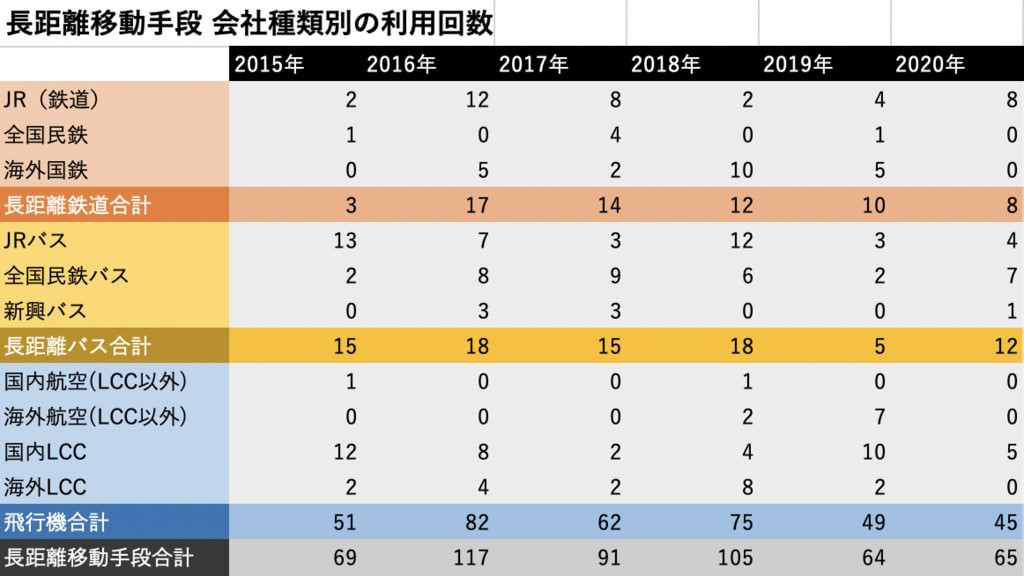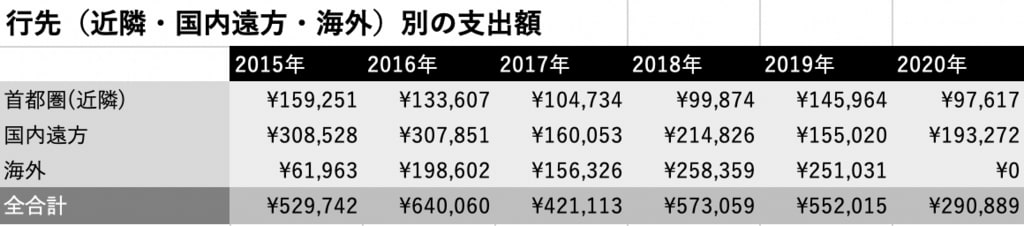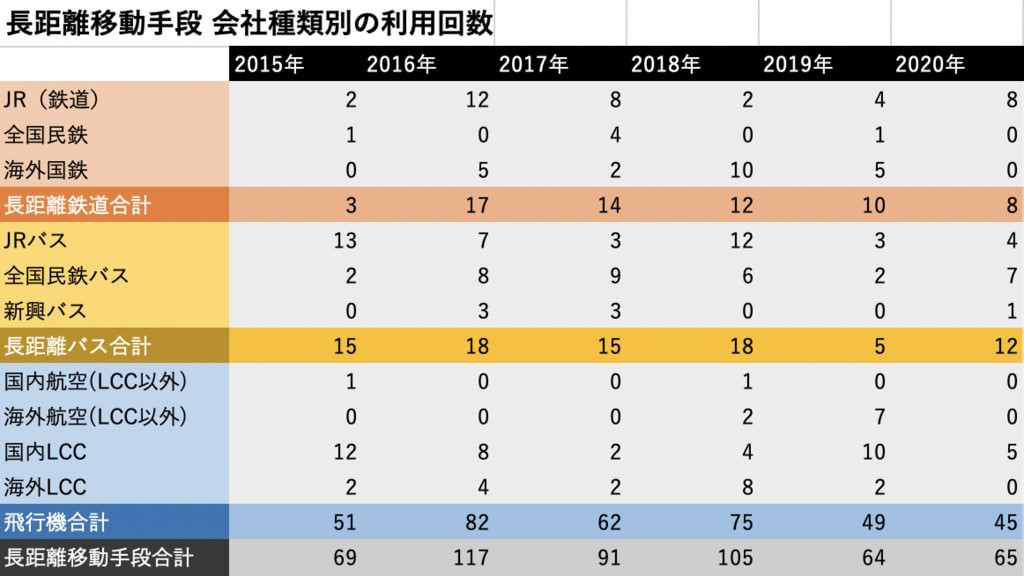ワタクシ、9月末に「お前の未来はない」と言われ、未来の行き詰まりを突きつけられました。誰が言ったって?・・・私です。
今年は、凄腕の空想地図作者が増えています。そのプレイヤーは大学生や高校生。コロナで遠くに行けない代わりに多くの時間が生まれたためこの勢いは進展した…と考えればコロナ影響ですが、関係ないかもしれません。それでは実際に見てみましょう。
手書きにして、今や幻となってしまった(※新規製作・刊行しなくなっただけで、残部は書店等にまだ多数あり、購入可能)1万分の1地形図です。よく見ないと見えないのですが、等高線は1メートル単位で描いてあります。その他、道路の車道と歩道が描き分けてあったり、何より全ての建物が描かれています。ひとつひとつ小さな建物が…戸建住宅や農家の納屋も…。芸が細かいというか、途方も無い作業量。さらに…
なんとこの方、架空の古地図をも作っています。この都市の旧版地形図です。右から読む旧字体であるだけでなく、この当時の地図記号(今は田を || で表現しますが、以前は水田、乾田、沼田がそれぞれ別の地図記号で、ここで描かれている || は水田)を再現。海岸線の線描グラデーションや、市街地の建物密集地の塗り方等、これまた芸が細かいのですが、自動車社会ではなかったこの時代特有の道路の広がり方や、河川改修されていない屈曲した川の様子、農村の様子が再現されています。
このツワモノはナニモノぞ、と思いますよね。ちょっと前まで高校生だったホヤホヤ大学生なのです。なんということだ…。
他にもいらっしゃいます。
こちらも新旧の古地図です。
旧城下町の城址が官有地や軍用地になって、戦後になると鉄道や道路が人やモノを集め、都市が広がっていく様子が描かれています。そして彼はさらに若かったはず…。
そして手描き勢に負けず、恐るべき知識とセンスと技術で空想地図を描くのが町田勢です。町田勢…と私が勝手に呼んでいるのですが、町田あたりにいる大学生2人です。ある時代の西洋画家を「印象派」と呼ぶ潮流があるように、あとで空想地図界の潮流を振り返るなら「町田派」とか言われているかも知れません。言われてるっていうか、私が言ってるのか…。
まさにこれは…
昭文社街の達人シリーズの1万分の1道路地図そのものなのですが、全て架空です。
彼はニュータウン開発、都市計画道路についてはかなり詳しく、宅地や道路の変化については、変わりゆく現地や、公示情報を追っています。情報収集力だけでなく、地図そのものも、
いかにももともと農村だったところが都市化して郊外住宅地になった…その様子をありありと描いています。私の中で巨匠扱いになっており、気安く声をかけられない状態にありますが、用件ができたのでこれから声をかけることになります(ハラハラ…)。詳しくは
彼のサイトをご覧ください。
最後に、もう一人の町田勢です。
彼もデザインは昭文社の都市地図そのものなのですが、近世から現代に至るまでの都市発展を追って、空想地図を作っています。城下町や主要寺社の形成、それらを結ぶ街道の形成を追い、それがそれ以降の時代の変化でどう都市化していったか、地名から道路や集落、その後の施設の作られ方、描き方は見事で、溜め息が出ます。私の語彙力と説明力が崩壊しています。
というわけで、空想地図界は恐るべきレベルアップで大変なことになっています。見て楽しいだけでなく学ぶべきものがありすぎる、空想地図の見どきです。気づいている人は気づいていて言わないだけだと思いますが、私は既に彼らにその知識や技術、センスを越されています。
そうなれば、私が空想地図作家を名乗って私ばかりがメディアに露出することへの不自然さが、そろそろ問題視されても良いのではないでしょうか。うちは歴史だけはあるけどおいしくない有名店、みたいなものです。
それゆえに、9月末に「お前の未来はない」と(私に)言われた訳ですが、そんな私に残された選択肢はふたつあろうかと思います。
・私がレベルアップする
・一人の描き手ではない、別の価値や機能、役割を見出す
結論から言うとどちらもやるんですが、私のレベルアップって限界があると思っています。なんたって彼らがすごい。とんでもない。それでもどうにか追いつこうと思っているわけです。
先日、こんなツイートをしたのですが、まだ構想段階で正式には決まっていません。オンライン「空想地図塾」。これは私が講師になって色々教えてやろう、というものではなく、私が学びたいのです。ただ、彼らに先生になってもらうのもアレなので(一流の職人が、それを教えるのに長けているとは限らない…というかたぶん彼らも職人肌)、空想地図の独習メソッドを模索し、技能向上の方法を編みだす試行錯誤の始まりです。私だけでなく他の描き手にも有益ではないか、と思っています。いつやるか、そろそろ決めなきゃ…。
続いて、別の価値や機能を見出すという話。前回の振り返りで「作家として生きる」話をしていたものの、それをひっくり返すような話ですが、空想地図"作家"のままではいかんなと。
彼らが技術と知識、センスに長けた職人であり、太刀打ちできないのなら、私に残されたアクション、アウトプットは何なのか。上記の独習メソッドもそうですが、空想地図を作ること、鑑賞することのプラットフォームづくりかと思っています。Twitterで空想地図を追っている人は、彼らの存在に気づいていますが、多くの人は私の空想地図にしか気づいていないかと思います。まず最初に、多くの人がこうした空想地図を見て、この記事で書いたような空想地図界の現状を知ってもらうのが先決だな、と思っています。
そのために…
来年内に
学芸出版社より「空想地図帳」を刊行予定です。さきほどは今年の空想地図の進展を紹介しましたが、これまでにも
Ranoさんをはじめ、凄腕空想地図作者はいます。今回紹介していない今年の空想地図もあります。古地図から現代の地図、街の様子が見える詳しい地図から、地域全体を見渡す地図帳まで、さまざまな地図があり、それぞれの地図から都市や地域の成り立ちを読み解くことができるのです。
ここまで来ると、空想地図は誰にも頼まれずに作られた、一人趣味のありもしない地図…ではなく、まちづくり関連の研究者、実務者にとって有益だ、と言うことです。作者としては一人前でなくとも、その中でなぜか商業出版の企画が通りやすい私ができることは、著述、刊行によってその道筋を作ることなのではないかと。
そう、そのために、これから私は各作者に掲載の許諾を取る連絡をするのです。掲載料…的にもそうおいしい話ではないし、りーべ君以外は会ったことがないし、多少の緊張を催すのですが、OKしてくれる作者が多ければ多いほど、内容は濃いものとなります。
それと同時に、さきほど「私の語彙力と説明力が崩壊しています」と書きましたが、問題は私の紹介力です。私にとって当たり前であえて紹介、説明することを省こうとする無意識…を言語化しなければなりませんし、私の知識や観点にも偏りがあるので、どこかで必ず知識不足が出てきます。これらをどうカバーし、良い本にしていくか…が、まず短期的な目標ではあります。
空想地図は私一人の一芸である…という誤解があるとすれば、この本でそれを解き、空想地図を見る人を育て、私だけでなく空想地図界の現状をしっかり把握する人が増えることを狙いたいと思っています。このままだと私は、私一人でこの件について悩む孤独状態で死にそうでしたが、やっと人とこの悩みを共有し、解決策を探っていく一助になるのではないか、って自分本位の話ですか…!??
スミマセン。ではまた。(つづく)
→