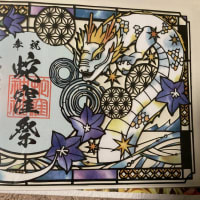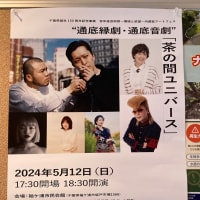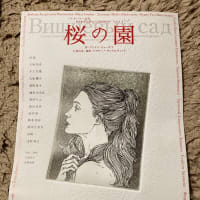シンポジウムがあって、それにも参加してきました。
場所は東京都現代美術館 地下二階 講堂で
先着200名でのシンポジウムでした。
■シンポジウム「過去からみる美術の現在(いま)」
総合司会:長谷川祐子(東京都現代美術館)
Session1「創造」の解放~ナム・ジュン・パイクからのメッセージ
ゲスト:阿部修也(ナム・ジュン・パイクの共同制作者)
パネリスト:森岡祥倫(評論家、メディア芸術史)
クワクボリョウタ(アーティスト)
村井啓哲(アーティスト)
Session2日常の実践~1970年代の美術と2000年以降
パネリスト:松井みどり(美術評論家)
中井康之(国立国際美術館)
青木淳(建築家)
モデレーター:住友文彦(東京都現代美術館)
Session1は11:00~12:30
Session2は14:00~15:30
一つ目のセッションでは、パイクと一緒に共同制作をした阿部修也さんが
ゲストで参加していました。
パイクがどんな人柄だったかなど、あと、面白い思い出話などしてくださいました。
もう、いいおじいちゃんなんですが、すごく目に力のあるしっかりとした
感じのおじいさんでした。
セッションの間、昼食をとったんですけど、近くの韓国焼肉屋に
入って食べていると、その阿部さんと、阿部さんとパイクを
引き合わせた今は亡き内田さんの奥さんとが入ってきて、
びっくりでした。
内気なので話しかけはできなかったんだけど、
二人で思い出話にふけっているようでした。
常設店のほうで、「TVクロック」というパイクの作品を再現して
いるんですけど、それを阿部さんが携わっているわけですが、
4日間で完成の予定が五日間かかったので、人件費を4日間で
申請してたので大変だったとか、いろいろ話を焼肉屋でしてました。
展示室に作品をひとつ飾るにもいろいろ苦労があるんだなぁと思いました。
それと昔のテレビと今のテレビは構造が違うらしく、
今のテレビは、火が出ないように、不具合が生じると切れるような
仕組みになっているそうです。ですから、パイクの作品を再現しようにも
今のテレビでは難しかったそうです。
コンピューターでごまかして、テレビに線を出しているんだそうです。
この話はシンポジウムでもされていたんですが、この話を聞かずに、
作品を見ていたら、きっとそんな苦労まで分からなかったろうなぁと
思います。
んでね、パイクの人間像としては、「一般人から抜け出たような人」
だったんだそうです。着眼点が違っていて、その上、細かくものを
見る人だったそうです。
このセッションのキーワードとして、「ベンド」という言葉がよく
使われていました。意味としては、目的はなく、とにかくいじるって
ことらしいです。
目的をもっての作品作りと、そうではなく、偶然性を楽しみ作品づくりと
いった話もいっぱい出てきました。
最近の作品づくりの傾向として、コラボ(企業などと)傾向が
あり、管理化されたアートといった印象が強いんだそうです。
・・・そうなんだ・・・とこれについてはあんまし考えたことなかったので、
そういう風な見方がされているんだなぁと勉強になりました。
セッション2のほうでは、焼肉食べて腹いっぱいってのもあって、
前半寝てしまいました。
セッション2では話が伸びて伸びて3時半終了予定が、4時半に・・・!
パネラー一人に10分程度と割り当てられてたのに、
一人ひとりがなんとなく長く話すもんだから、どんどん長くなってしまい、
一番聞きたいなぁと思っていた建築家の青木さんの話は本当に短くて
残念でした。
青木さんの最近の作品としては、昨年7月に建設された青森県立美術館
http://www.aomori-museum.jp/ja/が有名です。
「ぼくは~」とすごく穏やかな口調のおじさんで、
・・・本当に気のいいおじさんって感じなんですよね。
青森県立美術館にのHPに彼の写真がのっているけど、にこにこした
写真ですが、会場でもニコニコしている人でした。
話していることも、分かりやすい言葉でゆっくり話してくださったので、
分かりやすかったです。
セッション1もセッション2も私が重要だなぁと思ったことは、
壁を破ることですね。
目標を決めてしまうと、それ以上のことができない。
そうではなく、行き当たりばったりのようなたくましさって
必要だなぁって思うようなお話でした。
と、いうことで、帰りにアートショップによって手にした本は、
岡本太郎の「壁を破る言葉」という本。
岡本太郎の名言集のような感じの本ですけど、この本をパラパラ
見ていると、今日のシンポジウムで話題になっていたことが、
結構書かれているんですよね。
やっぱり岡本太郎は偉大なんだなぁと思わされました。
先の見えていた人なんでしょうね。
岡本太郎関連の情報として、4月より、東京都現代美術館で、
「明日への神話」が一年間常設で展示されるそうです。
見逃した方は是非、この機会をお見逃しなく。
最近の「美術」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事