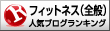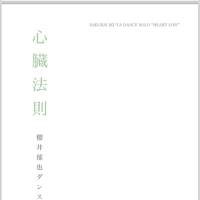数日前のこと。かかわっているダンス学校の学生のために「舞踊史」についての話を動画収録した。思いのほか大変だったが、良かった。
僕のメインの受け持ちは「創作・振付」なのだが、こちらは実技ゆえ「同じ場所に居る」ということの大切さが多大、なので、ウイルス状況をにらみつつナマで人数限定レッスン。それに先行して、「歴史」のレクチャーをオンラインで集中的に勉強してもらうつもり。
奇しくも、現代ダンスの生成期にもスペイン風邪のパンデミックが重なっている。第一次大戦、スペイン風邪、世界恐慌、、、。激しく世界が揺れるなかで、踊りもまた激しく生まれ変わっていったのだろうか。
ダンスの歴史は私たちの悲しみ喜び苦しみの歴史でもある。いま、こんな今を生きながら、祖先を想う。
発想にとって、過去への興味や感情はとても大切なのではないかと僕は思うし、過去は良くも悪くも僕らの原点なのではないか、とも思う。
僕自身、いまこの状況だから、ダンスというものの本来をさえ考えずにいられないし、創作や発表に対する取り組み方も連日あれこれ考える。そういうなかで、集中して歴史を話す時間を得たのは、大切な作業になった。
アフリカのドゴンやヌバのこと、トルコの旋回舞踊や足踏みによる祈りのこと、タリオーニ、ニジンスキー、ヴィグマン、ホートン、エイリー、カニンガム、土方さん、ピナ、、、。たどれば数知れない人のことがあり目眩がしたが、その目眩の中で、なんだかまた血が騒いできた。
人は本当に遠い昔から、この地上の隅から隅まであらゆる場所でダンスをしてきた。喜び苦しみ悲しみがある場所すべてにダンスは生まれるのだ。すべて素敵だったんだろうなあ、すごかったんだろうなあ。そう想像し妄想し、踊りたくなる。踊っても踊っても、もっと、としか言いようの無い誘惑が、ダンスというものには確かすぎるほど、あるのだ。
(僕のクラスやワークショップは全て実技だけれど、いづれ、舞踊史のレクチャーも一般の方向けに数日間やってみたくもあり、もし興味ある方がいらしたら、ぜひ声をください、企画します。)
そういえば、ナチョ・ドゥアートが改訂振付した「ラ・バヤデール」を数日前にテレビで観てとても良かった。もとはマリウス・プティパの有名振付だが、このようにして生まれ変わるのを見ると、なんだか、歴史というものの意味が伝わってくるように肌がざわめいた。少し前に観たアクラム・カーンの「ジゼル」でも歴史的なダンス作品が生まれ直す瞬間を深く感じた。
僕が学んだ師は日本に舞踏を生成したメンバーのひとりでもあり、そのすぐ先をたどればノイエタンツがあるし、その先をたどればクラシックも縁遠くはない。なんて思えば想像力がひろがる。学びと創りは刺激し合うのだろう。
踊りは、踊るという行為は、どこかで祖先に繋がっているにちがいない。ダンスは世代から世代へと何かを渡し繋げながら、新しく生まれ変わってゆく。
ダンスの身体は歴史を呼吸している身体でもある。
そう思う。
____________________________
▶レッスン内容、参加方法など
▶櫻井郁也によるステージ、ダンス作品の上演情報