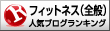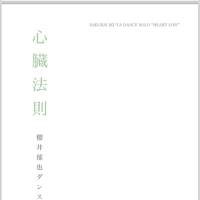音が与えてくれる心、というものがある。
ダンスを通じて、そんなことを思うことが多かった。
活動自粛となって以来、
公演作品とは別に、
ただ純粋に音楽を踊りたくて、ひとり稽古をしている。
そのなかに、マーラーの「亡き子を偲ぶ歌」という題名の曲集があり、
新しい思いを導いてくれた。
長く、ずっと心にあった曲だが踊ることはこのたびまでなかった。
壮大なシンフォニーにもかかわる歌・旋律・情。
踊らなければ聴こえてこないものが、
この音楽にはものすごく詰まっている。
受容。
音楽に射つらぬかれることから、はじまる。
いまはスタジオがないから、自宅の片隅で稽古する。
生活空間の一部で我を壊しくだくのはなかなか難しい。
発表とか作品とか言う前に、ただただ「聴く」ために稽古する。
修業時代の感覚に戻っている。
さぐる。さがす。
というようなことを、なぜか無性にしてしまう。
踊りの種はあらゆるところにあるが、
聴覚と舞踊感覚との関係には特別なものがあるように思う。
過去作の「かなたをきく」という公演の根にあったテーマにもつながる。

存在することについて、
希望について、
とてつもない深さと広さを、
マーラーのこの歌はあらわし響き渡る。
音楽にひたすら溶け込もうとする。
それは、タマシイに身をゆだねることにも似ている。
これは、ダンスの醍醐味のひとつかもしれない。
音楽はタマシイの声で、踊りをおこすのだ。
自分のナカを表したい気持ちとは別に、
他なる存在に近づきたいという気持ちが、
踊るとき大きい。
きこえるものに、身をよせる。
心身をいったん他者に預けてみる。
他者のココロに溶けてゆこうとする。
音楽に溺れる。
感極まった時に、自分の中に「誰か」が入り込んでくる。
それは、新しい心の「たね」が宿ることに、ちかい。
我を消す試み、と言うと大げさか、、、。
ダンスの作品をつくるとき、
僕はたいてい自分で音や音楽をつくる。
だから、
誰かの作曲した音楽を踊るときは、
特別その人の音楽でなければならない、というときだ。
他者の音楽を踊るというのは、
他者のタマシイを呼吸するようなもの、だ。
そう思う。
踊ることは、タマシイの呼吸
とも言えるのではないかと、
いま、本気で思う。
踊る、ということを考え直す時間。
生きる、ということを考え直す時間。
ここにいる、ということを考え直す時間。
そんなふうに、いまこの異様な状況の、時の流れを噛み砕いている。
※東京ではまだ緊急事態宣言が解除されない状況で、窮地が続くなか、僕が現在確信をもって出来ていることは、結局は、淡々と稽古する、個というものを確かめ直す、ということにつきております。
表には出なくとも、止まらないこと。持続。ということなのでしょうか。
少なくとも、いまの「この時間」から何か深まってゆくものはあるはずとの思いで、ここは、時間をかけた作品づくりの期間と認識しております。
じっくり温めたものでないと、自信をもってお見せすることが出来ないので、じたばたせずに稽古を重ねるしか、能がありません。
疫病による中断と危機は、少なくとも、自分の中身が枯渇して何も出来ないのとは、まったく違う状況です。
生活は困難ですが、どんどん何かが溜まり高まり、うねってゆくのを感じます。
____________________________
▶これからのレッスン内容、ご参加の方法など
▶櫻井郁也によるステージ、ダンス作品の上演情報