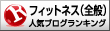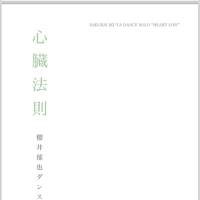言葉以前の言葉という言葉を以前ダンス公演のあとにいただいたことがあり、それを具体的に意識化する困難をも感じながら、しかし何度かの舞台を重ねながら次第次第にからだとことばの間に勝手に張り詰めさせていた膜のようなものが薄らいでゆくような感覚を、今秋の公演準備のなかで味わい始めている。
それはそれとしても、言葉なるものの重さを感じことが最近とても多い。
思い出せば、言葉の重さを痛感した一つが、言葉が肉体を破って出ることを同時に肉体が破裂寸前の言葉であるようにさえ感じたアレン・ギンズバーグ自身によるナマのビートパフォーマンスだった。
それは20世紀が終わるある夜の永田町の砂防会館だったが、自民党本部に近いそこは田中角栄がロッキード事件に関する初の会見を開いた地点つまり歴史のからくりが「舞台」すなわち「明るみ」に上げられた現場の一つだったという記憶が重なり(この日を境に日本人の政治家に対する眼差しが急速に冷却され、やがて一国の総理大臣を務めた人物は「田中」と呼び捨てにされて逮捕された)その当時の空気のなかで資本制民主主義という政治言語の裏を知覚し始め言論なるものの空々しさとさらには言語なるものの実体をさえ懐疑しながら育った僕らの世代には、偶然としてもその記憶の宿る場所にビートニクスの声が響きわたったその瞬間は「不屈の声」を垣間見たように生々しく刺激だった。
あの夜の、歴史の過程を共有しているのではないかというような感覚に対して、同じギンズバーグの言葉に触れる場でも21世紀の今度は、ある波を過ぎてなお深く身体の内部に響き蠢き続ける魂のどよめきに触れているような、発話される前の言葉の根っこに触れるような、あるいは一度発話された言葉が分解や溶解を経て新しい個の思索の渦を形成してゆく感覚を覚醒されるような「体験」を(ライブ当夜にも記事を書いたが)コンサートホールという中間地点(しかしその場所は3.11震災当夜の奇跡的演奏会の場として記憶された場所でもあるが)で行われたパティ・スミスとフィリップ・グラスと村上春樹によるリ・リーディング(読み直し=声と音楽による詩の再構築)によって与えられたように思う。
ギンズバーグというある詩人の誕生日であるその夜に集い詩人を思い出し詩人に語りかけ耳を澄まし合いやがて最終的には「ピープル」というこの詩人の痛みさえ連想する言葉を軸にした「ともに歌う」という行為に、会場全体で帰結を成したその夜は、個、の言葉というものが発話の地点を離陸した遥かあとに他者に受け継がれながら新しい魂や熱に着地し得ることの証しにもさえ、聴こえ、た。
時を越えて他者に受け継がれながら繰り返される言葉、詩、リサイト。
言葉の声。その残響をリピートしながら「真実を知りたければ劇場に行け」という古い言葉を思い出した。
それはアポクリファ(聖書編集から何らかの理由で外された書)の一つヨハネ言行録の一部だが、歌や踊りを聴き見つめながら人が生き方を振り返り「一人」の人間に帰還するための場所、神さえも思索の対象となる自由な感性の空間、蠢めく魂と言葉の混沌する場所、劇場とは祭りとはそういう場所でありそこに真実を知りたいならば、行け、と古人は書いたのだと思う。
しかしそのような場所でさえ暴力の対象になってしまう時代に僕らは生きていて何故いま生活者が集う場とその一人一人が傷を担わされるのかと悶えている。権力者も反権力者も、劇場なるつまり文化の現場を何を共有する場と思っているのだろうか。
そこには娯楽も享楽も訪れてあるがその背後には集う一人一人が怒りや渇きや矛盾や沈黙が反響しているはずで演者・裏方・見所それぞれふくめ集う私たちは一人一人が別なる思いを思いながらも劇場の狭い空間や祭りの喧騒のなかで言葉なき言葉を共有して新しい意識を模索してゆこうとしているのだしイデオロギーなどでは全く語り得ない無数の共感と反感の波打ちを舞台と客席の闇で反射しあいながら一人一人の心をプロセスしているのだということを彼らは知ろうとしているだろうか。
もし世界に語りかけたいならば銃ではなく歌をもって暴力ではなく発話をもって、力、としたい。
希求するものを想像力や哲学の仕方で交感し温めたい。
そう思って劇場や祭りの場に人々はわざわざ集うのではないだろうか。
実社会で立たされざるを得ない立場から離れて「一人」に還る時間と場所。
互いの別なる言葉を語り互いの沈黙を感じ互いに個に還ってゆくこと純粋な一人になって何かを感じ考えることそれを、劇場は確保する場だ。
僕らは無力だが無意味ではなく、とても小さなエネルギーの端っこではある。ゆえに集う。ゆえに語り歌い踊る。ゆえに見つめ、ゆえに傾聴する。
世界はおおむね無力者のささやかな営みの場所でそのなかにある劇場は祭りはとても小さな自由区だしかし、ほんのすこしのエネルギーが微かに微かに何かを変革してゆくことを信じている人々の場でもある。
世界は反感と共感の波打つ海でありそのなかにあるからこそ、例えば踊る、例えば歌う、例えば詩を書き、例えば一枚の小さな絵を描いて、互いに何かを託すのではないか。互いを見つめ、互いに耳を傾けてゆく、のではないか。
一羽の蝶の羽ばたきが、決して無意味でないように、、、。
相次ぐテロとそれらに対する権力の処し方のなかで、暴力でなく言葉を、銃ではなく歌を踊りを、と、切に切に思う。
抗う敵は、本当は何なのか、どこにいるのか。人を苦しめる力は、人の苦しみや不毛は、いまどこに根ざしてあるのか。世界は心で変わるのだから、一人一人の心の働きを、もっともっともっと一人一人が自分の心を感じて自分で考える時間がほしい。それは一人の重さを復権することにも繋がるはずではないか。そんなことを漠と考えていると、先のパティ・スミスたちがあえて「people/ヒトビト」という言葉をいま発話し直そうとしたことも、腑に落ちてくるのだった。
「考え、伝え、共感を待ち、行動する」そのような時間の使い方を獲得し、語りかけることによって不要な殺しを避ける、という知恵を得たことこそが霊長類におけるサピエンス(考える存在)への大きな進化だと読んだことがある。
怒れども過激にならず、小さく無力な言葉をこそ丁寧に紡いで、響き合いを待つ。そんなことを、もっと大切に出来ないものか、と思う。一人の運命は世界の運命に、おそらくは相似するし「私たち」とは「一人一人の他者」による「異質なるものの鎖」なのではないかと、思う。
ふと思い出して、このメモを書いた。
●櫻井郁也・次回ダンス公演info.
公演ホームページ http://www.cross-section.x0.com
それはそれとしても、言葉なるものの重さを感じことが最近とても多い。
思い出せば、言葉の重さを痛感した一つが、言葉が肉体を破って出ることを同時に肉体が破裂寸前の言葉であるようにさえ感じたアレン・ギンズバーグ自身によるナマのビートパフォーマンスだった。
それは20世紀が終わるある夜の永田町の砂防会館だったが、自民党本部に近いそこは田中角栄がロッキード事件に関する初の会見を開いた地点つまり歴史のからくりが「舞台」すなわち「明るみ」に上げられた現場の一つだったという記憶が重なり(この日を境に日本人の政治家に対する眼差しが急速に冷却され、やがて一国の総理大臣を務めた人物は「田中」と呼び捨てにされて逮捕された)その当時の空気のなかで資本制民主主義という政治言語の裏を知覚し始め言論なるものの空々しさとさらには言語なるものの実体をさえ懐疑しながら育った僕らの世代には、偶然としてもその記憶の宿る場所にビートニクスの声が響きわたったその瞬間は「不屈の声」を垣間見たように生々しく刺激だった。
あの夜の、歴史の過程を共有しているのではないかというような感覚に対して、同じギンズバーグの言葉に触れる場でも21世紀の今度は、ある波を過ぎてなお深く身体の内部に響き蠢き続ける魂のどよめきに触れているような、発話される前の言葉の根っこに触れるような、あるいは一度発話された言葉が分解や溶解を経て新しい個の思索の渦を形成してゆく感覚を覚醒されるような「体験」を(ライブ当夜にも記事を書いたが)コンサートホールという中間地点(しかしその場所は3.11震災当夜の奇跡的演奏会の場として記憶された場所でもあるが)で行われたパティ・スミスとフィリップ・グラスと村上春樹によるリ・リーディング(読み直し=声と音楽による詩の再構築)によって与えられたように思う。
ギンズバーグというある詩人の誕生日であるその夜に集い詩人を思い出し詩人に語りかけ耳を澄まし合いやがて最終的には「ピープル」というこの詩人の痛みさえ連想する言葉を軸にした「ともに歌う」という行為に、会場全体で帰結を成したその夜は、個、の言葉というものが発話の地点を離陸した遥かあとに他者に受け継がれながら新しい魂や熱に着地し得ることの証しにもさえ、聴こえ、た。
時を越えて他者に受け継がれながら繰り返される言葉、詩、リサイト。
言葉の声。その残響をリピートしながら「真実を知りたければ劇場に行け」という古い言葉を思い出した。
それはアポクリファ(聖書編集から何らかの理由で外された書)の一つヨハネ言行録の一部だが、歌や踊りを聴き見つめながら人が生き方を振り返り「一人」の人間に帰還するための場所、神さえも思索の対象となる自由な感性の空間、蠢めく魂と言葉の混沌する場所、劇場とは祭りとはそういう場所でありそこに真実を知りたいならば、行け、と古人は書いたのだと思う。
しかしそのような場所でさえ暴力の対象になってしまう時代に僕らは生きていて何故いま生活者が集う場とその一人一人が傷を担わされるのかと悶えている。権力者も反権力者も、劇場なるつまり文化の現場を何を共有する場と思っているのだろうか。
そこには娯楽も享楽も訪れてあるがその背後には集う一人一人が怒りや渇きや矛盾や沈黙が反響しているはずで演者・裏方・見所それぞれふくめ集う私たちは一人一人が別なる思いを思いながらも劇場の狭い空間や祭りの喧騒のなかで言葉なき言葉を共有して新しい意識を模索してゆこうとしているのだしイデオロギーなどでは全く語り得ない無数の共感と反感の波打ちを舞台と客席の闇で反射しあいながら一人一人の心をプロセスしているのだということを彼らは知ろうとしているだろうか。
もし世界に語りかけたいならば銃ではなく歌をもって暴力ではなく発話をもって、力、としたい。
希求するものを想像力や哲学の仕方で交感し温めたい。
そう思って劇場や祭りの場に人々はわざわざ集うのではないだろうか。
実社会で立たされざるを得ない立場から離れて「一人」に還る時間と場所。
互いの別なる言葉を語り互いの沈黙を感じ互いに個に還ってゆくこと純粋な一人になって何かを感じ考えることそれを、劇場は確保する場だ。
僕らは無力だが無意味ではなく、とても小さなエネルギーの端っこではある。ゆえに集う。ゆえに語り歌い踊る。ゆえに見つめ、ゆえに傾聴する。
世界はおおむね無力者のささやかな営みの場所でそのなかにある劇場は祭りはとても小さな自由区だしかし、ほんのすこしのエネルギーが微かに微かに何かを変革してゆくことを信じている人々の場でもある。
世界は反感と共感の波打つ海でありそのなかにあるからこそ、例えば踊る、例えば歌う、例えば詩を書き、例えば一枚の小さな絵を描いて、互いに何かを託すのではないか。互いを見つめ、互いに耳を傾けてゆく、のではないか。
一羽の蝶の羽ばたきが、決して無意味でないように、、、。
相次ぐテロとそれらに対する権力の処し方のなかで、暴力でなく言葉を、銃ではなく歌を踊りを、と、切に切に思う。
抗う敵は、本当は何なのか、どこにいるのか。人を苦しめる力は、人の苦しみや不毛は、いまどこに根ざしてあるのか。世界は心で変わるのだから、一人一人の心の働きを、もっともっともっと一人一人が自分の心を感じて自分で考える時間がほしい。それは一人の重さを復権することにも繋がるはずではないか。そんなことを漠と考えていると、先のパティ・スミスたちがあえて「people/ヒトビト」という言葉をいま発話し直そうとしたことも、腑に落ちてくるのだった。
「考え、伝え、共感を待ち、行動する」そのような時間の使い方を獲得し、語りかけることによって不要な殺しを避ける、という知恵を得たことこそが霊長類におけるサピエンス(考える存在)への大きな進化だと読んだことがある。
怒れども過激にならず、小さく無力な言葉をこそ丁寧に紡いで、響き合いを待つ。そんなことを、もっと大切に出来ないものか、と思う。一人の運命は世界の運命に、おそらくは相似するし「私たち」とは「一人一人の他者」による「異質なるものの鎖」なのではないかと、思う。
ふと思い出して、このメモを書いた。
●櫻井郁也・次回ダンス公演info.
公演ホームページ http://www.cross-section.x0.com