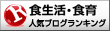・炭/木炭Charcoal すみ/もくたん
主によく、脱臭に用いている炭ですが、既存添加物とし着色目的で認められ食品添加物としても使われています。
木炭や竹炭の原料を空気が少ないところで加熱すると、300℃くらいから急激に組織分解を始め、二酸化炭素(炭素・水素・酸素)などの揮発分がガスとなって放出し、炭化によって植物体の炭素の30~40%の炭ができると言われます。材料の木材から揮発成分を抜いたものであり、木材と違い炎が出ないか、少なくなります。
一般的な炭は木材(水分・繊維・ミネラル)を原料として造られています。伐倒(ばっとう)直後の木は含水率が60~100%、スギのような水分の多い木では含水率が200%近くあることさえあるようです。木材はセルロース、ヘミセルロース、リグニン、炭素、酸素、水素などの物質で木材を普通に加熱すると、160~400℃で熱分解が起こります。260~800℃で組成分解し炭化、600~1800℃で炭素化、1600℃で黒鉛化するのですが、酸素が少ないところでの加熱では、280℃~300℃くらいから急激に組成分解が始まり、二酸化炭素、一酸化炭素、水素、炭化水素等のガスが揮発し、炭化(たんか)が進みます。
酸素が少ない環境では、ガスに火がつくことはなく、小さな結晶が不規則に並んだ無定形炭素に変化します。木材内部には道管や師管と言われる無数の管を張り巡らし炭化すると、その管の跡がミクロの孔となって残ります。多孔質で、空気浄化、水質浄化、脱臭などで用い知られます。
さらに無数の小さな孔に空気が取り込まれ加熱していくと、炭は木材よりも燃えやすく、火持ちが良くなり炭・木炭(水分10%内外)として用いてきたのです。
食品原材料としての食品添加物があります。植物炭末色素という名称の着色料として利用しています。既存添加物である活性炭はJECFA(FAO/ WHO合同食品添加物専門家会議)による、植物炭末色素はEUによる安全性評価がなされていることから、基本的な安全性の確保があると評価しています。発がん性物質であるベンゾピレンBenzopyreneが含まれている可能性がありますが非常に微量であり、不必要に大量使用しなければ、比較的安全なものであると考えられるとしています。
植物炭末色素の主成分は炭素であり、一般的にタケ・ミカン・スギ等を原材料として製造します。タケからの竹炭パウダーが植物炭末色素とし多く流通し最も多く食品利用しています。色素添加物で、炭素由来の黒色を呈しています。植物炭末色素を食品に使用した場合、食品ラベルに「植物炭末色素」「炭末色素」「着色料(炭末)」との表示です。
植物炭末(たんまつ)色素は、2μm~25μmまでの粒径(りゅうけい)にあり全体の90%は15μm以下の大きさとなり、 粒子平均は5~7μmと非常に細かいので、食べた際にざらつき等の違和感はないようです。
また、主成分が炭素なので、熱や光に対して安定、水や油に溶解しないという特徴があります。
竹炭自体は無味無臭のため、竹炭を入れたからといって 味が変わるわけではありません。菓子、パン、麺、カマボコ、ソースなど様々な食品を黒色に着色するために用いています。また、黒ゴマや黒豆味の食品への補色利用、焼き鳥やステーキの炭火焼き感の増強に利用されることもあります。最近ではインスタ映えを狙って、様々な食品を黒色にする際の着色剤としての利用も多いようです。
使用基準として、こんぶ類、食肉、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、豆類、野菜およびわかめ類に使用してはならない。
直射日光、高温多湿を避け、20度以下の冷暗所保管、開封後は本品は乾燥品ですので、大変吸湿をしやすくなっています。長時間の開封を避け密封後20度以下の冷暗所保管です。
昔から「炭焼き職人は長生きする」といわれています。炭焼き職人は炭のでき具合を確かめるために炭を食べる習慣があったためではないかという説があります。炭が体に良いことについては昔から知られています。1日の摂取量は耳かき2~3杯程度といわれています。炭の製造過程に生じる孔が有する吸着力が体内の有害物質を排出するという作用で、消化不良や便秘などで腸内に滞留した消化物から発生する有害物質やガスの吸着・排出に有効であると言われます。カリウムやマグネシウム等ミネラル分の補給にもなります。
人の体内には健康を害する様々な有害物質が入り込んできます。炭はそのような有害物質を吸着作用で孔内部に取り込み、便とともに体外に排出することで私たちの健康維持に貢献してくれることもあるようです。
ご愛読戴きましてありがとうございます。よりよい情報をお届けしてまいります。