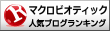・柿の日 かきのひ
明治28年(1895年)の10月26日からの奈良旅行で、「柿くえば鐘が鳴るなり法隆寺 」と・正岡子規(1867
柿Persimmon かき
カキノキ科、中国原産。甘柿(温暖地・次郎、富有、御所)と渋柿(寒冷地・平核無[ひらたねなし]、会津身不知〈あいづみしらず〉、百目〈ひゃくめ〉)に大別している。10~11月にかけて果実が成熟し採取され生食用とし市場に多く出回り旬とし、0~15℃で2~3ヶ月の保存が可能としている。
そのまま食べるほかサラダ、柿なます、干し柿、柿羊羹として加工される。柿の葉がお茶、揚げ物、柿の葉寿司に利用している。昔からの言い伝えで「柿が赤くなると医者が青くなる」といわれるぐらい栄養価値の高い食材であるが、不消化が多く消化が悪く、身体を冷やすといわれ多食を避けたほうがよいともいわれる。
特徴は、干柿にみられる表面の白い粉マンニット(ブドウ糖、果糖)が、粘膜を潤し、咳止め、気管支炎の予防によい。柿の色を出しているのはフラボノイド、アントシアン、カロチノイド(リコピン、ルチン、クリプトキサンチン500μg%、βーカロチン420μg%)により、リコピンが多いとあざやかにみえる。渋みの主体シブオール(フェノールカルボン酸、タンニン)は、渋柿で1~2%、甘柿(ゴマは、タンニン細胞の変化したもの)0.01~0.08%含む。柿の渋みタンニンは、水溶性で甘柿は成熟するに従い不溶性に変化して甘くなるが渋柿は成熟してもそのまま残っているのでお湯、アルコールに漬け、エチレンガスを利用、干し柿にして渋みを抜いている。
褐変の原因になるポリフェノールオキシダーゼをあまり含んでいないので皮をむいて多少の保存が可能としている。
柿渋が日本酒の清澄剤(せいちょうざい)、渋紙に使われる。ビタミンC70mg/100g中で多く含む。カテキンやプロアントシアニジンProanthocyanidinなどの抗酸化成分も豊富に含まれる。柿は植物名ではカキノキが正しく、ヘタを柿蔕(してい)といい、古くからしゃっくり止、鎮咳に利用していた。
ご愛読戴きましてありがとうございます。よりよい情報をお届けしてまいります。