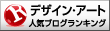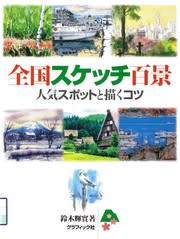「デッサン」というと対象物の形やあり様を正確に捉える力、そしてそれを表現する力ということとなります。
「スケッチ」というともう少し描く人の気持ちに近い、フレンドリーな響きではないでしょうか。
「旅に出てスケッチを楽しむ。」というのは、人が旅の途中で気づいたこと、感じたことをメモ代わりに絵で表したものと言えます。正確に描くということよりも、その人のものの捉え方、感じ方が表れるものなのです。そこでは大胆な省略やデフォルメも許されます。
しかし、造形言語で表されたスケッチにおいても、見たものや感じたことが絵で伝わっているかかどうか、という点は大きなポイントとなります。
スケッチを通して作者の見たもの感じたことが第三者とコミュニケーションできることは大切です。
時々、自分だけの記録ですと言う人もいますが、描いたものを第三者に見てもらい共感してもらえると、そこに新たな喜びもうまれるのです。
スケッチは短時間に対象としっかり向き合い、夢中に、集中して、心の中で対話をしながら自分が感じたことに素直に描写していく姿勢が一番大切です。
時間をかけて描いたからといっていいスケッチになるとは限りません。
短時間でも、「集中した深さ」がスケッチの良し悪しを決めます。
「スケッチは、対象物に自分をぶつけることが大切だ。無心になると言い換えてもいいし、無我夢中になると言ってもいい。あるいは集中して描くと言ってもいい。自然や文物や仏像や人物に対して、心の中で対話をしながら対象物から感じ取ったことを線で思うままに描写していく。《スケッチとは、全人格の練磨となる》」
「対象物をどうスケッチしようと構わないわけだが、スケッチとは、それまでの持てる知識と技術を総動員し、その対象物をどう理解するか、を問われているのである。・・・表現力とか描写力を鍛えるには、なによりも「自分の意見(考え)」を持つことこそが大切なのである。」
「どこを省略して、どこを強調するかということは、言い換えれば、自分を問われていることなのだ。自分に意見がなければ、どこを省略したらいいのか皆目、見当ががつかない。省略とデフォルメが有機的につながってこそ、その人独自の世界が生まれてくるのである。」
(平山郁夫「永遠の道」110p~103p、1992、プレジデント社)
「スケッチ」というともう少し描く人の気持ちに近い、フレンドリーな響きではないでしょうか。
「旅に出てスケッチを楽しむ。」というのは、人が旅の途中で気づいたこと、感じたことをメモ代わりに絵で表したものと言えます。正確に描くということよりも、その人のものの捉え方、感じ方が表れるものなのです。そこでは大胆な省略やデフォルメも許されます。
しかし、造形言語で表されたスケッチにおいても、見たものや感じたことが絵で伝わっているかかどうか、という点は大きなポイントとなります。
スケッチを通して作者の見たもの感じたことが第三者とコミュニケーションできることは大切です。
時々、自分だけの記録ですと言う人もいますが、描いたものを第三者に見てもらい共感してもらえると、そこに新たな喜びもうまれるのです。
スケッチは短時間に対象としっかり向き合い、夢中に、集中して、心の中で対話をしながら自分が感じたことに素直に描写していく姿勢が一番大切です。
時間をかけて描いたからといっていいスケッチになるとは限りません。
短時間でも、「集中した深さ」がスケッチの良し悪しを決めます。
「スケッチは、対象物に自分をぶつけることが大切だ。無心になると言い換えてもいいし、無我夢中になると言ってもいい。あるいは集中して描くと言ってもいい。自然や文物や仏像や人物に対して、心の中で対話をしながら対象物から感じ取ったことを線で思うままに描写していく。《スケッチとは、全人格の練磨となる》」
「対象物をどうスケッチしようと構わないわけだが、スケッチとは、それまでの持てる知識と技術を総動員し、その対象物をどう理解するか、を問われているのである。・・・表現力とか描写力を鍛えるには、なによりも「自分の意見(考え)」を持つことこそが大切なのである。」
「どこを省略して、どこを強調するかということは、言い換えれば、自分を問われていることなのだ。自分に意見がなければ、どこを省略したらいいのか皆目、見当ががつかない。省略とデフォルメが有機的につながってこそ、その人独自の世界が生まれてくるのである。」
(平山郁夫「永遠の道」110p~103p、1992、プレジデント社)