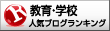「太い芯の鉛筆で描きましょう。」
今の子どもは鉛筆ではなくシャープペンシルを良く使います。
ノートをとるのには一定の細い線が安定して書けるということが非常に便利な筆記具ですが、絵を描く場合、その線の細さがネックになります。
線が細いと、小さな形のくるい、少しの線のくるいが気になります。
紙に対しても筆圧がかかってしまい、紙にキズがついてしまいます。
3B~8Bなど、芯が太くてやわらかいと、太い線がそのまま大まかな形の捉え方となり、小さなの形のくるいは気にならなくなります。
柔らかい芯でやさしく形を探していきましょう。
対象の大きな構造をつかむには、太い芯の鉛筆がいいのです。
戻る
今の子どもは鉛筆ではなくシャープペンシルを良く使います。
ノートをとるのには一定の細い線が安定して書けるということが非常に便利な筆記具ですが、絵を描く場合、その線の細さがネックになります。
線が細いと、小さな形のくるい、少しの線のくるいが気になります。
紙に対しても筆圧がかかってしまい、紙にキズがついてしまいます。
3B~8Bなど、芯が太くてやわらかいと、太い線がそのまま大まかな形の捉え方となり、小さなの形のくるいは気にならなくなります。
柔らかい芯でやさしく形を探していきましょう。
対象の大きな構造をつかむには、太い芯の鉛筆がいいのです。
戻る