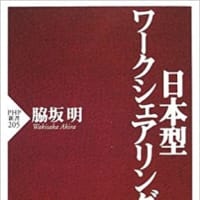米澤泉,2014,「女子」の誕生,勁草書房.(2.7.25)
「子ども」や「主婦」と同様、「女子」も近代社会が生み出した存在であり、その「女子」の内実がどう変容してきたのか、それを主にファッション雑誌から探り出し、読み解こうという米澤さんの問題意識は、まことに正道を行くものだ。
「女子」がもっとキレイにカワイくなろうとするのは、男のためではない。
鏡に映った自分に萌えるため、あるいは、「気分をあげる」ため、である。
階層上昇婚を当て込む女子大生をターゲットにした『JJ』等の「赤文字」系ファッション誌はとうに姿を消した。
「きさまいつまで女子でいるのか」という問いへの答えは、「いつまでも」、である。
コスメや衣服で武装し、「女子」という「鎧」を身にまとう女たちは、おそらく、一生、「わたしに萌える」。
年齢や役割、ライフスタイルと強固に結びついていたファッションが九〇年代を境にその呪縛を解き放たれた。女子大生もOLも主婦もキャリア女性も目指すところは同じとなった。もっとキレイに、もっとカワイく。ファッション誌にもはや成熟した大人の女性はいらない。いくつになってもフリルやリボンを身に付けたい。好きな服を自由に着たい。「女子」の誕生である。「28歳、一生〝女の子”宣言!」と「常識」を超えた「大人かわいい」ファッションの台頭とともに、それを着こなす「大人女子」が増殖してきたのであった。すぐさまファッションの世界においては、「三〇代女子」や「四〇代女子」が当たり前の存在となった。そして、今や、「大人女子」はファッションやメイクの流行の域を超える現象となったのである。
「女子」という言葉の裏側には、何歳になっても主役を降りたくない、脇役に回りたくない、という女性たちの願望が存在する。妻でもなく、母でもなく一人の「女子」として一生を生きていくという「三〇代女子」や「四〇代女子」の決意は、主役人生を全うすることの表明である。
さらに、「女子」という言葉は女性を既婚や未婚、キャリアや主婦といった立場に分かつことなく、一つにする。女子と呼ばれ、まだ未分化だったあの頃、あるいは女子校時代のように。女性たちは自らを「女子」と認識することで、女子校のような男子不要の文化、男子のいない世界を求めているのかもしれない。それは、数年前から流行している、女子だけの集いである「女子会」ブームにも見て取ることができる。
そもそもファッション誌の世界は女子だけの国、卒業のない女子校なのだ。女子校内での女子は、男子のためにおしゃれをしたり化粧をしたりするのではない。彼女たちは男性がいなくても、さまざまな衣服に身を包み、化粧を施すのである。着せ遊びに男性はいらない。そのことを改めて教えてくれるのが、着せ替え人形である。リカちゃん人形にワタル君が必ずしも必要ではないように、バービー人形にケンが必要ではないように。着せ替え人形にとってのボーイフレンドは必需品ではなく、単なる添え物にすぎない。
(中略)
つまり、女性たちは「私に萌える」ためにおしゃれをするのである。ファッション誌の世界では当たり前となったこの「私萌え」の姿は、今やさまざまなメディアで目にすることができる。例えば、「大人女子」が愛飲する資生堂「ザ・コラーゲン」のCMでは、仲間由紀恵と水原希子率いる数え切れないほど大勢のドレスアップした「女子」たちが華やかに集っており、まるで女子大の謝恩会のような華やかさに満ち溢れている。満面の笑みで「女子」の世界を謳歌する彼女たちにつけられたキャッチコピーは「女でよかった!」である。お互いの美しさを讃えるように、コラーゲン・ドリンクを飲み、「女でよかった!」と実感し合う「女子」たち。コラーゲンを飲んで美を保つのも、単に男性を惹きつけるためというわけではない。むしろ、いつまでも私が私に萌えるため、まり卒業のない女子校の住人でい続けるためというわけだ。
そもそも、女子大生が謝恩会で自分史上最高のドレスアップをするのは、何のためなのか。それ共学よりも女子大の謝恩会の方がいっそう華やかなのはなぜなのか。たとえ、女子校は卒業しても、いつまでも卒業のない女子校の住人でいたい、という意志の表れではないだろうか。その証として、彼女たちは卒業後もことあるごとにドレスアップし、「女子会」と称して集うのである。
(pp.184-187)
当初は、化粧好きな「新専業主婦」であったはずの『美ST』読者が、いつのまにか「美魔女」となり、「フォーエバーガール」と歌っているのである。赤文字雑誌から生まれた「美魔女」が、赤文字雑誌というその枠組みをいつしか超え、「ガール」として、「好きに生きてこそ、一生女子」を標榜する青文字雑誌の領域に歩み寄っているのだ。
「美魔女」の逆襲。主婦であっても、一度は赤文字雑誌の「幸せな結婚」という生き方を選択しても、私たちはやっぱり「女子」。躍進する「美魔女」の姿からは、そのような声が聞こえてきそうである。「美」は分断していた女性たちを一つにするのだ。派閥や生き方を超えて、「美」を求める限り、私たちは「女子」なのである。
「今の自分が一番キレイだと思う。キレイでいるのは自分のため。自分がなりたい自分になりたいだけ。」(毎日新聞大阪本社版夕刊二〇一三年一〇月四日付)と語る「美魔女」。恋愛でも、他者のためでもなく、最終的には私自身のために、「私に萌える」(米澤2010)ために「美」を求めているのである。「美魔女」たちは、他者よりもむしろ、自分自身を鼓舞するための力として美をとらえているのではないか。また、彼女たちの強い自己肯定感は、当然「大人女子」と共通するものである。
(pp.152-153)
人生が、「わたし萌え」の快楽のおかげで楽しくなるのであれば、大いにけっこうなことだ。
その楽しみが「女子」のみの特権というわけではないことは、若い男性のコスメ熱が物語っている。
それにより、カネと権力に執着し、害悪をまきちらす「有害な男性性」が払拭されるとすれば、これほど歓迎すべきことはない。
男の子よ、「女子」になろう。
米澤泉,2015,女子のチカラ,勁草書房.(2.7.25)
本書は、「強くなりたい」と願い、日常の困難に立ち向かう女子を分析する。雑誌、コスメと美、下着、バッグとシューズ、ファッションビルの広告を手掛かりに、ファッションを原動力として、女子が強く生きていく姿を追う。美しさという「武器」を手に、装いという「知恵」を盾に、困難を乗り越える「女子のチカラ」を明らかにする。
なぜ彼女たちは、永遠の少女のまま自立できたのか。岡崎京子、オリーブ少女から蜷川実花まで。大人女子とファッションの関係を探る。
美しく自分を装うことは、強くなること。
「女子」という「わたし萌え」の着ぐるみをまとうことで、人生は、もっと明るく、楽しいものになる。
岡崎京子さんと蜷川実花さんが、なぜ、強力な「女子」のロールモデルとなったのか、その謎がみごとに解き明かされている。
目次
序章 前に進むために―岡崎京子とファッション誌の女子
第1章 雑誌のチカラ―『Olive』というファッション遺産
第2章 美魔女のチカラ―ポスト「コスメの時代」の美をめぐる冒険
第3章 下着のチカラ―女子を導く自由の女神
第4章 バッグのチカラ、シューズのチカラ―人生のマストアイテム
第5章 広告のチカラ―パルコの女からルミネの女子へ
終章 女子のチカラ―美しさという「武器」、装いという「知恵」