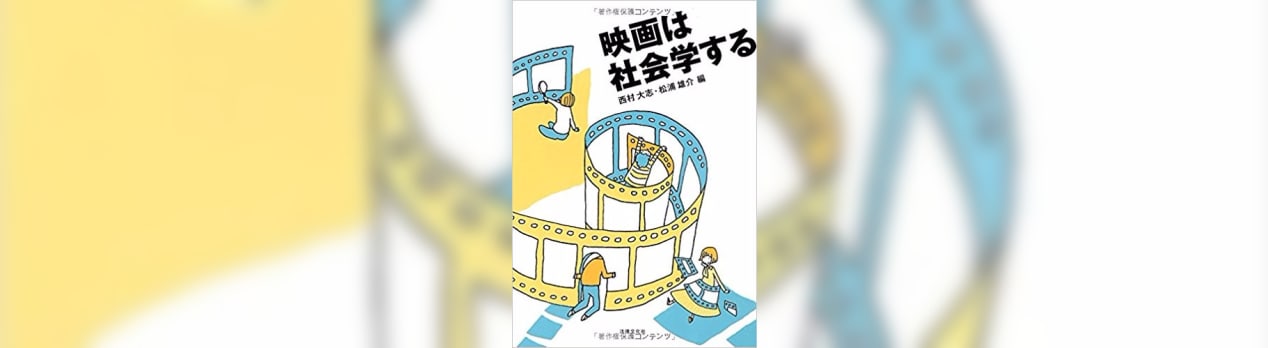
わたしの大学生時代は、出席をとる講義科目などほとんどなかった。したがって、話術が落語家なみに長けた教員の講義は聴くが、それ以外の科目は自分で本を読んで勉強しほとんど出席することはなかった。毎日が日曜日である。読書、アルバイト、そして映画鑑賞と、好きなように時間が使えた。本もたくさん読んだが、映画も見放題であった。ミゲル・リティンの『戒厳令下チリ潜入記』に衝撃を受け、ラテンアメリカ従属論や世界システム論の勉強をしたりと、「映画」はときとして「学問」への架け橋となった。
2006年より、文部科学省と厚生労働省の指示により、大学での授業はすべて出席をとらねばならないようになり、授業を1/3以上欠席した学生は、単位取得資格を失うこととなった。授業をサボって映画を観る余裕などいまの学生にはない。加えて、アルバイト、サークル活動、ボランティア活動と、とかくいまどきの学生は忙しい。読書も映画鑑賞も、学生が思う存分享受できるものではなくなっている。
それでも、近年の大学図書館のAVブースは充実しており、授業の空き時間に映画を観る学生も少なくない。映画館に行く余裕はなくとも、DVD等はウェブ上からレンタルできるし、TVやネットで配信される作品を観る機会も豊富にある。「映画」で漠然とした問題意識をもち、それを「社会学」の諸概念と接続させ、世界を理論的に説明する能力と想像力を鍛える機会は貴重である。
山中速人氏編著の『ビデオで社会学しませんか』と、大場正明氏の『サバービアの憂鬱──アメリカン・ファミリーの光と影』が出版されすでに24年が経過した。宮台真司氏の『絶望・断念・福音・映画──「社会」から「世界」への架け橋』(2004年)、『正義から享楽へ──映画は近代の幻を暴く』(2016年)などの作品はあるものの、映画を導きの糸として社会と社会学を学べる書物がもってあって良いとは誰しも思うところ、本書は時宜に適った作品といえる。
本書で、映画(邦画に限定されている)作品の内容と絡めながら解説されている社会学の概念は、動機の語彙、行為と演技、ラベリング、ジェンダーとセクシュアリティ、身体技法、組織と集団、社会関係資本、感情労働、親密性、ダブルバインド、集合的記憶、消費社会論、規律訓練と主体化、監視社会、観光のまなざし、オリエンタリズム、想像の共同体、伝統の創造、リスク社会、以上である。
どの章もよく考え抜かれて書かれており、社会学の入門書として読めるだけではなく、やや専門的な内容にまで踏み込んでいながら、文章が平易で読みやすい。ごく最近出版された社会学の某概説書が、よく書かれてはいるが退屈極まりなかったのと比べると、本書はとてもよくできていると思う。成功のポイントは、入門書として読める内容でありながら、あまりに教科書的な内容は避け、ちょうどほどよい程度の専門性を保ちながら、厚みのある記述が展開されていること、それとなんといっても、だれもが知っている映画の内容と社会学の概念が相互参照されながら説明され、現実を抽象化した表現としての映画と社会学概念とが、違和感なく接続されているからである。
映画も社会学も、現実を抽象化して表現したフィクションであることに変わりはない(と言えばコテコテの実証主義者から怒られそうだが)。ただ、映画は、モヤモヤとした思いを残すだけでそこにロゴスは希薄である。社会学は、観てそれで終わりになりがちな映画鑑賞の経験に、言葉を、論理を、そしてそれらにより構築された社会的なるものの存在とその説明原理を教えてくれる。
18歳人口の減少とともに、社会学のマーケットも縮小しつつあるが、それでも、教養としての社会学の需要は大きい。社会学の新たな概説書が毎年何冊も出版されているのも、じゅうぶんペイできるだけのマーケットがあるからだ。わたしは、「社会福祉調査法」を除き、どの講義でも教科書は使用しないが、「指定図書」として、学生諸氏の社会学的想像力を喚起し、できれば読んでおもしろく、長い人生のなかで間接的にでも役に立ちそうな内容の入門書、概説書を取り上げ、読んでおくことを勧めている。そのために、「読んでもどうせほとんど知っていることばかり」とはわかっていながら、新刊にはできるだけ目をとおすことにしているが、文字どおりの「教科書」は、読むのが修行になるほどつまらない。しかし、本書のように、ほどよい専門性と厚みのある記述、映画作品の内容と社会学概念との接続といった一工夫があれば、社会学を「教える側」もじゅうぶんに楽しめるテキストとなる。次年度の「社会学概論」の「指定図書」の一冊は、本書に決まりである。
最後に、ないものねだりであることを承知のうえで、本書が再版される機会があれば、かなえていただきたいことがある。それは、わたしだけでなく、多くの社会学者がその内容に惹きつけられた(と思われる)以下の映画作品を、本書の内容に加えていただきたいというものだ。
①渡辺文樹「ザザンボ」
②原一男「ゆきゆきて、神軍」
③園子温「冷たい熱帯魚」
①はDVDの入手が困難な作品であるが、東北の一農村にかつてあった排他的因習、障がい児の排除を取り上げたものである。映画化もされたきだみのる『気違い周游紀行』、宮本常一『忘れられた日本人』(とくに「土佐源氏」)、赤松啓介『夜這いの民俗学』ともども、「日本人」の文化的DNAについて、若い人たちにはぜひ知っておいてほしいところだ。「社会的排除」という概念とも照合できる作品である。
②は、文句なしに優れたドキュメンタリーであり、ビデオカメラのまなざしを意識し凶暴化する奥崎謙三の姿は、「メディア論」からのアプローチも可能だろう。
③は、実在の事件をもとにした作品で、②で奥崎が攻撃の標的にした戦争犯罪人と同様、「狂気」が日常化し、反転して「正常」であることの異様性があぶり出される内容である。
最後に最後、本書でわたしの勤務先の同輩が二人執筆しているよしみで公私混同して言うのではけっしてない、次年度の「社会学」の「指定図書」をどれにするのかお迷いのそこのあなた、本書をぜひお勧めする。
本書評は、某学会誌に寄稿予定のものです。
最新の画像もっと見る
最近の「本」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事















