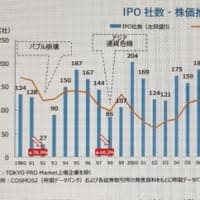アノマリー(anomaly)は標準から外れた現象のこと。金融の世界では効率的市場仮説EMHに反する特異現象をさす。しかし多数のアノマリーが発見されるにつれ、むしろ効率的市場仮説の方が仮説として間違っているのではないかと議論されるようになった。なお効率的市場仮説に代わる仮説として行動ファイナンスという分野に様々な仮説がある(私自身による行動ファイナンスの説明は市場原理主義についてを参照)。それは人間とは認識と行動において合理的存在ではないということをベースにした学問分野であり、経済学における経済主体としての人間に行動の捉え方にも影響を与えている。
| 1月効果January effect | 1月の月次投資収益率が極端に高い(日米とも)。 |
| 月曜日効果Monday effect | 月曜日のリターンが他の曜日より低い{大村・俊野} |
小型株効果small capitalization effect, small firm effect | 時価総額の小さいグループのパフォーマンスが市場の平均的なリターンよりも高い{高橋}:企業規模効果{大村・俊野};類似したものに、無名ブランド効果generic stock effect{大村・俊野}、neglected firm effect{山崎} |
| 低PER効果 | E/P比率の高い株(低PER株)ほど高いリターンを示す{大村・俊野};類似したものに、低PBR効果。逆張り的でありバリュー株(割安株)ともいえる{山崎} |
| リターンリバーサル効果 | リターンの逆転現象が生ずること、逆張り的{山崎};相場の行き過ぎの修正と解釈できる |
| 季節性銘柄 | ビール銘柄や肥料銘柄が毎年のように12月から1月に底値をつけ4月から5月にかけて天井をつけることなど |
| 1月効果 | ダウジョーンズでは見られないので「小型株効果」 前年マイナスだったものが高い リスクが高いものほど高いリターンを顕著に1月に示す |
| 週末効果 | 月曜終値より金曜終値のリターンが高い |
| 月曜効果 | 月曜は寄りつきから終値にかけて上昇する傾向がある 取引開始の45分 月曜は押し下げ その他の曜日は際立った上昇 取引終了の直前 価格が一気に跳ね上がるブリップ現象 |
| 月の前半より後半が低い |
実証研究の結果 平均値回帰(ランダムウオークの否定)が明確に否定されないこと がわかっている。以上は セイラーの『セイラー教授の行動経済学入門』ダイヤモンド社、2007年 第11章と第12章 よりカレンダー効果 などの記述の抜粋.このほか米国では大統領選挙の前年には景気浮揚策がとられるため、株価が上がりやすいとされます。しかし大統領選挙の前年にあたる2011年については、政府債務の削減問題があり、この経験則があてはまらないのではと指摘されています。
文献
高橋元『証券市場と投資の理論』同文舘,1993年, 194-195.
大村敬一・俊野雅司『証券投資理論入門』日本経済新聞社, 2000年, 89-92, 192-199.
真壁昭夫『最強のファイナンス理論』講談社, 2003
山崎元『新らしい株式投資論』PHP新書, 2007年、137‐149.
セイラーの『セイラー教授の行動経済学入門』ダイヤモンド社、2007年 第11章と第12章
ピーター・L・バーンスタイン 青山護・山口勝業 訳『証券投資の思想革命』東洋経済新報社, 2006年, 215-216. アノマリーの存在にもかかわらず、市場平均を上回る投資は相変わらず至難の業であることにかわりはないと、話を続けている。
ピーター・L・バーンスタイン 山口勝業訳『アルファを求める男たち』東洋経済新報社, 2009年, 44-47. 小型株効果を、大型株と比べた投資層の違い(分析力の高い機関投資家がほとんど入ってこないこと)、取引コストの高さ(株価が過大あるいは過少に評価されてもその状態が持続しがちであること)などから説明しようとしている。
田淵直也『ファイナンス理論全史』ダイヤモンド社, 2017
Andrei Shleifer, Inefficient Marklets, Oxford University Press, 2000, 122,182.small firm effectやvalue stock effectについては、riskの高さ(違い)からの説明があることを紹介している。また, small firm effectについては機関投資家がインデックス投資を進めるほど消滅する。またインデックス以外の投資はコストが上昇する。だからインデックス内の株式の成果がよいときは、小投資家は、インデックス内の銘柄の選択に集中することが賢明であると指摘している。
日本株アノマリー観察日記 曜日効果 2002年1月7日から2006年11月20日までの曜日効果(52週平均)の観察 この観察データ(東証株価指数)からつぎのようなことがわかる。①月曜が最も低くて金曜にかけて収益率が上昇するというパターンが観察される時期が確かにある(2003年9月22日から2004年9月6日。そして2005年8月22日から2006年6月5日。)。しかしそれは観察期間のすべてではない。②アノマリーをどのような数値の動きとして理解するか。その定義によって実証結果は微妙に変わってくるのではないか。
日本株アノマリー観察日記 旬ベースでみた月次効果 2000年1月4日から2006年4月28日までの旬アノマリーの観察(日経平均)により月次効果を旬ベースで細かくみよう。すると年末から前半にかけてかなりはっきりした収益率の変化が観察される。12月上中旬マイナス(12月の株安)。12月下旬プラス。1月上旬マイナス。1月中旬プラス(1月の株高 節分天井)。2月の上旬マイナス。2月下旬から3月上旬はプラス。3月中旬マイナス(3月の彼岸底)。3月下旬から4月上旬プラス(4月の株高)。4月中旬から5月上旬マイナス。
景気波動についてはアナマリーとしていいかは検証が必要だが、実は信じている人は少なくない。コンドラチェフ(60年)クズネッツ(20年)ジュグラー(10年)キチン(4年)が知られている。年数は概数である。
Written by Hiroshi Fukumitsu. You may not copy, reproduce or post without obtaining the prior consent of the author.
2011-09-10(2018-03-14 revised
2023-08-28 更新