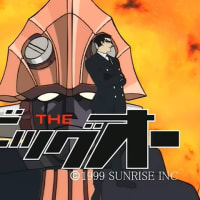私のブログにお越しいただいてありがとうございます。どうか、みなさまとご家族、関係者の方がご健康であっていただければと思っております。
さて、私の会社の机の上の週めくりカレンダーの今週のものです。。
「“未来””毎日“は創れます。今が辛くとも悲観せず、創造を続けてください。」
by ヒラヒワケ(白日別)& トヨヒワケ(豊日別)
シラヒワケ(白日別)さん、トヨヒワケ(豊日別)さんともに古事記に登場する神さまの名前です。イザナギさんとイザナミさんが4番目に作ったのが筑紫島(=九州)で、この筑紫島には4つの顔があり、そのうちの一つがシラヒワケさん、もう一つがトヨヒワケさんです。
さてさて、先日、江戸時代に肥後国(現;熊本県)に現れたというアマビエの話を書きましたが、ほかにも日本の各地には疫病除けにまつわる言い伝えや寺社が受け継がれています。
3月4日には、全国の多くの神社を包括する神社本庁が「新型コロナウイルス感染症流行鎮静祈願祭執行の件」という通知を出し、各地の神社で新型コロナウイルス鎮静祈願の神事が行われていました。
京都府京都市の八坂神社などでは、例年ならば夏に置かれる「茅の輪」が登場しました。八坂神社は創建時から疫病と深く関わりがあり、9世紀に流行した疫病を鎮めたことで知られるようになったそうです。
疫神社の祭神は、各地で信仰される蘇民将来(そみんしょうらい)さんです。言い伝えでは、旅の途中で宿を乞うた武塔神(むとうしん)さん、本当はスサノオノミコト)さんが旅の途中にお兄さんの蘇民将来さんと弟の巨旦将来(こたんしょうらい)さんに宿を求めました。巨旦さんは裕福でしたが断り、蘇民さんは貧しかったものの、できる限りの歓待をしました。スサノオさんは、そのお礼として、「茅の輪をつけていれば厄病を免れる」ということを教えてくれて、疫病が流行したときに蘇民さんの一家だけが助かったというのです。
その後、地域によって違いがあるものの、日本各地でお守りや家の門に、「蘇民将来之子孫也」と書く習慣が生まれ、神社には茅の輪くぐりが行われるようになったそうです。
今回、八坂神社には1877年9月末にコレラの流行した時以来、143年ぶりに期間外に茅の輪が設置され、それくらいの異常事態だということになります。
昔から疫病は人間の命を脅かし、医療や科学が発達した現代でも、そう簡単に克服できないことがあらためて感じられます。それだけに、医療や科学が未発達だった時代には、疫病はとてつもなく恐ろしいものであり、神仏に祈るしかないというのは人間として自然なことだったでしょう。
これまでも多くの疫病が繰り返し流行し、人間を苦しめてきました。それでも、人間は最終的に乗り越えてきました。
新型コロナウイルスによって、多くの人の今までの日常だった生活が非日常になってしまいました。まだまだ終息は見えていないため、不安な状態がしばらく続くと思います。
でも、「未来」「毎日」を創るのは、誰でもない私たち一人ひとりです。
今が辛くとも悲観せず、創造を続けていかなければならないでしょう。
未来に生きる人たちのためにも・・・ですよね。