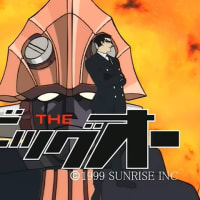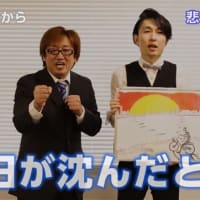「おひたし」とは、野菜をゆでて、かつおぶしや昆布からとった出汁(だし)と、しょうゆなどを合わせた調味液にひたした料理のことです。和食の小鉢でよく見かける料理で、いろいろな季節の野菜を使ったおひたしがあります。
おひたしの始まりは、「浸し物」と呼ばれていたらしく、奈良時代からこの調理方法があったと推察されており、江戸時代には、「煎り酒(煎り酒(いりざけ:日本酒にうめぼしなどを入れて煮詰めたもの。江戸時代中期ころまで醤油が普及する以前に使われていた)や酢で味付けしたり、いりこやくらげなどの海産物を使ったおひたしもあったそうです。
その後、明治時代以降になって現在のような野菜などをゆでて出汁しょうゆに合わせるようになったようです。
これからの季節ならば、「菜の花」などもいいですし、何といっても定番としては、「ほうれんそう」や「こまつな」です。
(ほうれんそうが、ほとんど見えていません)
さて、「ほうれんそう」ですが、会社生活などでよくいわれる、上司への「報告・連絡・相談」、いわゆる「ほう・れん・そう」があります。これに対して、上司が「怒らない・否定しない・助ける(困り事あれば)・指示する」の、「お・ひ・た・し」というものがあります。
特に入社したての新人への教育で、「ほう・れん・そう」を求める中で、「お・ひ・た・し」を心掛けていると、良くない内容でも早めに相談してくるようになるので、対応が早くできるようになります。また、「困らせない・迷わせない・詰めない・悩ませない」という、「こ・ま・つ・な」というのも大事だと思います。
「ほう・れん・そう」を行うように指示する上司にマナーがなければ、部下はついてこなくなるものです。
おひたしには、出汁の合わせ方が大事です。いくら、新鮮でいい野菜であったとしても、野菜の味を活かす出汁が美味しくなければ、主役の野菜が活きてきません。
また、野菜をゆでて出汁に合わせたものならば、すべておひたしですので、野菜の数だけおひたしの種類があると思ってもいいと思いますが、一番おひたしに合う野菜は、やっぱり、ほうれんそうになると思います。
ほうれんそうのおひたしはあなどれません。
今日も、私のブログにお越しいただいてありがとうございます。
今日がみなさんにとって、穏やかで優しい一日になりますように。そして、今日みなさんが、ふと笑顔になる瞬間、笑顔で過ごせるときがありますように。
どうぞ、お元気お過ごしください。また、明日、ここで、お会いしましょう。






![[ 閲覧注意 ] どういう状態になったかと言うと・・・](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/46/ff/52ba0cd2fa20b2d36331b107d2ce63e4.jpg)