朝日記151015 表現の曖昧さについてとHeideggerへの読み筋をみつけつこと
10・15おはよう
みなさん、おはようございます。
徒然こと
今朝は紅白色に金色の縁の雲に見とれました。
ラジオ体操もTシャツに長袖シャツで温度調節したり
選択に迷います。ずいぶん日も短くなりました。
道に落ちていた柘榴の実や花梨の実が片付けられ、
秋萩が勢いよく張っていたその元枝も始末され、まだ金木犀のかおりがのこっていたりです。毎朝ほぼ同じ道筋でスケッチの対象を探したりしているのでちょっとした季節のかわりの気配を目にします。 柑橘の剣のような葉ぶりや、柿の実のたわわな枝ぶりなど、それをいかに描くかをながめるのもおもしろいです。 この数日は、柳の木炭でさっと描き、家に帰ってフィクサティフのスプレーをかけ、定着させます。
この霧の芳香が毒だと家内は警戒します。 すこし絵を大きくするために、同じものを描くのは如何なものか、抵抗を感じていましたが、スケッチしたものを横において、意を決して描くと 線の強弱が生き返ってきて うれしく感じることもあります。 大学の図書館で古い本で「曖昧さ」について書いてある本があって、あまり読む気もなかったのですが、結局手にとりました。 英国人の著で、曖昧に表現することから生まれる効果などが、詩を中心に解説し論じていました。そのなかで、英国の風景画家コンスタンチンのことが、目にとまります。かれは、同じ絵を三つ描くのですが、最初のは素描レベルのもので、つぎに、それを基にし制作し彩色したもの、そして最後に作品として制作したものです。そして 後世に評価を得たものは、かならずしも最後のものではなく、二番目のものが多かったというようなことであった。
そんなことでした。 また手に取ってみようかとおもっています。 (龍口寺にて)
(龍口寺にて)
徒然こと 2
institutionとagencyについての資料をつくって、総合知学会の月例会で話をしました。質疑をいれて3時間で 声帯のリハビリもさることながら、体力がものをいいます。その質疑の展開で、スタンフォードの哲学者John Searleを使って、存在論と認識論との接合的な話し、カントの哲学のフレームに帰着させるような話をいたしました。
質疑のなかで、SearleのいっていることはHeideggerの言っていることとすべて同じだという指摘がありました。 SearleはHeideggerを引用しているのかというあたりで、答えて読んでいないのではないかといって、軽率さを露呈してしまいましたが、米英系は彼をナチ主義との関係で敬遠している経過もあり、妙に納得したひともおられました。
二日ほどまえから、図書館から借りていた「存在と時間」をとりあげ、読んでいます。「現存在」とか「実存」などがでてきて いつもは退屈するのですが、前者を「agency」とし、後者を「institution」と置きなおして読んでいくと、おもしろいほど 話の筋が見えてきて、退屈ではなくなりました。そんなことをご報告いたします。
(江ノ電江の島駅)















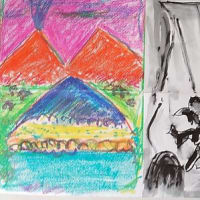









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます