朝日記181008 日本絵画とコンピュータ世界についてと今日の絵(No.8330 )
おはようございます。
きょうは、日本絵画が 現代世界思想に発信していることを バーリンスキーとロラン・バルトの二人に焦点を当てて、徒然ことを綴りました。ご覧ください。
絵は(無理は禁物だよ、キツネ君)と(骨組み) です。
(なお、キツネ君は、10月9日から11月9日まで町田市民ホールのメインアリーナに美術協会受賞作といsて 飾られます。)
徒然ことは以下三つです:
徒然こと 1 バーリンスキー 日本絵画とコンピュータ世界~記号化と情報としての表徴としての絵画
徒然こと 2 ローラン・バルト 画面空間を緻密にペイントするだけでは、包含しきれない表現体としての日本絵画
徒然こと 3 見下されていた方が、本来上だったかもしれない
 (無理は禁物だよ、キツネ君)
(無理は禁物だよ、キツネ君)
 (骨組み)
(骨組み)
~~~~~~~
徒然こと 1 バーリンスキー 日本絵画とコンピュータ世界[1]
~記号化と情報の表徴としての絵画
人間はみるものを対象として捉え、表現しようする 涙ぐましい努力をつみかさねてきたといえる。 その典型は、対象の言語論理化をへて概念化つまりロゴス化である。 しかし、これがすべてではない。人間が五感でとらえたものを、非論理媒体、音、像、味覚、嗅覚、触覚など器官を通じての感受と、それを介しての表現伝達であらう。つまりパトスである。 さらに、人間が群れを構成し、生存するための同意や、約束やルールを創りだし、交渉し、遵守していくための表現の意識とその規範化がつづく。つまりエトスである。
ロゴスという点に重心をおいて近代文明の成立基盤をみるなら、ニュートンやライプニッツに代表される近代科学に帰し、その功罪はあったとしても、現代文明がその系譜のうえにあるとみることには異論がないであろう。
ニュートンについては、宇宙全体にたいして統一原理をめざす物理学を構築し、近代文明のひとつの系譜を形成したそのシンボルとして世界が認めるところである。ニュートンのは対象を物質原理に一元集中し、その探求の結果から普遍原理を求めるものであった。
一方、ライプニッツは、バーリンスキーの表現を借りると、「ときとして、自分が表現しきれない計画に取り組んでいたよう」であったと指摘する。百科全般にわたって、壮大な体系が(少なくとも論理上)が本来あるものとして、個々の思考の括りのなかでは、未だ、はたらいていなくても、それらは、抽象度が増す方向へと発展し、統一的な原理への到達を考えていたようである。
バーリンスキーのその説明イメージとして、日本の伝統的絵画を西洋絵画ととりあげ、前者をライプニッツ、後者をニュートンと対比したところに筆者の素朴な興味をひいたのである。
彼に語らせよう。
「ライプニッツは百科事典からその内容の痕跡をすべて取り除きあとに残ったものを純粋な記号と形式の体系のみに注目した。」これを丁度以下のイメージとして日本の絵をしるしている。「日本の画家が最後にはパレットから黒を除くあらゆる色を取り去る(そして黒と対照をなす白を紙そのものに求める)。」
つまり、 絵をみるものにとっては、表現するもの(対象)は、網膜に写るものを、像として対象認知し、表現イメージとして「対象化」される。 その「対象化」の過程は、ふたつに分かれると考えられる。ひとつは 象形文字への記号化の意識転換と表現操作の活動として、具体的には「筆」を経て、表現体が制作される。現在では「書道」もしくは「書」とよばれている。もうひとつは、象形文字に限りなく接近するが、表現イメージの「対象化」としての象形文字への記号化を嫌い、さらに言語による概念化を嫌う。画家の意志は、潜在的な意識からのものであり、その意志が対象の形を通して、対象のもつ属性を取捨捨象し、対象のなかから画家の願望を引き出そうとする活動がはじまる。対象は意識のなかのイメージへと形象し、転換し、凝縮し、表現体が制作される。 これを「絵画」とよんでおく、そして有限な線の構成する記号化として発信した。
非常に興味深いのは、ものごとの認識が、ニュートンの第二法則のように物質の統一法則からの派生として得られるというものに対して、ライプニッツは、物理学の法則をも包含した大き原理を想像して、この追求は、その途中で、多様性や複雑性を認めなければならす、それを論理表現化するために「記号」いう概念を導入している。
現代では、「記号」、「情報」そしてこれを計算処理する「アルゴリズム」が、人類社会に機能し、拡大作動原理化させていると彼の論を展開する。
日本の伝統絵画が、われわれ自体が感得して、感性への純化を意識するのとは、まったく別に、「記号論」というライプニッツ的な新しい思想パラダイムへと啓蒙を与えているところに、人類世界共通のあらたな価値を教唆するものを感じたのである。バーリンスキーは 皮肉にも、日本絵画から、あたらしいコンピュータ社会の示唆を得たともいえる。
徒然こと 2 ローラン・バルト 画面空間を緻密にペイントするだけでは、包含しきれない表現体としての日本絵画[2]
ロラン・バルトRoland Barthesは、一世を風靡したフランスの構造主義に文化人類学者といわれる。
「ルーツ・ベネディクトの「菊と刀」での日本人論について、この世界の状況を垣間見るために、図書館で放送大学教材「表象としての日本 ―西洋人がみた日本文化―」を出会うことになった。
バルトは、つぎのように説く;「西洋では絵筆とはあくまでも絵の具を壁面に塗装する道具である。これに対して漢字文化圏にあっては、絵筆は同時に書の筆でもあり、顔の、そして目と、それらを書く(ècrit)。 けれども塗装するpaintingわけではない絵筆のことがその描線の役割り」をもつ。このècritureの本義なのだから。」
この世界でも、理系世界の「アルゴリズム」とは、直接 渡り合っていないようであるが、ècriture記号の意味論 つまりSemioticsは重要らしい。バルトは、記号論での彼の拡張として 画面空間を緻密にペイントする西洋絵画では、包含しきれない表現体としての日本絵画の「虜」になってしまったようである。 その「書く」ècritureは、多分 日本語での「描く」で、英語のdrawとは基本的に異なるとみたようだ。バルト曰く;「ècritureは「書く」にあたるècrireら派生し、ふつうには文体や筆跡、さらに一般にその結果としての文字一般を意味する。(中略)さらには筆記する行為そのものまでも含む概念が、ècritureであり、(中略)そこに作品内容や作家の政治的イデオロギーなどには還元できない。「書体」の純粋形式を探ろうとしてきた。(中略)バルトは、これに置き換え可能な便利な言葉は、日本語には見いだせないが、その当の日本にこそ、自らの革新あるいは妄想に、ècritureの理想郷を見いだした -ことになる。」
彼にとっては、大げさにいえば西洋にとって大変な発見ともいえる。 ここでは、アルゴリズムとは一見逆に、言語論理の可能性の喪失ともいえる。( 筆者は、言語論理のみによるに認識可能性の限界を暗に示唆する点では 両者共通しているとみている)
ここでは、画面空間を緻密にペイントするだけでは、包含しきれない表現体としての日本絵画としてまとめておきたい。
徒然こと 3 見下されていた方が、本来上だったかもしれない
 (無理は禁物)
(無理は禁物)
バルトの言をつづけてみよう[3];
「当初謎めいていた道の対象 -日本人の行動や倫理意識 -が、分析と記述を経ると、むしろ理解可能なものへと変貌してゆく。それた裏腹に、今までと全と思っていた自分たちのふるまいのほうが、なにか奇妙で説明をようするような『気分におそわれる。これは人類学者グリフォード・ギアツが、ルース・ベネヂクトの『菊と刀』(1944)[4]を再読した論文で述べた逆説だった(『文化を読む』。
さらに、「知的理解は、その対象を「自然」らしく見せ、最初は不合理に見えたその有様を「合理化」する。だがその過程で、認識主体が当初、対象に対して抱いていた不思議さは、いやおうなく色あせてしまう。」
バルトは、「日本」の記号に、「けっして自然を装ったり、合理化されたりはしない」様を見て取った。言い換えれば、バルト自身の「日本」へのまなざしは、この「日本」という記号に、偽りの「自然さ」や辻褄合わせの「合理化」を施すような、蛮行は、これを、最初から決然として放棄していることになる。」
つまり、バルトは、理解不能なるものに直面した認識装置の自壊告白という系譜学として
発見の興奮と方向性の喪失感のなかにあったようである。グリフォード・ギアツのいう 見下していた方が、本来上だったかもしれないということであるが、さて、我が国での哲人諸賢はいかにあるか、気になるところである。
以上












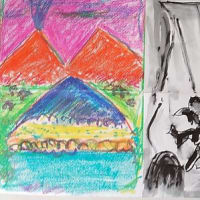













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます