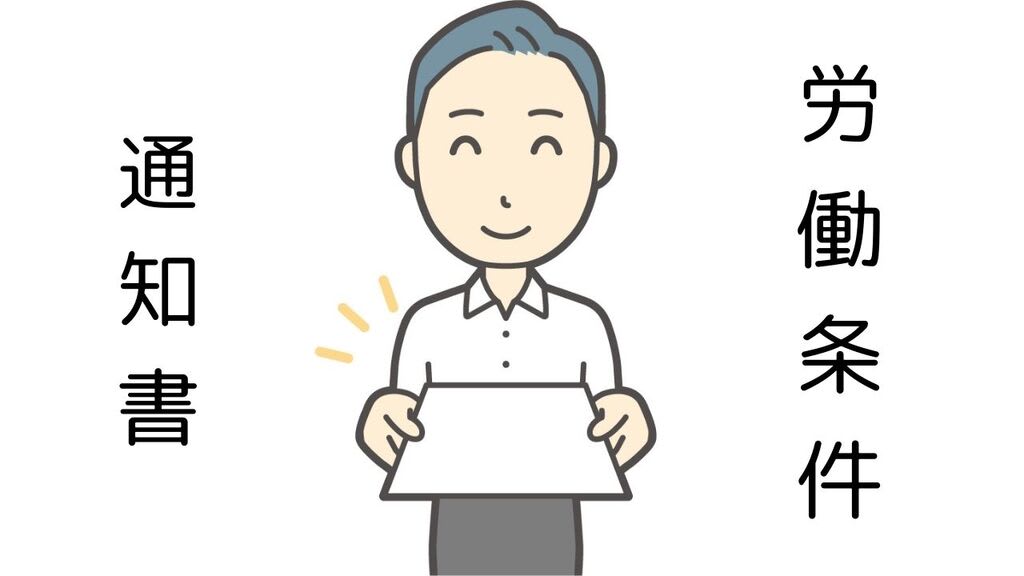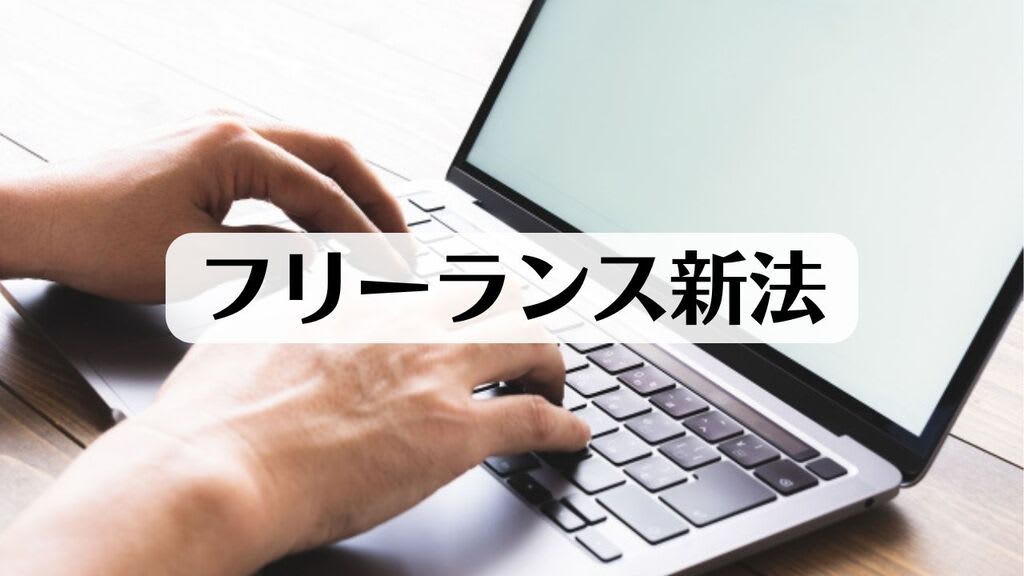みなさんこんばんは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。前回の記事では、労基法15条の「労働契約の解除と帰郷旅費」について解説しました。今回は、労基法16条の「賠償予定の禁止」について解説しようと思います。短い条文なので、まずはそれを確認してみましょう。
労基法16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
これだけです。「違約金」とは、労働者が労働契約をちゃんと守らない場合(無断欠勤するなどの場合)に、損害発生の有無にかかわらず、労働者が雇い主(使用者)に支払うお金のことです。要するに「罰金」です。キャバクラなどによくありますよね、「無断欠勤したら1万円の罰金とする」みたいな決まりが。ああいう契約を結んではならない、ということです。
労基法16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
これだけです。「違約金」とは、労働者が労働契約をちゃんと守らない場合(無断欠勤するなどの場合)に、損害発生の有無にかかわらず、労働者が雇い主(使用者)に支払うお金のことです。要するに「罰金」です。キャバクラなどによくありますよね、「無断欠勤したら1万円の罰金とする」みたいな決まりが。ああいう契約を結んではならない、ということです。
もしこの法律がなかったらどうなるか。「6か月以内に退職したら罰金100万円とする」などの契約が可能になり、そうなると労働者に「退職の自由」がなくなってしまいます。これは強制労働に近しい状態と言えます。だからこの法律が出来たというわけです。
「損害賠償額の予定」とは、労働者が労働契約をちゃんと守らない場合(遅刻するなどの場合)に、労働者が雇い主(使用者)に支払う額をあらかじめ決めておくことです。これも、損害発生の有無にかかわらず、労働者はお金を払うことになります。要するに「罰金」です。つまり「違約金を定める契約」と「損害賠償額を予定する契約」は、ほぼ同じ意味です。雇い主と労働者のあいだで、キャバクラなどによくある「無断欠勤は罰金1万円」みたいな契約を結んではいけないのです。
じゃあなぜ、キャバクラなどには「罰金制度」があったりするのかと言うと、キャバクラ嬢は労働者ではない場合があるからです。キャバクラ嬢が個人事業主(フリーランス)としてキャバクラの店主と契約し、店主の指示や命令を受けずに客にサービスを提供していれば、労働者ではありませんから、労働基準法も適用されず、「遅刻したら罰金5千円」みたいな契約も有効になります。
でも、キャバクラ嬢が店主の指示や命令を受けて客にサービスを提供していると(メイドカフェのメイドさんをイメージしてください)、その場合は労働者とみなされて、労働基準法が適用されます。なので、もしそのキャバクラ嬢が店主に「無断欠勤したら罰金1万円ね」と言われていても、罰金を払う必要はありません。その契約は労基法16条に反していて無効だから。
キャバクラやスナックの中には、どう見ても労働者であるキャバクラ嬢やホステスに「罰金」を払わせているお店もあります。それは労働基準法違反なので、キャバクラ嬢やホステスは罰金を払う必要はありませんし、経営者はそんな制度は撤廃しなければなりません。「労基法にそんな決まりがあるなんて知らなかった」ということなのかもしれないけど、労働者を雇うのであれば、「労基法を知らなかった」では済まされません。
「損害賠償額の予定」とは、労働者が労働契約をちゃんと守らない場合(遅刻するなどの場合)に、労働者が雇い主(使用者)に支払う額をあらかじめ決めておくことです。これも、損害発生の有無にかかわらず、労働者はお金を払うことになります。要するに「罰金」です。つまり「違約金を定める契約」と「損害賠償額を予定する契約」は、ほぼ同じ意味です。雇い主と労働者のあいだで、キャバクラなどによくある「無断欠勤は罰金1万円」みたいな契約を結んではいけないのです。
じゃあなぜ、キャバクラなどには「罰金制度」があったりするのかと言うと、キャバクラ嬢は労働者ではない場合があるからです。キャバクラ嬢が個人事業主(フリーランス)としてキャバクラの店主と契約し、店主の指示や命令を受けずに客にサービスを提供していれば、労働者ではありませんから、労働基準法も適用されず、「遅刻したら罰金5千円」みたいな契約も有効になります。
でも、キャバクラ嬢が店主の指示や命令を受けて客にサービスを提供していると(メイドカフェのメイドさんをイメージしてください)、その場合は労働者とみなされて、労働基準法が適用されます。なので、もしそのキャバクラ嬢が店主に「無断欠勤したら罰金1万円ね」と言われていても、罰金を払う必要はありません。その契約は労基法16条に反していて無効だから。
キャバクラやスナックの中には、どう見ても労働者であるキャバクラ嬢やホステスに「罰金」を払わせているお店もあります。それは労働基準法違反なので、キャバクラ嬢やホステスは罰金を払う必要はありませんし、経営者はそんな制度は撤廃しなければなりません。「労基法にそんな決まりがあるなんて知らなかった」ということなのかもしれないけど、労働者を雇うのであれば、「労基法を知らなかった」では済まされません。
第16条に違反した雇い主は、6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科されます。
ちなみに、実際に労働者から罰金を取っていなくても、「罰金の契約」をしただけで違法になりますので、経営者の方は気をつけてください。労働者の方は、「それって労基法違反じゃないですか?」と言ってやりましょう。
以上の解説は、水町勇一郎先生の『労働法』を参考にして書きました。労働法に関してかなり深いところまで理解できる、おすすめの本です。
私は社会保険労務士の資格も持っており、先日noteに『【貧乏】できるだけお金をかけずに社労士に合格する方法【2025】』という記事を投稿しました。文字数は合計で2万字近くあります。社労士試験に関して私が持っている知識と経験を惜しみなく注ぎ込んだ記事です。「社労士試験を受けてみたいけれど、出来るだけお金はかけたくない!」という方がおられましたら、ぜひ購入をご検討ください。