大前提として、リストカットした過去があっても就職できると思います。リストカットした過去があれば就職できないと実証する研究は皆無だと思います。
当記事では、「大学キャリアセンターのぶっちゃけ話 知的現場主義の就職活動」(沢田健太著、2011)の内容を引用、検討します。
大学キャリアセンター職員である著者が大学キャリアセンターの事情、大学生の就職活動に切り込む本書。類著がことごとくスルーしていることに切り込んでおり、私は就職活動に役立つ本として以前紹介させていただきました。
ただ、著者の中で支援方法が確立していないと思われる部分があり、当記事は当該部分をフォローすることを一つの目的とする記事です。
当記事では、3章構成とします。1章で上記本該当部分の引用検討、2章で著者を含む大学キャリアセンター職員への提言、3章でリストカットした過去のある大学生の方へのアドバイス、と続けます。
長い記事になりますが、ご容赦ください。
1 リストカットの跡がある学生に対する対応の検討
本書178頁で、学生の手首にリストカットの跡を見つけた場合の具体的対応が記されている。
しかし、「こうした学生は満たされない承認欲求に突き動かされてキャリアセンターを訪れるため、生産的な相談の場にはなりづらい。ぎくしゃくとしたやりとりが、一時間、二時間と続くという事態も覚悟せねばならない」(同書179頁)と記し、現実を吐露している。
以下、私の考えを箇条書きにして記します。
①承認欲求自体は自然な感情。当然私にも承認欲求はある。
②キャリアセンター職員が学生を承認することも重要だと思う。著者も具体的対応として「しばらくは聞き役、うなずき役に徹する」(同書178頁)と記していることから、学生を承認することの必要性は認識しているものと思われる。
③「生産的な相談の場にはなりづらい」としているが、「生産的」のハードルを高く設定しすぎではないかと思う。就職に直結する相談、提案を「生産的」として目標とすると、相談者も相談を受ける職員も苦しくなると思う。
少しばかり前向きな行動変容といった達成できそうな目標を設定し、相談の場を少しでも明るいものとした方がいいと思う。
④やりとりが「ぎくしゃくとした」ものとなる理由は判然としないが、職員側の原因として疑われる事情が一つある。リストカットの跡に気づいたにもかかわらず、リストカット(自殺未遂)について相談の俎上にのせていないのでぎくしゃくするのではないかと思う。
職員は、自殺を考えている(かもしれない)人と自殺について語ることは望ましくないと無意識に考えているのかもしれない。
しかし、そうした考えは相当疑わしいと思う。「自殺対策を推進するために 映画製作者と舞台・映像関係者に知ってもらいたい基礎知識」(WHO 訳 自殺総合対策推進センター 2020)によると、そうした考えは「迷信」であり、「隠し立てせずに自殺について語り合うことは、自殺関連行動を助長するのではなく、その人に自殺以外の選択肢や考え直す時間を与えることができる。その結果、自殺の防止につながる」としている(基礎知識11頁)。
2 キャリアセンター職員への提言
1を参考にキャリアセンターへの提言を考えると、以下の通り。
学生の手首にリストカットの跡を見つけた場合、しばらく聞き役に徹し信頼関係を構築した辺りで体調について気遣うことがいいと思う(「少し元気なさそうだけど体調大丈夫?」といった感じ。)
「大丈夫です。」という答えが返ってきたら、表面上気にせず相談を続けていいと思う。目標設定でハードルを上げすぎないことは必要だと思うが。
場合によっては、誰かに話したいと思っていてリストカットについて告白することもありうると思われる。その場合は、リストカットについても相談の俎上に乗せ、自殺以外の選択肢を考えるきっかけを作るといいと思う。
3 大学生へのアドバイス
リストカットに至る事情は色々かと思いますが、就職活動に関するアドバイスは基本他の学生の方と一緒です。強いて他に挙げるとすれば自分の体調(メンタル面含む)を気遣うことです。仕事が難しいくらいの体調でしたら、無理して就職活動を継続するのは得策ではないと思います。体調を回復させてからというのが良いと思います。
後、先にも記しましたが承認欲求は自然な感情なので、承認してくれる人を探すことはいいことだと思います。そういった人に元気づけてもらいながら就職活動を無理のない範囲で続けることが就職につながると思っています。











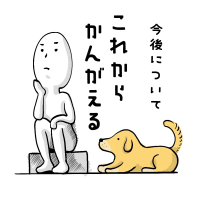
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます